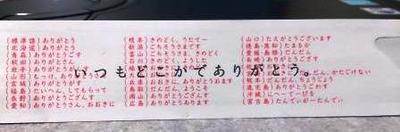大学・学部3年生の講義で、「植物育種学I, II」というのを日向先生から講義を受けた。出張先なので、当時のノートはないが、最初は、光合成、耐病性とか、育種、つまり、品種改良を考える上で考えなければならないポイントだったような。もちろん、他の講義でも聴いたことがあるようなことを何度も聞いたような。。。後半になってくると、実際の育種・品種改良をするためには、どのようなことが問題となり、どのような方法があるかの講義となった。そのときに考えないといけないのは、自家不和合性を持っているような他人の花粉で種子形成が起きる「他殖性」の場合と、自分の花粉でも問題なく自殖弱勢が出ない、イネのような「自殖性」の場合。自殖性であれば、簡単にというわけでもないかもしれないが、純系は作りやすい。一方、他殖の場合は、自殖弱勢が出て、雄性不稔などが現れることから、単純に自殖を繰り返すわけにはいかない。また、純系ができても、どの組合せとどの組合せがよいのか、など、最終的には、たくさんの子孫ができた中から、そのときの社会情勢あうような形質を持った系統を選抜することが大事になる。ただ、実際に育種・品種改良をしたことがないものが言うのは、おこがましいが、それぞれの親の持つ形質、それがどのように子孫に受け継がれるのか、結果、どの系統を選抜するのがよいかというのは、その選抜する眼を持たなければならない。現場の人に言わせると、10年も特定の作物を見ていれば、この系統が使えるというのが見えるらしい。確かに、30年近くアブラナを見ているが、このままの栽培では、よくないとか、そうしたことくらいはわかるようになったような気がする。それぞれの系統の特性を理解して、この場面では使いにくいけど、別の場面では活用できると言うこともある。そうしたことを理解して、育種して、品種にするというのは、植物育種学を学んだものとしては、いろいろな場面で考えないといけない、そんな気がする。

今の研究室は、植物育種学という名前にすることはできなかったと言うことと、遺伝学をやりたかった、生殖という形質を扱っているので、「植物生殖遺伝分野」とした。何れ、植物、作物を扱い、その遺伝子の機能を決めるということが目標である。では、遺伝子がわかれば、その植物、作物が理解できるかと言えば。。。確かに一面、理解できるように思う。例えば、その遺伝子が機能しないと、おしべが花びらに変化するとか。確かに、理解できるように思える。ところが、どのような化学反応が起きたのか、もっと言えば、分子とか、原子のレベルで何が起きたのかという理解にはなっていない。つまり、生き物として、大まかには理解できたのかもしれない。ただ、そうはいっても、もっと小さなレベルで見たときに起きていることまで、理解できたというわけではない。つまり、どの次元でわかっているのかと言うことを理解した上で、今の現状を把握して、さらにつぎに進めると言うことを考えないといけない、まだというか、そんな時代のような気がする。では、そうしたことがいつできるようになるのか、。。ずっと先かもしれないし、異分野との交流で、意外と近いのかも。。。簡単には予想できない感は否めない。。。
植物で遺伝子の解析をしたフロントランナーというのは誰かというと、。。これは、古い文献を調べればわかることである(たぶん、1980年代には、遺伝子がクローニングされていたと思うが、それが誰なのか、何なのかは。。。比較的早いのは、花の花色だったような。。。違っていたら、すみません。)。では、品種改良のフロントランナーとなると、。。これも、教科書的には、集団育種法とか、F1雑種育種法というのが、書かれていたが、それを厳密に誰が最初にと言うのは、書かれてなかったような。。。もっと言えば、品種改良というのは、人類が野生にあったものを、これは食べることができると言うことから、選抜し、さらなる改良をしたわけで。。。そうなると、そのフロントランナーを歴史から探すのは、ほぼというか、不可能であろう。少なくとも誰もやっていないことにトライして、その時代時代で、ここまではできるということをしたからこそ、現時点での優秀な農作物が確立されているのであろう。
ということを、愛媛出張をして、菜の花が咲き乱れている自然を見ながら、ふと感じた、雨のお彼岸の中日であった。。。

わたなべしるす