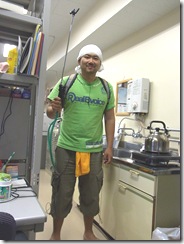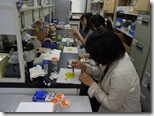今回の講義は、6/17に七北田小学校で行った「キャベツとブロッコリー」という身近なアブラナ科野菜を通して、それが同じ種であることを説明し、それらを交配したら、どんな植物、野菜ができるのだろうかと言うことを考える講義を行いました。当日は、保護者の方も来るような講義になっており、多くの方に参加頂いたのは、講義をした方としてもうれしい限りでした。実際には、キャベツの断面、ブロッコリーの断面などを見ながら、どうなるか考え、模造紙にその絵を描いてもらい、発表してもらいました。子どもさんたちだけでなく、保護者の方々にも参加頂き、発表してもらいました。子どもから見る大人の絵、逆に大人が見た子どもの絵がどのように写ったのか、自宅に帰ってから、その話で会話が弾んだり、食育の話になったのであれば、幸いです。
今回の講義は、6/17に七北田小学校で行った「キャベツとブロッコリー」という身近なアブラナ科野菜を通して、それが同じ種であることを説明し、それらを交配したら、どんな植物、野菜ができるのだろうかと言うことを考える講義を行いました。当日は、保護者の方も来るような講義になっており、多くの方に参加頂いたのは、講義をした方としてもうれしい限りでした。実際には、キャベツの断面、ブロッコリーの断面などを見ながら、どうなるか考え、模造紙にその絵を描いてもらい、発表してもらいました。子どもさんたちだけでなく、保護者の方々にも参加頂き、発表してもらいました。子どもから見る大人の絵、逆に大人が見た子どもの絵がどのように写ったのか、自宅に帰ってから、その話で会話が弾んだり、食育の話になったのであれば、幸いです。 どこの班も皆さん、よく考えており、とても楽しい絵を描いて、プレゼンしてくれました。今年になって、最高に蒸し暑い日であり、午後から2コマの連続授業であったにもかかわらず、集中して、お話を聞いてもらい、絵を描いて、プレゼンをして、質疑応答をしていたのは、とてもすごいと思いました。これからもがんばって下さい。秋からは、実際に自分たちで、キャベツとブロッコリーを栽培して、その雑種を作ろうと言うことになり、先生方とも打合せを行いました。
どこの班も皆さん、よく考えており、とても楽しい絵を描いて、プレゼンしてくれました。今年になって、最高に蒸し暑い日であり、午後から2コマの連続授業であったにもかかわらず、集中して、お話を聞いてもらい、絵を描いて、プレゼンをして、質疑応答をしていたのは、とてもすごいと思いました。これからもがんばって下さい。秋からは、実際に自分たちで、キャベツとブロッコリーを栽培して、その雑種を作ろうと言うことになり、先生方とも打合せを行いました。 最後になりますが、今回の授業を競って頂いた先生、保護者の方々に感謝したいと思います。ありがとうございました。また、秋以降にお会いできるのを楽しみにして。
最後になりますが、今回の授業を競って頂いた先生、保護者の方々に感謝したいと思います。ありがとうございました。また、秋以降にお会いできるのを楽しみにして。わたなべしるす
PS. 講義中にもいくつか質問を頂きましたが、最後にもこの様な質問が。。。「で、キャベツとブロッコリーを交配してできる植物の答えは?????????」。世の中全てのことに答えがあるわけでなく、答えがないも、わからないことが自然なこともたくさんあります。だからこそ、どうなっているのだろうと考えることが大切になります。最初と最後だけ理解して、その考える過程を抜きにするのは、サイエンスをする心を育てると言うことには、遠くなります。ぜひ、考える習慣をつけましょう。