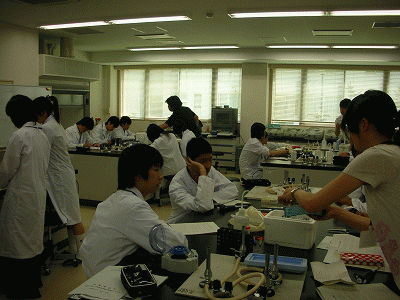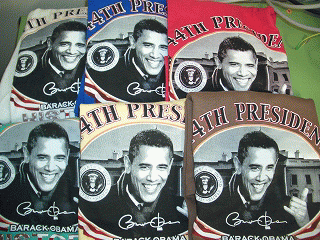
増子@今日から仙台七夕、です。
8月に入り、アーケードに吹き流しが掛けられる時期になると、本格的に夏が来たんだなと感じます。
今年も食事で学外に出るついでに、色々見て回ろうと思っています。
数分で街中に出れるのも片平キャンパスならでは。有難い限りです。
さて、話は少し前に遡りますが、7/18~22のハワイ学会のお土産に、渡辺先生が学生のお土産にオバマTシャツを買って来て下さいました。
全部で6枚、色違いです(ブルー、レッド、クリーム、グリーン、ブラウン、ホワイト)。
さながら、オバマ6兄弟です(笑)。
並べるとなかなかファンシーな図ですが。。。(写真参照)
オバマ大統領の素敵な笑顔がラボに南国の風を運んできました。
これをジャンケンの争奪戦で各人に分配。
壮絶な男の戦いが繰り広げられ。。。無事、↑の通りに分配されました。
最後に、皆で着てオバマと共にアロハポーズ!
そういえば、アロハポーズとウィッシュ(by.DAIGO)のポーズって、似てるなあ。。。
そんな脈絡のない想像が駆け抜けた、イネサンプリング前夜でした。
今年もイネチーム藤岡軍団長の元、サンプリング期間に入っています。
9月までの長丁場なので、バッチリがんばれ、くらいのテンションでいきたいところ。
イネサンプリングも、Yes, We can!の精神で頑張っていきます!
ますこ
余談ですが、
もう一つのハワイ土産(あぶないロコボーイ&ガールボールペン(by.高田さん))も大好評でした。
これは。。。
あぶなくて写真掲載できませんので、植生渡辺グループメンバーに直接見せて貰って下さい。