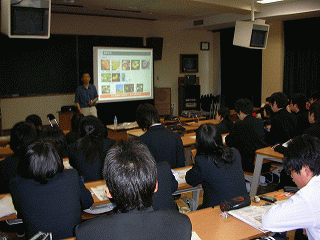5/16-17にオープンラボを行いました。ポスターを見て、説明を求めてこられた方、そのあと、研究室に来られた方など様々でしたが、多くの方々に興味を持ってもらえたことは、感謝に堪えません。ありがとうございました。これからも、研究室への訪問、mailでの質問など、常時受け付けておりますので、ご連絡お待ちしております。
ぜひ、来年から、新しいメンバーを迎えて、自家不和合性、耐冷性、small RNA等の研究を発展できればと思っております。こちらもみなさまの期待に応えられるような研究成果をこの1年で出したいと思います。
新しいメンバーが増えることを祈りつつ。。また、良い成果が出ることを祈りつつ。。
わたなべ