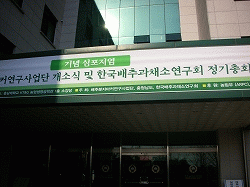つい先日まで、三寒四温で、春は遠いと思っていたら、あっという間に菜の花が咲いて、実験のシーズンになりました。菜の花がたくさん咲き始める来月には、イネの材料の準備です。春、夏、秋と季節が変わって、サンプルがあるのは、良いことだと思います。
さて、前置きはこれくらいにして。topページにもあるとおり、5/10-11でopen labがあります。現在、3年生で新しく心機一転、大学院をかえてという方、ぜひ、お越しください。5/10の午前中は、研究科全体の説明会です。生命科学の大学院生向けの、全体の説明があります。午前中からですので、時間のない方は、午後から、直接、渡辺の研究室までお越しください。もし、あらかじめ来る時間などがある場合には、渡辺まで連絡してください。連絡先などは、渡辺のweb siteの中に、連絡するサイトがありますので。
https://www.ige.tohoku.ac.jp/cgi-bin/watanabe/contact/
研究室では、アブラナ科植物の自家不和合性、イネの耐冷性の分子機構、植物の生殖器官特異的に機能するsmall RNAなどについて、研究を展開しています。渡辺だけでなく、当日は、大学院生、博士研究員もいますので、様々な立場からお話が聞けると思いますので。
詳しい説明は、topページから、ぜひ、ご覧ください。しばらくは、News relaseからご覧ください。近いうちにtopに目立つようにしますので。
では、5月の菜の花のシーズン、田植えのシーズンにお待ちしております。
わたなべしるす。