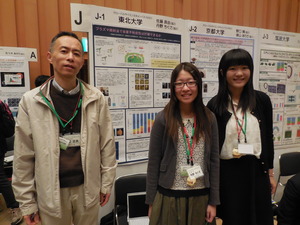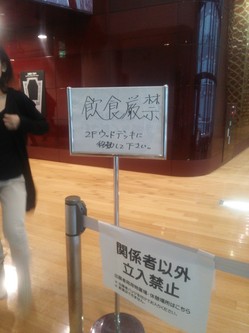経済学部一年倉田健太郎です。秋冬野菜を盆栽として育ててみようの講義で白菜とカイワレ大根を育てています。すこし期間が開いてしまいましたが、三日ほど前から三枚目と四枚目の本葉が成長し、大きくなってきたので報告したいと思います。
〇ミニ白菜について
葉の裏表や茎もチェックしてみましたが、目に見える虫害は見られないです。ただ、子葉が一週間くらい前から少し白くなって変色してしまっていて心配なところがあります。小学校などの記憶では本葉が育ってくると子葉がこのように役目を終えて枯れてくる気がして安心していたのですが、病気ではないでしょうか?
 調べてみましたが、特にそのような病気は出てこず、本葉には全く影響がないようなのでこのまま育つのではないかと思っています。高さは三センチ程度にまで延びました。60日程度で収穫できるとのことでしたが、4週間でそれほど育たなかったような気がします。寒さ対策で昼外に出して、家に入れるようにしていますが、夜遅く帰ってから入れたり忘れてしまったりで寒さで少し成長が遅れているのではないかと思っています。水遣りは前回アドバイスいただいた通り、遣り過ぎないよう土が乾いてからやるようにしています。成長の遅れが寒さによるものなら良いのですが、子葉の変色が何らかの影響を与えている恐れもあって心配です。本葉がどんどん成長しているので大丈夫だとは思いますが、助言いただけるとありがたいです。
調べてみましたが、特にそのような病気は出てこず、本葉には全く影響がないようなのでこのまま育つのではないかと思っています。高さは三センチ程度にまで延びました。60日程度で収穫できるとのことでしたが、4週間でそれほど育たなかったような気がします。寒さ対策で昼外に出して、家に入れるようにしていますが、夜遅く帰ってから入れたり忘れてしまったりで寒さで少し成長が遅れているのではないかと思っています。水遣りは前回アドバイスいただいた通り、遣り過ぎないよう土が乾いてからやるようにしています。成長の遅れが寒さによるものなら良いのですが、子葉の変色が何らかの影響を与えている恐れもあって心配です。本葉がどんどん成長しているので大丈夫だとは思いますが、助言いただけるとありがたいです。
 〇カイワレ大根について
〇カイワレ大根について
アドバイス通り市販のものと食べ比べてみました。写真等取り忘れてしまいましたが、せっかくですので中間報告のプレゼンで本報告したいと思います。
中間報告に向けた準備も進めていきたいと思います。
**********************
渡辺コメント
経済学部・倉田さん、2回目の投稿ありがとうございました。今朝はずいぶん風が強いですが、どうでしょうか。拡大写真でここのこととわかりやすくしているのは、よいですね。書いてあるとおり、本葉が生長してくると、子葉はかれてきますが、少し病気か、生理障害のようですね。おもうに、水をやりすぎのような、感じがします。土の色から。常に土の表面がぬれているということは、根っこはもっとしめっていますので。少し水をあげないように、乾かすようにして下さい。一度、水をあげる直前の写真を撮って、記事を書いて下さい。そうしたら、よくわかります。あと、昨日、メンターの木幡君が、もう少し大きい植物かもしれないですが、栽培記録を出してくれています。参考にして下さい。
カイワレダイコン、食べ比べ、楽しみですね。どうなったのか。次は、中間発表ですね。楽しみにしています。
わたなべしるす
**********************
〇ミニ白菜について
葉の裏表や茎もチェックしてみましたが、目に見える虫害は見られないです。ただ、子葉が一週間くらい前から少し白くなって変色してしまっていて心配なところがあります。小学校などの記憶では本葉が育ってくると子葉がこのように役目を終えて枯れてくる気がして安心していたのですが、病気ではないでしょうか?
 調べてみましたが、特にそのような病気は出てこず、本葉には全く影響がないようなのでこのまま育つのではないかと思っています。高さは三センチ程度にまで延びました。60日程度で収穫できるとのことでしたが、4週間でそれほど育たなかったような気がします。寒さ対策で昼外に出して、家に入れるようにしていますが、夜遅く帰ってから入れたり忘れてしまったりで寒さで少し成長が遅れているのではないかと思っています。水遣りは前回アドバイスいただいた通り、遣り過ぎないよう土が乾いてからやるようにしています。成長の遅れが寒さによるものなら良いのですが、子葉の変色が何らかの影響を与えている恐れもあって心配です。本葉がどんどん成長しているので大丈夫だとは思いますが、助言いただけるとありがたいです。
調べてみましたが、特にそのような病気は出てこず、本葉には全く影響がないようなのでこのまま育つのではないかと思っています。高さは三センチ程度にまで延びました。60日程度で収穫できるとのことでしたが、4週間でそれほど育たなかったような気がします。寒さ対策で昼外に出して、家に入れるようにしていますが、夜遅く帰ってから入れたり忘れてしまったりで寒さで少し成長が遅れているのではないかと思っています。水遣りは前回アドバイスいただいた通り、遣り過ぎないよう土が乾いてからやるようにしています。成長の遅れが寒さによるものなら良いのですが、子葉の変色が何らかの影響を与えている恐れもあって心配です。本葉がどんどん成長しているので大丈夫だとは思いますが、助言いただけるとありがたいです。 〇カイワレ大根について
〇カイワレ大根についてアドバイス通り市販のものと食べ比べてみました。写真等取り忘れてしまいましたが、せっかくですので中間報告のプレゼンで本報告したいと思います。
中間報告に向けた準備も進めていきたいと思います。
**********************
渡辺コメント
経済学部・倉田さん、2回目の投稿ありがとうございました。今朝はずいぶん風が強いですが、どうでしょうか。拡大写真でここのこととわかりやすくしているのは、よいですね。書いてあるとおり、本葉が生長してくると、子葉はかれてきますが、少し病気か、生理障害のようですね。おもうに、水をやりすぎのような、感じがします。土の色から。常に土の表面がぬれているということは、根っこはもっとしめっていますので。少し水をあげないように、乾かすようにして下さい。一度、水をあげる直前の写真を撮って、記事を書いて下さい。そうしたら、よくわかります。あと、昨日、メンターの木幡君が、もう少し大きい植物かもしれないですが、栽培記録を出してくれています。参考にして下さい。
カイワレダイコン、食べ比べ、楽しみですね。どうなったのか。次は、中間発表ですね。楽しみにしています。
わたなべしるす
**********************