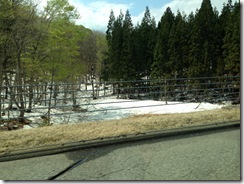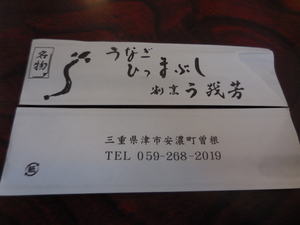渡辺先生が、春の野辺で謎の植物を拾ってきました。
ひょろひょろとした姿、単子葉でしょうか。
根元を見ると、タマネギのようです。ネギボウズ??いやいや。

花っぽいところに何かもにゃもにゃと生えています。
球根のようにも見えます。謎です。

坂園助教がひとつもいでみたところ、ネギの香りが漂います。
やはりこれは...。
ひとつひとつバラバラにして、植えてみることにしました。
強くなるネギの香り。やっぱりこれは.........。

ノビルとかそれ系?(推測)。
ネギ科のうちの一部は花が咲いた後、むかごを形成するそうで(球根のようなものね)。
それは通常地上に落ちた後に発芽するのですが、希に花序に付いたまま発芽を起こし、このような状態になるのだそうです(参考URL、イラスト注)。
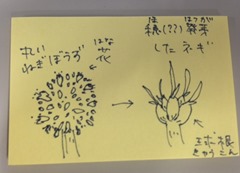
速、件の球根にルートンを塗布し、植えておきました。
とはいえ、可食かも不明。
しかし、あわよくば、夏のそうめんの具材になってもらうべく、育ったら味見したいと思います。
どこのネギかもしれないのに危ないって?
いやいや、僅かな勇気が本当の魔法だって、ネギも言ってますからね!
(魔法先生ネギま!のネギの本名は、ネギ・スプリングフィールドって言うの。週刊マガジン2003~2012に連載)

ますこ