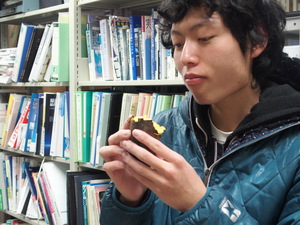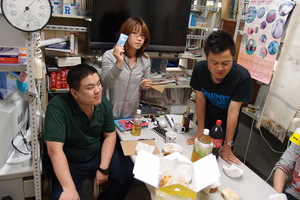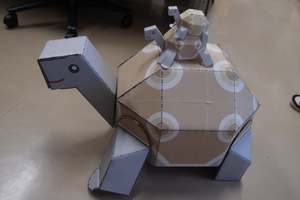こんにちは。M2の田口です。
お米ってとても手間がかかります。
稲(植物体)からもみ(実)を外して(脱穀)
もみからもみがらを外して玄米にして(もみすり)
玄米から外側の層を削って(精米)
ようやく白米になります。
食べるときはさらにここから炊きましょう。
前置きが長くなりました。
コイン精米機はそれなりに近くにあるものの、
もみすりもできる精米機は見つからず・・・。
米穀店に電話してようやく利府市にあることが判明しました!

本当にもみすりができるようです。よかったよかった。
わかりやすい。

ざーっと入れます。

100円でもみすりができて玄米になり、さらに100円で精米ができて玄米から白米になります。

ここから白米が出てきます。
精米する機械を見るのは初めてだったのでとても面白かったです。
普段実験に使うものも遺伝子とか花とかなので、使う実験機器も小さいので
こんな大がかりな機械が動くところを見るのは楽しかったです。
(写真では大きさがわかりづらいですが、天井まであります。)
楽しかったので、今年収穫したらまた行きたいです。
田口
稲(植物体)からもみ(実)を外して(脱穀)
もみからもみがらを外して玄米にして(もみすり)
玄米から外側の層を削って(精米)
ようやく白米になります。
食べるときはさらにここから炊きましょう。
前置きが長くなりました。
昨日、後藤君が研究室訪問ともみすりの話をダイアリーに書いてくれましたが、
彼がとんかつ屋に行き、講義に出ている間のお話です。
そのとき、私は増子さんと利府市まで精米しに行ってました!
後藤君のダイアリーでは手動でもみすりをしていましたが、
それはほんの一部で、大部分は機械でやってました。
ラボにはもみがらがついたままのもみがずっと置いてありました。それはほんの一部で、大部分は機械でやってました。
コイン精米機はそれなりに近くにあるものの、
もみすりもできる精米機は見つからず・・・。
米穀店に電話してようやく利府市にあることが判明しました!

本当にもみすりができるようです。よかったよかった。
わかりやすい。

ざーっと入れます。

100円でもみすりができて玄米になり、さらに100円で精米ができて玄米から白米になります。

ここから白米が出てきます。
精米する機械を見るのは初めてだったのでとても面白かったです。
普段実験に使うものも遺伝子とか花とかなので、使う実験機器も小さいので
こんな大がかりな機械が動くところを見るのは楽しかったです。
(写真では大きさがわかりづらいですが、天井まであります。)
楽しかったので、今年収穫したらまた行きたいです。
田口