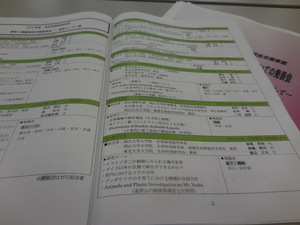HPに出前講義等のアウトリーチ活動の記録が多いので、渡辺は本当にサイエンスをしているのか、疑問を持つ方も多いのでは。。。。たしかに。。。昔は、電気泳動をしたり、交配をしたり、花粉管の観察をしたり、もちろん、多くの論文をhandlingして。。。論文のhandlingは、今も重要な活動です。そんな昔の渡辺のことを知っている、Penn. State Univ.のProfessor Kaoと一緒に座長を賜ったのが、日本植物生理学会シンポジウム「植物の生殖過程における鍵分子とその機能解析」。渡辺がはじめて、国際学会に参加したのが、1991年のInternational Congress of Plant Molecular Biologyが米国アリゾナ州ツーソンで開催され、ポスター発表のつもりで申し込んだら、short talkにも選ばれて。その当時は、英語力はほぼゼロ。。。。見かねた師匠の日向先生が原稿を作ってくれ、また、最後に、質問を受けてもこたえることが無理なので、そのための工夫の文章も。その会議で渡辺の発表をきいてくれていたのが、Professor Kao。それ以来、こちらが海外に出た折り、日本で開催の学会などで、話をするようになり、今では様々な場面でお世話になっている方。そんな方と座長を一緒にできるのは、この上ないありがたいことで。。。
 Speakerには、名古屋大・上口先生、横浜市大・木下先生、Penn. State Univ., Professor Kao、奈良先端大・藤井先生、名古屋大・東山先生。上口先生からは、昨年、Scienceに掲載されたシダ類とアンセリジオーゲンとの関係。木下先生からは、植物の雑種研究の歴史からepigeneticな制御について。Professor Kaoは、ペチュニアの自家不和合性の歴史。1994年にS-RNaseが雌しべ側S因子であるのを形質転換で証明したスライドもあり、横浜での国際会議で通訳をやったのを思い出しました。。。そこで、渡辺がちょっと大変だったことを覚えている方もいないので。会場には。。。それにしてもいろいろあったのだと。。。藤井先生からは、自家不和合性の乳頭細胞で、何が起きているのか。ずいぶん考えさせられました。ちょっと考えないと。。。かなりですね。最後の東山先生のは、圧巻でした。かなりのヒントを頂きましたし、共同研究が大事なと思いました。こんなに楽しいシンポジウムのお世話役をさせてもらえたのは何よりでした。
Speakerには、名古屋大・上口先生、横浜市大・木下先生、Penn. State Univ., Professor Kao、奈良先端大・藤井先生、名古屋大・東山先生。上口先生からは、昨年、Scienceに掲載されたシダ類とアンセリジオーゲンとの関係。木下先生からは、植物の雑種研究の歴史からepigeneticな制御について。Professor Kaoは、ペチュニアの自家不和合性の歴史。1994年にS-RNaseが雌しべ側S因子であるのを形質転換で証明したスライドもあり、横浜での国際会議で通訳をやったのを思い出しました。。。そこで、渡辺がちょっと大変だったことを覚えている方もいないので。会場には。。。それにしてもいろいろあったのだと。。。藤井先生からは、自家不和合性の乳頭細胞で、何が起きているのか。ずいぶん考えさせられました。ちょっと考えないと。。。かなりですね。最後の東山先生のは、圧巻でした。かなりのヒントを頂きましたし、共同研究が大事なと思いました。こんなに楽しいシンポジウムのお世話役をさせてもらえたのは何よりでした。
最後に、Concluding Remarksを、Professor Kaoから。このシンポジウムの特徴をしっかり理解して持っていて。30年以上、自家不和合性の研究をされている訳なので、。。感動でした。関係の先生方、さらには、早い時間からきて頂いた皆様に、感謝申し上げます。ありがとうございました。

わたなべしるす
PS. 学会の意向で、audienceの99%は日本人。でも、発表は英語。。。。グローバル化というのは、ありだと思いますが。必要に応じて、渡辺がProfessor Kaoに説明をすればよいわけで。日本語なら。ましてや、Professor Kaoの出身は台湾。大学まで台湾で過ごされ、大学院から米国へ。なので、漢字があれば、かなりのことを理解してくれます。もちろん、グローバル化の時、漢字だけで何とかなるのは、台湾、中国を含めて、少ないかも知れないですが。それでも。。発表して頂いた先生方も必要に応じて、日本語を入れてくれて、audienceに配慮頂いたのは、よかったのではと。ありがとうございました。
 Speakerには、名古屋大・上口先生、横浜市大・木下先生、Penn. State Univ., Professor Kao、奈良先端大・藤井先生、名古屋大・東山先生。上口先生からは、昨年、Scienceに掲載されたシダ類とアンセリジオーゲンとの関係。木下先生からは、植物の雑種研究の歴史からepigeneticな制御について。Professor Kaoは、ペチュニアの自家不和合性の歴史。1994年にS-RNaseが雌しべ側S因子であるのを形質転換で証明したスライドもあり、横浜での国際会議で通訳をやったのを思い出しました。。。そこで、渡辺がちょっと大変だったことを覚えている方もいないので。会場には。。。それにしてもいろいろあったのだと。。。藤井先生からは、自家不和合性の乳頭細胞で、何が起きているのか。ずいぶん考えさせられました。ちょっと考えないと。。。かなりですね。最後の東山先生のは、圧巻でした。かなりのヒントを頂きましたし、共同研究が大事なと思いました。こんなに楽しいシンポジウムのお世話役をさせてもらえたのは何よりでした。
Speakerには、名古屋大・上口先生、横浜市大・木下先生、Penn. State Univ., Professor Kao、奈良先端大・藤井先生、名古屋大・東山先生。上口先生からは、昨年、Scienceに掲載されたシダ類とアンセリジオーゲンとの関係。木下先生からは、植物の雑種研究の歴史からepigeneticな制御について。Professor Kaoは、ペチュニアの自家不和合性の歴史。1994年にS-RNaseが雌しべ側S因子であるのを形質転換で証明したスライドもあり、横浜での国際会議で通訳をやったのを思い出しました。。。そこで、渡辺がちょっと大変だったことを覚えている方もいないので。会場には。。。それにしてもいろいろあったのだと。。。藤井先生からは、自家不和合性の乳頭細胞で、何が起きているのか。ずいぶん考えさせられました。ちょっと考えないと。。。かなりですね。最後の東山先生のは、圧巻でした。かなりのヒントを頂きましたし、共同研究が大事なと思いました。こんなに楽しいシンポジウムのお世話役をさせてもらえたのは何よりでした。最後に、Concluding Remarksを、Professor Kaoから。このシンポジウムの特徴をしっかり理解して持っていて。30年以上、自家不和合性の研究をされている訳なので、。。感動でした。関係の先生方、さらには、早い時間からきて頂いた皆様に、感謝申し上げます。ありがとうございました。

わたなべしるす
PS. 学会の意向で、audienceの99%は日本人。でも、発表は英語。。。。グローバル化というのは、ありだと思いますが。必要に応じて、渡辺がProfessor Kaoに説明をすればよいわけで。日本語なら。ましてや、Professor Kaoの出身は台湾。大学まで台湾で過ごされ、大学院から米国へ。なので、漢字があれば、かなりのことを理解してくれます。もちろん、グローバル化の時、漢字だけで何とかなるのは、台湾、中国を含めて、少ないかも知れないですが。それでも。。発表して頂いた先生方も必要に応じて、日本語を入れてくれて、audienceに配慮頂いたのは、よかったのではと。ありがとうございました。