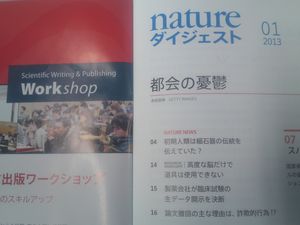あけましておめでとうございます。
M2の前田です。
お正月です。
お正月というのにお店はだいたいあいてます。有り難いです。
今年は全然お正月感がありません。
コタツに入ってないからでしょうか。
家にいても研究室にいてもパソコン画面とにらめっこ状態です。
デスクトップのパソコンなので、コタツに入れません。
さて、去年を振り返れば、楽しい1年間だったなと思います。
食事に行けば、高確率でメニューを間違えられます。
普通の人はそうそうないくらいのレベルだと思います。
まさか、大晦日にもやってくれました。
某ハンバーガー屋さん。
僕はハンバーガーが大好きです。大学時代はアルバイトもしておりました。
そこで、僕はジューシーチキンスナックというものを注文しました。
これは、ジューシーチキンフィレオたるもののパティ(具)です。
働いてたので分かります。
一口食べて、衝撃を受けました.
・・・味が変。
実は、味は変ではないのです。
これは、チキンタツタ用のパティでした。
探偵ナイトスクープでやってました。
プリンと言われてて茶碗蒸しを出されると、腐っていると感じてしまうのです。
その茶碗蒸しがどれだけおいしい茶碗蒸しだとしても。
ジューシーチキンスナックだと思ってチキンタツタ用のパティを食べても、味が変だと感じてしまいました。先入観とは恐ろしいものです。
これだけでなく、
学食でカレーを頼んだらカレーの代わりに謎のたれがチョロンとかかってたり、
自分の目の前で品物こぼされたり、
それがキノコのみそ汁だったのでラッキーと思ってたら同じの出されたり、
メニューの間違いは日常茶飯事、謝るのにもなれました。
このように、去年は周りに楽しませて頂きました。
もちろん食べ物だけでなく、周りの人たちにも楽しませてもらいました。
そこで、新年の抱負。
2013年、今年は楽しませてもらうだけでなく、周りの人を楽しませたいと思います。
そして、自分に降り掛かる小さなハプニングに幸せを噛み締めたいと思います。
M2 前田