
来年のことを言うと、鬼が笑うと言いますが、そういえば、今年も残すところ、31日でしょうか。。あっという間でした。
今年もいろいろあったというのは、また、年末にするとして、今年の大きなことは、建物の改修工事でしょうか。地球に優しいという点では、建物を新築するより、効率的で、良いのではと思います。その意味では、地球で、CO2を吸収できる植物研究者としては、良いことをしたのではと思っています。その意味で、身の回りの植物、作物を大事にして、CO2を吸収するようにすることは、大学の目標にもあうとのこと。なによりです。研究をすることが、大学の目標に合うというのは、幸せなことです。
地球温暖化しても、すぐに、仙台が亜熱帯になるわけでもなく、異形花型自家不和合性を示す、スターフルーツが、仙台で栽培できることはないでしょう。さすがに。。。。出前授業による地域貢献という「環境作り」もできました。ことしは。
来年には、新しいlab spaceが完成するでしょう。その意味で、来年も、引き続き、様々な環境改善に向けて、labをと思うのでした。
わたなべしるす


 11/30-12/1に、海洋研究開発機構「階層構造の科学」研究グループと明治大学グローバルCOE「現象数理学の形成と発展」が企画した、「階層構造科学+現象数理学」研究会に招待され、「植物の多様性、自家不和合性、生殖」ということで講演をしてきました。物理現象、気象現象、金融・経済危機、非線形性、シミュレーション、など、きわめてheteroな研究会でした。
11/30-12/1に、海洋研究開発機構「階層構造の科学」研究グループと明治大学グローバルCOE「現象数理学の形成と発展」が企画した、「階層構造科学+現象数理学」研究会に招待され、「植物の多様性、自家不和合性、生殖」ということで講演をしてきました。物理現象、気象現象、金融・経済危機、非線形性、シミュレーション、など、きわめてheteroな研究会でした。
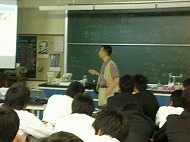 沖縄県立八重山高校で、自家不和合性、生殖の不思議、品種改良などをテーマに講義を行ってきました。今回の沖縄、それも最南端の高校での出前講義を設定していただいたのは、生命学研究科のサイエンスエンジェル(SA)の学生さんのおかげです。まず、最初にその方々に感謝します。
沖縄県立八重山高校で、自家不和合性、生殖の不思議、品種改良などをテーマに講義を行ってきました。今回の沖縄、それも最南端の高校での出前講義を設定していただいたのは、生命学研究科のサイエンスエンジェル(SA)の学生さんのおかげです。まず、最初にその方々に感謝します。 仙台市教育委員会との提携で、今日は「鹿野小学校」で「出前授業」でした。国道286号線沿いにあり、何かで通るとよく見かけることはありましたが、講義で伺うのははじめてでした。1, 2校時が授業の時間でした。先週の吉成小学校同様に、リンゴをモデルとした、受粉、受精、自家不和合性、果実の成熟など、小学校5年生には少し難しい課題ではありましたが、一生懸命講義を聴いてくれて、質問ももらいました。朝早くの講義と言うこともあり、後半になるほど、生徒たちのエンジンもかかってきて、最後のリンゴの観察では、食い入るように見ていたのが印象的でした。
仙台市教育委員会との提携で、今日は「鹿野小学校」で「出前授業」でした。国道286号線沿いにあり、何かで通るとよく見かけることはありましたが、講義で伺うのははじめてでした。1, 2校時が授業の時間でした。先週の吉成小学校同様に、リンゴをモデルとした、受粉、受精、自家不和合性、果実の成熟など、小学校5年生には少し難しい課題ではありましたが、一生懸命講義を聴いてくれて、質問ももらいました。朝早くの講義と言うこともあり、後半になるほど、生徒たちのエンジンもかかってきて、最後のリンゴの観察では、食い入るように見ていたのが印象的でした。