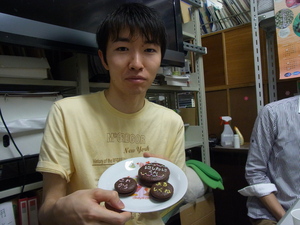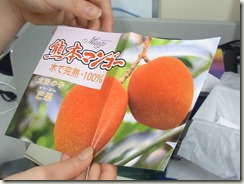前線が上がってきて、今日は雨降りだが、昨日はずいぶんと仙台でも暑かった。7月上旬なのに。。。30oCを越えるとは。。。小学校の頃、通学路くらいだろうか、アスファルトで舗装されていたのは。。。脇道になると、土埃の道だったし、周りは、畑、水田が多かった。そのアスファルトで舗装された道を今頃歩いていると、暑い日には、「逃げ水」というのを見て、びっくりした。物理の理屈はきちんと説明できないが、見た時は、感動した。土埃があるのは確かに、環境的にはよくないのかもしれないが、大学の中を考えても、昔はここまで舗装してなかったところまで、舗装しているからだろう。こんなに気温が上がるようになったのも。逃げ水ならぬ、温度をどこかに逃がす工夫ができないと、今年の夏もまだ始まってない頃から暑いのでは。。。何とかしないといけない。
 ゲリラ豪雨が増えた一因として、都市部でのヒートアイランド現象というか、それで積乱雲ができてというのを聞いたことがある。そう考えると、昔、通り雨というような雨があったが、今のような大粒であることもないし、長時間でもなかった。何事もそうかもしれないが、原因があって、それに伴う結果が生じる。ただ、結果は見えるけど、原因が何かというのがわからない、わかりにくいこともある。遺伝学は、表現型という結果を見て、その原因を考える訳であるので、こうしたことに、敏感なのかもしれない。直接であれ、間接であれ、原因は原因。その原因をきちんと理解しないと物事は始まらない。というか、次への新しい発展もない。まずは、現象を見て、その原因を考えることから、初めて見ることで、何かかが変わるような気がするというより、変わってほしい。
ゲリラ豪雨が増えた一因として、都市部でのヒートアイランド現象というか、それで積乱雲ができてというのを聞いたことがある。そう考えると、昔、通り雨というような雨があったが、今のような大粒であることもないし、長時間でもなかった。何事もそうかもしれないが、原因があって、それに伴う結果が生じる。ただ、結果は見えるけど、原因が何かというのがわからない、わかりにくいこともある。遺伝学は、表現型という結果を見て、その原因を考える訳であるので、こうしたことに、敏感なのかもしれない。直接であれ、間接であれ、原因は原因。その原因をきちんと理解しないと物事は始まらない。というか、次への新しい発展もない。まずは、現象を見て、その原因を考えることから、初めて見ることで、何かかが変わるような気がするというより、変わってほしい。わたなべしるす
PS. 昨日の昼過ぎには、M5.0の地震が岩手県沿岸北部で。。。最初に揺れて、そのあとそれなりの地震になるかと思ったのですが。。。収まってほっとですが。。。M5.0の地震も久しぶりでしたので。何か被害があった訳でないですが。。揺れると、気になるものです。