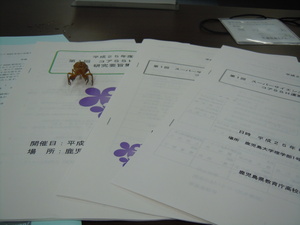夏休みの間、娘が学校で栽培している朝顔を家に持って帰ってきていました。
自分で育てた花が初めて咲いて、とても嬉しそう。
ある日、水を撒きながら翌日咲きそうなつぼみを発見して、「花が咲く瞬間が見たいな〜。」と言い出しました。
瞬間って、、、風船が割れるように一瞬でパッと開くとでも思っているのかな???
とりあえず、次の日に早起きしてみようと言うことで、目覚ましを4時にセットしました。
1日目、AM4:00
ベランダに見に行くと既に花が咲いていました。
う~ん、朝顔って思ったより早起きなのね。
2日目、AM3:00
色々なHPを読んでみると、朝顔の体内時計が花の中肋で明暗を感知して開花時刻を決めている様で、日没からおよそ8~10時間後に花が開くようです。
そこで、昨日の失敗を教訓に、1時間早めて3時に起床してみました。
ところが、3時に起きてみると既に咲いている!!
「やられた~。」と思いつつよく見てみると、少し開きかけの花がもう1輪あったので、取りあえず10分おきに観察してみることに。花は30分程かけて完全に開きました。(睡魔と戦いつつ暗闇で撮影した為、ピンぼけ写真で失礼します。)
3日目、AM2:00
またまた別の資料によると、朝顔は明けがたの温度によっても開花時間が変わるらしく、気温が下がると開花が早まるようです。ちょうど肌寒い日が続いていたので、開花時間が早まっているのかな?と思い、気合いを入れて今日は2時に起床してみました。
微妙に開きかけ?の1輪があったので、また10分おきに観察してみることに。ところが、1時間過ぎても開かない!!1時間半過ぎたところで痺れを切らして、花の先端をちょっと突いてみました。
10分後、再度見に行くと、、、「あ~~~~。」咲いちゃってる(涙)。
4日目、AM3:00
3日間の疲れからか?2時には起きることができず、3時に起床。
けれども窓を開けると、面白い光景が目に入ってきました。
まるで朝顔が徐々に開く様子を表すかのように、「つぼみ」、「咲きかけ」、「8分咲き」、「満開」の4輪の花が!!
(つぼみは裏側で残念ながら写真に写りませんでした。)
うまくいけば、立派な自由研究になるのでは?という企みの元で始めた観察でしたが、連日の寝不足で観察は4日目で終了としました。
けれども、朝顔の花は一瞬で開くものではなく、ゆっくり時間をかけて開いているのだということは何となく分かってもらえたかな?
もうすぐ夏休みも終わりますが、この時期にしか出来ない、楽しい(眠たい?)朝の観察会でした。
いとう