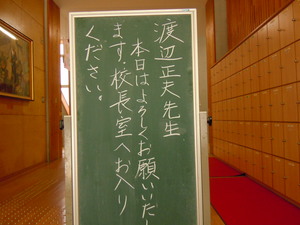実験の打ち合わせを兼ねて、ゲノム・遺伝子相関班会議に参加してきました。
今回の会場はANAクラウンプラザ神戸。
梅雨に入っていましたが、ほとんど雨にあたることなく過ごすことができました。
仙台とは違い、じめじめ、むしむし、暑かったです・・・。
さて、今回の班会議でも、30の研究グループの研究状況報告を聞くことが出来ました。
まだまだ自分は勉強不足だなぁと感じたので、少しでも知識が増えるように今後も努力していきたいです。
また、今回の班会議では若手のポスター発表の場があり、私も発表させて頂きました。
初めてのポスター発表で緊張しましたが、良い経験になりました。
このような機会を与えて下さった先生方、ありがとうございました。
今回の経験を今後に活かしていきたいと思います。
県外に行くと、その土地の食べ物が食べたくなりますよね。
ということで、懇親会では神戸牛がでました!!実演!
ケーキもホテルの方が切り分けてくれるというサービス!
幸せなひとときでした・・。
そういえば、コンビニにはこんなおにぎりが。
このような、その土地ならではのものを見つけると、うれしくなりますね。
普通のおにぎりと比べると高いですが、神戸の方はこれを食べているのでしょうか・・・。
最終日には時間があったので、会場の近くの神戸布引ハーブ園に行ってきました!
ラベンダーとバラがたくさん咲いていました!
ハーブ園なので、香りのする植物や、スパイスとして使われる植物など、
おもしろい植物がたくさんありました。
マスタードも展示されていました。
いつも見ているアブラナのタネと同じでした。
今回の班会議では、昨年の若手の会で知り合いになった方や、
他大学の先生方ともお話しすることができ、有意義な時間を過ごすことができました。
これからも、多くの研究に触れ、自分の視野を広げられるようにしていきたいなと感じました。
M2 曽根


-thumb-200x150-5624.jpeg)

-thumb-200x150-5626.jpeg)
-thumb-150x200-5640.jpeg)