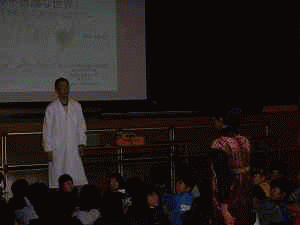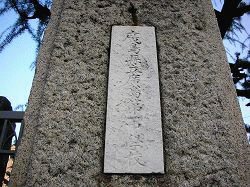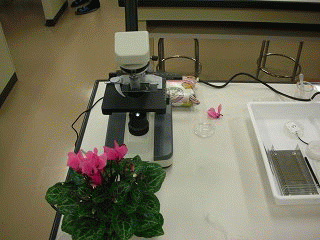
先月、SSH実施高校である、宇都宮女子高等学校1年生全体への特別講義、「植物科学研究における最近のトピックス--自他識別が起きる自家不和合性とは。。。--」を行いました。そのうちの生徒さんが、宇都宮大などでの実習と平行して、渡辺をはじめとする3名の大学の教員が高校を訪問して、出前実験を行いました。渡辺は、生物を担当し、「身近な花をじっくり観察してみよう!!」と言う題目で実験を行いました。新型インフルエンザの猛威で、本来なら20名近い生徒さんとの実験でしたが、7クラス中、5クラスが、学級閉鎖と言うことで、先生方を含めて、8名での実験となりました。
まず、キクの花をピンセット、カミソリなどで分解してもらい、実体顕微鏡で観察し、形態的特徴をつかんでもらいました。花粉に着目する生徒さんもいれば、維管束に興味がある生徒さんも。それぞれが、それぞれの興味で観察、記録をとってもらいました。渡辺も形態観察は苦手で、特に絵を描くのは、へたでした。その当たりも生徒さんでばらつきがあるのは、今も変わらないのだと、実感しました。その後は、各自で準備した花を観察したり、シクラメンの花粉発芽を寒天培地の上でトライしてもらったり。宇都宮と言えば、餃子。その餃子に欠かせない「ニラ」の花を観察したり。あっという間に実験が終了しました。もう少し実験を続けたいという生徒さんも多く、終わったあとも、熱心にやっていた姿は、とてもうれしかったです。ぜひ、このスタンスを続けてください。
来年は、ぜひ、より多くの方に、「観察することの大切さ」、「何を観察するのか、何に着目するのか、と言うことの難しさ」、「記録をとること、書くときに特徴をどう記すのかと言うことのたいへんさ」も学習してほしいと思います。観察は生物学の基本ですから。
なお、キクの花、シクラメンの花などを供給していただいた栃木農試の天谷室長には、この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。
わたなべしるす