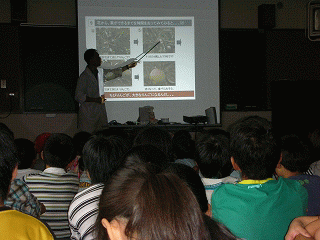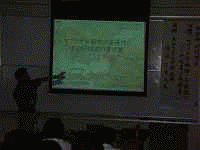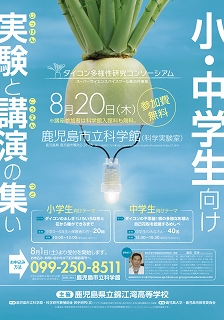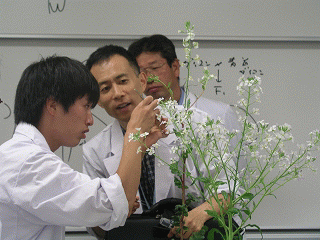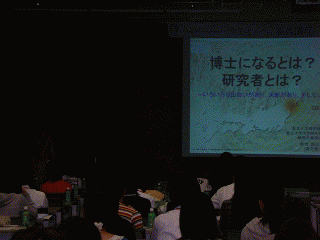
4月から高校1, 2年生を対象に募集していたall 東北大の企画である「経験・体験を通して「科学を見る眼」をもつ「科学者の卵」養成プログラム」の第1回特別講義を開催しました。受講生の皆さんもずいぶんなれてきた様子で、他県の高校生同士がフランクにしゃべっている様子は、こちらが意図している異分野交流の1つではないかと思いました。
6月にも渡辺が「進化論を唱えたダーウィンも注目した高等植物の自家不和合性--花粉と雌しべの細胞間コミュニケーションとその分子機構--」と題して、植物の花粉と雌ずいの自他識別のモデルともいえる自家不和合性について、講義しました。これは、植物科学研究の最先端のお話をしたわけですが、今回は、趣を変えて、研究者・科学者としてのキャリア、つまり、どのようにして、現在に至ったかを、渡辺を例に取り上げてお話ししました。
小学校、中学校、高校、大学、研究者になってから、これらからのこと等々、渡辺がどこで何を考え、どのような分岐点をかいくぐってきたのかをお話ししました。小学校、中学校の頃に覚えた、「あやとり」、「ルービックキューブ」は、不完全なりにも、記憶の片隅に残っていて、できます。また、テレビから影響を受け、科学者、博士、研究者、になろうとしたようなことも。というか、そんな単純な発想で、今に至っていることを考えると、それでよいのかというのももちろんありますが。。
科学の講義ではなかったため、少し質問は少なかったですが、提出してもらったレポートには、講義でこちらが伝えたかったことがよく伝わった内容のコメントがたくさんありました。それについては、一両日中に、未来の科学者の卵のHPで紹介しますので、ぜひ、ご覧ください。
http://www.ige.tohoku.ac.jp/mirai/
http://www.ige.tohoku.ac.jp/mirai/news/2009/09/14172108.php
http://www.ige.tohoku.ac.jp/mirai/news/2009/09/14163242.php
http://www.ige.tohoku.ac.jp/mirai/activity/2009/09/16171526.php
自分が何をしたいのか、どこまで達成したいのか、というようなはっきりとした目標を持つことは、単に、受験とか、そういうことに限らず、重要であると思った、今日の講義でした。
わたなべしるす
PS. 当日は、プレスの取材もあり、近いうちに新聞紙上でも紹介される予定です。