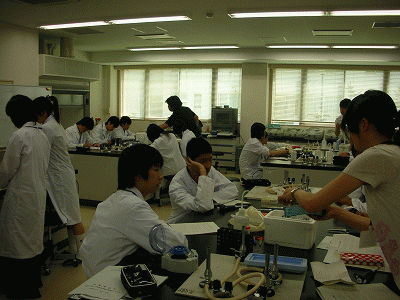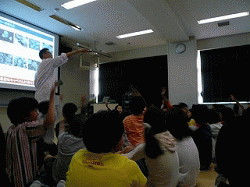東北地方でもようやく天気がよくなったようですが、西日本の天気の良さは、それから比べると、考えられないような猛暑です。そうした環境でも、植物は花を咲かせ、実を実らせている様子を見るにつけ、「植物のすごさ」を痛感するのでした。
そのような中で、今治南高で農場見学にあわせて、「高等植物の受粉・受精」の実験について、先生方と検討会を行い、高校でも可能な興味深い実験の可能性を模索しました。スイカ、キュウリ、ゴーヤなどのウリ科の作物を使っての、受粉、結実を最終的にできる果実で、わかるようにするために、受粉を雌しべの先端の一部だけに行うなど、おもしろい実験ができそうでした。同じ実験系は、トマトなどのナス科の作物でも可能だろうし、おもしろい表現型になるのではということになりました。このideaを早く実証したくなってきました。
暑さに負けないで、作物の管理をしている生徒さん、先生方に感動したのでした。
わたなべしるす