 ダイコンコンソーシアム研究指導のつながりで、石川県小松高校で講義をしたり、研究指導を行ったのは、10/30でした。その際は、キャリア教育を1, 2年生対象に行ったり、ダイコンなど、生物関係の研究について議論をしたり、今後後の方向性を検討したりと、よい刺激を受けました。
ダイコンコンソーシアム研究指導のつながりで、石川県小松高校で講義をしたり、研究指導を行ったのは、10/30でした。その際は、キャリア教育を1, 2年生対象に行ったり、ダイコンなど、生物関係の研究について議論をしたり、今後後の方向性を検討したりと、よい刺激を受けました。
そのつながりで、石川県で実施されているSSH校、3校(金沢泉丘高校、七尾高校、小松高校)合同の生徒研究発表会に招待され、コメンテーターを務めました。県内に複数校のSSH校があれば、このようなことも可能なのだと、実感できました。課題研究発表会の進行は、生徒自身が行い、7題の研究発表でしたが、活発な議論が行われたとともに、研究内容も高校生らしいテーマでありながら、deepに研究され、きちんと考察されていたのには、感動しました。最近は、海外の高校との交流も行っているのが多いようですが、その交流が将来、どのような形で生かされるのか、将来像が示されればよかったように思いました。
その中でも興味深かったのは、石川県では発表の多くに「数学」があったことです。「数学」は、科学の基礎であるということは疑いないことであり、それを活発に取り組んでいる点でした。ただ、数学という証明だけに終わらず、実際の自然科学の分野を見直してみるのも1つではないかと思います。発表を聞きながら、自家不和合性の優劣性の遺伝学(linear, non-linear)を思い出しました。生物、物理、科学、地学と、とてもバランスのとれた発表でした。どの課題もとても楽しく拝聴しました。次年度以降の発展を楽しみにしております。
ところで、何より驚いたのは、生徒さんがちが熱心に質問し、議論を行っている点です。これは、今までSSHの発表会を見た中でも、最高だったと思います。とてもすばらしく、うちの大学院生にも、ぜひ、学んでほしい点と思いました。
来年以降、また、こうした発表会に引き続き、参加できればと実感できた、よい1日でした。
わたなべしるす
PS. 当日は今年一番の寒波というおまけもあり、雪・雹(ひょう)・霰(あられ)の歓迎を受けました。また、北陸新幹線(長野新幹線が延長されて。。。)が、このあたりまで来るのだなという実感を、金沢駅、小松駅の高架で実感できたのでした。
 高校生にとって、発表をまとめるというのは、どうしてもレポートのようになりがちで、実験をやった順番、全てのデータを使うと言うことになりがちで、それを論文というポスターにまとめるとき、どれが結論になり、最終的にどうまとめるのか、それに至るまでにどのデータを並べるのが、問題なのですが、そうしたトレーニングはしていないので、その感覚になれることに大変のようでした。
高校生にとって、発表をまとめるというのは、どうしてもレポートのようになりがちで、実験をやった順番、全てのデータを使うと言うことになりがちで、それを論文というポスターにまとめるとき、どれが結論になり、最終的にどうまとめるのか、それに至るまでにどのデータを並べるのが、問題なのですが、そうしたトレーニングはしていないので、その感覚になれることに大変のようでした。 外での植物観察では、品種間で自家不和合性の程度が異なり、自然に放置していても、種が着きやすい系統、つきにくい系統があることを実感してもらいました。最後に、小松高校近隣の自制しているハマダイコンの様子も観察できました。ありがとうございました。種がうまく収穫できるのを楽しみにしております。
外での植物観察では、品種間で自家不和合性の程度が異なり、自然に放置していても、種が着きやすい系統、つきにくい系統があることを実感してもらいました。最後に、小松高校近隣の自制しているハマダイコンの様子も観察できました。ありがとうございました。種がうまく収穫できるのを楽しみにしております。 学会発表まで1ヶ月ほどですが、がんばって下さい。
学会発表まで1ヶ月ほどですが、がんばって下さい。






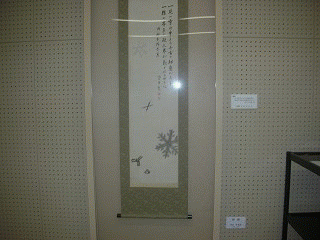 昨日の石川県SSH生徒研究発表会・コメンテーターに引き続き、小松高校でSSHを対象にして、「自家不和合性」の講義を行うとともに、ダイコンコンソーシアム研究指導を行いました。
昨日の石川県SSH生徒研究発表会・コメンテーターに引き続き、小松高校でSSHを対象にして、「自家不和合性」の講義を行うとともに、ダイコンコンソーシアム研究指導を行いました。  ダイコンコンソーシアム研究指導のつながりで、石川県小松高校で講義をしたり、研究指導を行ったのは、10/30でした。その際は、キャリア教育を1, 2年生対象に行ったり、ダイコンなど、生物関係の研究について議論をしたり、今後後の方向性を検討したりと、よい刺激を受けました。
ダイコンコンソーシアム研究指導のつながりで、石川県小松高校で講義をしたり、研究指導を行ったのは、10/30でした。その際は、キャリア教育を1, 2年生対象に行ったり、ダイコンなど、生物関係の研究について議論をしたり、今後後の方向性を検討したりと、よい刺激を受けました。