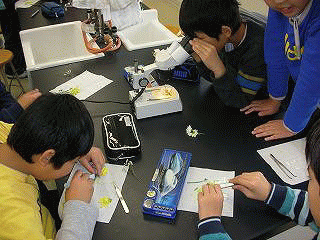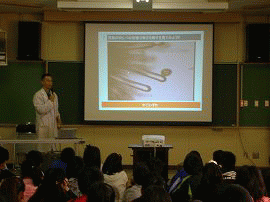 東北大と仙台市教育委員会の連携による「出前講義」は、今年は2件でした。9月はじめの川平小学校に続いて、鹿野小学校が2校目。これで今年は、終わりになります。鹿野小学校は、去年から講義依頼を頂き、リピーターとして、今年も講義をお願いいただいたのは、うれしい限りです。昨年度の5年生の担任の先生からのご推薦だそうです。ありがたいことです。これからも長く続けることができればと思います。本来は、11月の中旬の予定でしたが、昨今の新型インフルエンザの猛威の関係で、学級閉鎖などがあり、12/2の開催となりました。5年生・3クラスで、95名と校長先生をはじめとする5名の先生も受講していただいたのは、うれしい限りでした。
東北大と仙台市教育委員会の連携による「出前講義」は、今年は2件でした。9月はじめの川平小学校に続いて、鹿野小学校が2校目。これで今年は、終わりになります。鹿野小学校は、去年から講義依頼を頂き、リピーターとして、今年も講義をお願いいただいたのは、うれしい限りです。昨年度の5年生の担任の先生からのご推薦だそうです。ありがたいことです。これからも長く続けることができればと思います。本来は、11月の中旬の予定でしたが、昨今の新型インフルエンザの猛威の関係で、学級閉鎖などがあり、12/2の開催となりました。5年生・3クラスで、95名と校長先生をはじめとする5名の先生も受講していただいたのは、うれしい限りでした。
今年の出前講義も、「「花の不思議な世界」--りんごの花からリンゴができるまで??--」ということで、リンゴをモデルとして、花が咲き、受粉、受精して、リンゴができる。その過程には、花粉管が伸びること、自家不和合性という花粉の自他識別があるということ、植物の動的変化というか、ダイナミクスを話しました。花粉管が伸びたり、自家不和合性反応が、柱頭の表面で起きると、「へーーー!」という歓声が。やはり、動画はインパクトがあるようでした。
自家不和合性がなぜ、植物に必要かということを質問したところ、遺伝子が混じることが大切だと。とてもすばらしい答えに、感動しました。ぜひ、将来、一緒に研究ができればと思います。講義の最後に、10名を超える子供さんから、とても純粋な発想の質問をたくさんもらいました。リンゴの品種の数、リンゴはなぜ赤いのか、リンゴとナシは交配できるのか等々。そういえば、この小学校でもこの講義・質問のあとに、サイン会がありました。最近のこともさんがこんなにサインを求めるのかと、不思議に思ったりもしました。いつものように、子供さんたちからの感想文が届くのが楽しみです。
鹿野小学校にも、キャベツとブロッコリーの苗を配布して、ここでも栽培・観察をトライしてもらうことにしました。春には、キャベツとブロッコリーができることを楽しみにしていますし、片平から近いこともありますので、ぜひ、観察会ができればと思います。キャベツとブロッコリーの成長の違いをぜひ、よく観察してくださいね。
最後になりましたが、校長先生、担当の大風先生、東海林先生をはじめとする鹿野小学校の先生方にお礼申し上げます。
わたなべしるす
PS. 講義のあと、校長室で東海林先生を交えて、継続的な講義などについて、お話がありました。良い方向に進めばと思います。そういえば、この鹿野小学校の現校長の前々任者は、一昨年、立町小学校でお世話になった、狩野校長先生でした。世の中、とても狭くて、人のつながりは、すごいと実感したのでした。
https://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/diary/2007/10/18214734.php
追伸(12/4) 鹿野小学校のHPに、東海林先生が日記を記してくれてあります。併せて、ご覧ください。
http://www.sendai-c.ed.jp/~kanosho/blog/index.php?UID=1259726679
 これまでずいぶん多くの出前講義を行ってきました。その対象はほとんどが、小学生、高校生でした。数年前に、IT企業の方々を前にして、「植物・遺伝子・農業」についてと言うことでお願いされ、お話ししたことはありましたが、高校の先生方を対象にして、講義をすると言うことは、今回が初めてでした。
これまでずいぶん多くの出前講義を行ってきました。その対象はほとんどが、小学生、高校生でした。数年前に、IT企業の方々を前にして、「植物・遺伝子・農業」についてと言うことでお願いされ、お話ししたことはありましたが、高校の先生方を対象にして、講義をすると言うことは、今回が初めてでした。

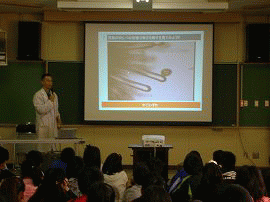 東北大と仙台市教育委員会の連携による「出前講義」は、今年は2件でした。9月はじめの川平小学校に続いて、鹿野小学校が2校目。これで今年は、終わりになります。鹿野小学校は、去年から講義依頼を頂き、リピーターとして、今年も講義をお願いいただいたのは、うれしい限りです。昨年度の5年生の担任の先生からのご推薦だそうです。ありがたいことです。これからも長く続けることができればと思います。本来は、11月の中旬の予定でしたが、昨今の新型インフルエンザの猛威の関係で、学級閉鎖などがあり、12/2の開催となりました。5年生・3クラスで、95名と校長先生をはじめとする5名の先生も受講していただいたのは、うれしい限りでした。
東北大と仙台市教育委員会の連携による「出前講義」は、今年は2件でした。9月はじめの川平小学校に続いて、鹿野小学校が2校目。これで今年は、終わりになります。鹿野小学校は、去年から講義依頼を頂き、リピーターとして、今年も講義をお願いいただいたのは、うれしい限りです。昨年度の5年生の担任の先生からのご推薦だそうです。ありがたいことです。これからも長く続けることができればと思います。本来は、11月の中旬の予定でしたが、昨今の新型インフルエンザの猛威の関係で、学級閉鎖などがあり、12/2の開催となりました。5年生・3クラスで、95名と校長先生をはじめとする5名の先生も受講していただいたのは、うれしい限りでした。