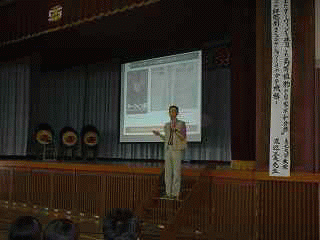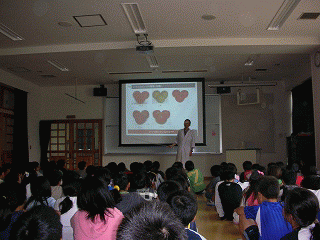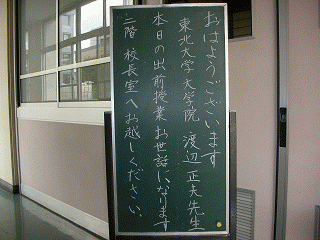
一昨年から始めた、今治市内の小学校での「出前講義」も今年で3年目。日吉小学校では、春に「アブラナの交配」を指導し、校庭には、キャベツを始め、多くのアブラナ科植物が栽培されていました。キャベツとブロッコリーの雑種ができるのも、近いのではと感じました。
5, 6年生、51名に、校長、教頭先生を始め、6名の先生方も参加頂き、体育館で講義を行いました。四国という温暖な地であることもあり、「リンゴの花」を知っている生徒さんは少なく、でも、「ミカンの花」は見たことがある生徒さんが多かったのは、さすがと思いました。しかしながら、普通の花は色が違うだけで、「バラの花」もわからなかったのは、少々残念でした。
今回の出前講義は、「「花の不思議な世界」--りんごの花からリンゴができるまで??--」ということで、リンゴをモデルとして、花が咲き、受粉、受精して、リンゴができる。その過程には、花粉管が伸びる、自家不和合性という、花粉の自他識別があるという、植物のダイナミクスを、話しました。花粉管が伸びたり、自家不和合性反応が、柱頭の表面で起きると、「へーーー!」という歓声がおきました。最初の花とリンゴの対応関係を考えてもらって、花が咲いている状態とリンゴが逆さまになっているのを気がついてもらえたのは、身の回りの不思議の大切さを感じてもらえたのではと思います。講義のあとには、10名を超える生徒さんから、とても純粋な発想の質問をたくさんもらいました。感想文が届くのが楽しみです。
入り口の案内板、講義の垂れ幕、看板を作って頂いた先生方には、最後になりますが、感謝したいと思います。また、ぜひ、来年も講義ができればと思いますので。
キャベツとブロッコリーの雑種を作ること、ぜひ、がんばってください。
わたなべしるす