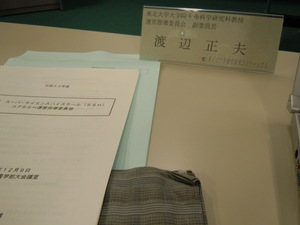今年もあと10日ほどになり、昨日から、仙台は雪模様。。。。HPに告知を打たないとと思いつつ。。今年で3年目。all 東北大の企画である「経験・体験を通して「科学を見る眼」をもつ「科学者の卵」養成プログラム」。今年のキャリア教育も渡辺が担当になりました。卵のHPも併せてご覧になっているかたにはずいぶん前に告知しました。渡辺の講義を聴いたことある方はご存じかもしれないですが、渡辺が小学校から、どうやって今まできたかを、お見せします。それを参考にして、是非、自分の人生の方向性などを決めてください、という企画です。
 今年もずいぶん多くの高校で、キャリア教育をお願いされました。それなりに好評でしたが、今回は、1.5hrはしゃべりまくれるということで、可能な限りやります。学内の方は、受付で、これを見たといえば、入ることができますので、お時間のある方は、片平、さくらホールで、15:00から、おまちしております。なお、この渡辺の講義の前には、工学部の安藤先生の「プラズマが拓く未来社会~宇宙・エネルギーからナノ応用へ~」、併せて、お越しください。
今年もずいぶん多くの高校で、キャリア教育をお願いされました。それなりに好評でしたが、今回は、1.5hrはしゃべりまくれるということで、可能な限りやります。学内の方は、受付で、これを見たといえば、入ることができますので、お時間のある方は、片平、さくらホールで、15:00から、おまちしております。なお、この渡辺の講義の前には、工学部の安藤先生の「プラズマが拓く未来社会~宇宙・エネルギーからナノ応用へ~」、併せて、お越しください。
なお、講義の場所など詳細については、関連のHPをご覧ください。
わたなべしるす
PS. 先週、全学の講義、 「『レポート力』アップのための情報検索入門」ということで、、「資料・情報の活用方法(4)研究活動の実際と情報探索①-自然科学分野」のテーマで講義を行いました。東北大には、講義のメモ、感想を書く紙として、「ミニットペーパー」というのがあるらしく、それに感想などを書いてまとめてくれたものを、統括されている附属図書館図書館参考調査係の方からいただきました。positiveな感想が多く、好評だったこともあり、来年もまた、この講義をという契約になりました。ありがたい限りです。もっと腕を磨いて、おもしろい講義をしたいと思います。

 今年もずいぶん多くの高校で、キャリア教育をお願いされました。それなりに好評でしたが、今回は、1.5hrはしゃべりまくれるということで、可能な限りやります。学内の方は、受付で、これを見たといえば、入ることができますので、お時間のある方は、片平、さくらホールで、15:00から、おまちしております。なお、この渡辺の講義の前には、工学部の安藤先生の「プラズマが拓く未来社会~宇宙・エネルギーからナノ応用へ~」、併せて、お越しください。
今年もずいぶん多くの高校で、キャリア教育をお願いされました。それなりに好評でしたが、今回は、1.5hrはしゃべりまくれるということで、可能な限りやります。学内の方は、受付で、これを見たといえば、入ることができますので、お時間のある方は、片平、さくらホールで、15:00から、おまちしております。なお、この渡辺の講義の前には、工学部の安藤先生の「プラズマが拓く未来社会~宇宙・エネルギーからナノ応用へ~」、併せて、お越しください。なお、講義の場所など詳細については、関連のHPをご覧ください。
わたなべしるす
PS. 先週、全学の講義、 「『レポート力』アップのための情報検索入門」ということで、、「資料・情報の活用方法(4)研究活動の実際と情報探索①-自然科学分野」のテーマで講義を行いました。東北大には、講義のメモ、感想を書く紙として、「ミニットペーパー」というのがあるらしく、それに感想などを書いてまとめてくれたものを、統括されている附属図書館図書館参考調査係の方からいただきました。positiveな感想が多く、好評だったこともあり、来年もまた、この講義をという契約になりました。ありがたい限りです。もっと腕を磨いて、おもしろい講義をしたいと思います。