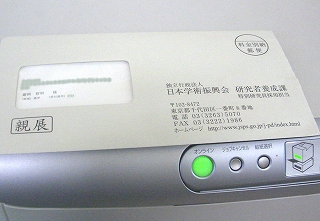
D1藤岡君が、来年度からの学振(DC2)に内定しました!
学振とは、学術振興会が「我が国のトップクラスの優れた若手研究者に対して研究に専念する機会を与える(HPより抜粋)」ことを目的とした研究奨励金制度の通称です。ドクターコース学生とポスドクを対象に2種類あり、この奨励金を獲得することは若手研究者にとって高いステータスの1つになっています。フジが内定したDC2というカテゴリーは、ドクターコースの学生が対象で、その採用率は約25%。日本中の多くのドクターコース学生がトライする狭き門。研究経歴(論文・学会発表等)や今後の研究計画等を厳しく審査されます。フジはこの1年、日々の実験はもちろんのこと、第1著者での論文出版や国内学会での口頭発表、国際学会での発表などいろんなことに精力的に取り組み、今回の結果はそれらの積み重ねによって成し得たものと思います。おめでとう、フジ!!
これで、これからの研究生活が素晴らしいものになるベースができあがりました。あとはフジの頑張り次第で如何様にも変わる未来が待っています。さぁて、フジの今後の研究者人生はどうなっていくのでしょう?とても楽しみです。
これからも研究(+少々!?の遊び)に全力投球。一緒にがんばっていきましょう!
ボスと剛さん、両親への感謝も忘れずにね(笑)。
すわべ





