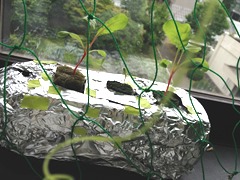留守番部隊No.2のますこです。
伊藤さんがおるすばん日記に乗っかってくれてうれしいな。ありがとうございます>伊藤さん
昨日の続きです。
今日はちゃんと写真を撮ったので、温室の野菜と、水耕栽培の様子をリポートしてみます。
---------------------------
まず、バジルです。もっさもさです。もうジェノバソースにしてもいい位のボリュームになりました。
あまり置いても硬くなるので、今が食べ時かもしれません。

花芽がついて来るので、深く摘んで葉がかたくなるのを防ぎます。


左はベビーリーフ。ベビーというか、もう立派なレタスです。
コマツナ、ルッコラ、レタス等の混合種なんですが、今回はレタスが多いです。そろそろ食べようかね。
右は春菊です。脇芽を摘み摘み食べてきました。
そろそろ脇芽が出なくなってきた株もあり、整理しつつ食べてます。


ミニトマト。かなり立派になってます。ブドウの如く。
この後、少し混んできた下葉を整理しました。泥はねによる病気予防ですね。
脇芽を継いだミニトマトも、だいぶ大きくなってきました。これからに期待ですね。
どちらかというと、脇芽を伸ばして2本で仕立てた個体は花が多いが実が生るのが遅い。
脇芽を摘んで1本に仕立てた個体は、花は少ないが実が生るのが早い、という様子が見られます。
実がとれる時期がズレていいかもしれん。じゅるり。



オクラーズ。アーリーファイブ、まるみちゃん、赤まるみちゃん、白ひすいが植わっています。
コンスタントに花が咲き、コンスタントに実が生ります。
葉も茂って元気ですね。これも、この後、下葉を整理しました。
毎日、丁度良い実を取ってやらないと、個体が弱る上、硬くなり食べられなくなるので注意して見ています。



ズッキーニ・ダイナーズ。
非常に大きく、たくましく育っています。葉の白いのは模様で、病気ではないようです。
かぼちゃの仲間なので、受粉が必要です。
温室は訪花昆虫が少ない(いない)ため、人間が受粉してやります。
受粉が出来ている時は実が大きくなります。ダメだと実が黄色くなって枯れてしまうようです。
最近、雄花が咲かなくて、あんまり受粉出来てません。まー、そのうち。


さつまいも。これは紅あずまだったかな?
徐々に大きくなってきました。良いさつまいもが生ると良いなあ。。。

キュウリーズ。1号、2号、3号とも、コンスタントに実をならせてくれます。
一度ウドンコ病になりましたが、葉を早目に刈ったり、薬をやったりしたので広がらず、元気にしています。
湿気て寒いといけませんね。時々、泥はねによる病気防止のため、下葉を刈ってやっています。
ある程度の節まで伸ばしたら、頂芽を切って脇芽を伸ばしますが。。。
支柱を超えるくらいになったら切ってもいいなあ。



今日も素敵なキュウリがなりました。早速冷蔵庫に入れておきました。

水栽培のミニトマト1号。
一度根ぐされで死にかけ、もうダメだと思っていましたが、復活したので外に出しました。
外にいた方がなんとなく調子良いようですね。窓際だと光と温度が足りないようです。
下葉が薄黄色なのは、一度死にかけたから。上の葉はそうでもないんですけどね。


つるなしいんげん・サツキミドリ。
コンスタントに生るので、実を次々取ってやります。じゃないと弱りそうな気がします。
今日もこれだけ取れました。少し疲れてきたのか、長い莢が取れなくなってきましたね。



えだまめ・酒の友。2週間ほど前、無理やり土寄せをしました。
莢がついてきました。もう少し太れば、ほんとうに酒の友になってくれそうです。がんばれ。


水栽培の野菜たち。窓ぎわなので逆光ですいません。オクラーズ。
徒長はしていますが、水栽培と窓際と相性がいいのか、特に支障なくコンスタントに実がなります。
柔らかくて、くせがなく、美味しいオクラになります。
苗立ての際にかなり大きくしたのも良かったかもしれません。
光が少なくても、トマトやキュウリのように障害が出づらい感じがしています。


ペットボトルを横にして作った水耕栽培器では、にじいろ菜(不断草)を育てています。
種から水栽培ですが、だんだん大きくなってきました。多少徒長していますが、今後どうなるか。
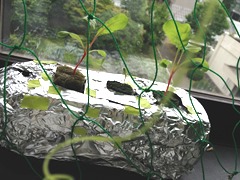
ミニトマト2号は、ひょろひょろですが、元気です(ピンボケすいません)。
1号を外に出したら調子良さそうなので、これも外に出そうかなあ。
ミニトマトは光が多い方が調子が良い気がするな。

きゅうりは一時すっかり葉が枯れ、茎だけになってきましたが、脇芽が出て、葉が広がってきました。
もうダメかな、と思ってたんですが、もうちょっと様子見ます。
最近、暖かくなって廊下の温度も上がったので、調子が良いのかも。

水耕栽培は、窓際でやってみて、一番相性が良かったのはオクラでした。
他、きゅうり、トマトは光が足りないのか一時寒かったのか、徒長して実もあまり付かなくなってきました。
今後どうなるか、観察してみます。
さて、明日には皆帰ってくるかな。お土産話を楽しみにしています。
おるすばん日記でした。
ますこ