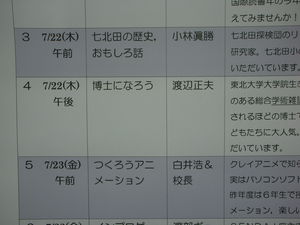昨年から始まった「未来の科学者養成講座」、東北大では「科学者の卵養成講座」と呼んでいますが。この講座の第一回全国大会が、東京大学で開催されました。東北大からも、昨年の発展コースから、2つのグループが発表し、高い評価を得ました。それぞれの大学でどの様な取組を行い、その結果、どの様な成果が受講生のレベルで達成されているのか、よく分かり、今年度以降の東北大の取組に活かしていこうと。
 3日間のプログラムでしたが、2日目の夜には、1日目とは違うグループで自己紹介のようなことではなく、3つの異なる講座を用意し、運営をされている各大学の先生方、受講生と討論会でした。そのうちの1つを、JSTの方からお願いされ、渡辺の方で提供しました。昨年の東北大のこの講座の1つの大きな特徴であった「キャリア教育」の一端を講義しました。少し中身をわかりやすくするようにと言うことで、「世界トップ水準の研究者を目指せ!!!--そのために不可欠な要素とは???--」と言うタイトルで講義をし、他の大学の先生方からのコメントをいただき、受講生との討論会でした。
3日間のプログラムでしたが、2日目の夜には、1日目とは違うグループで自己紹介のようなことではなく、3つの異なる講座を用意し、運営をされている各大学の先生方、受講生と討論会でした。そのうちの1つを、JSTの方からお願いされ、渡辺の方で提供しました。昨年の東北大のこの講座の1つの大きな特徴であった「キャリア教育」の一端を講義しました。少し中身をわかりやすくするようにと言うことで、「世界トップ水準の研究者を目指せ!!!--そのために不可欠な要素とは???--」と言うタイトルで講義をし、他の大学の先生方からのコメントをいただき、受講生との討論会でした。
コメントでは、様々な分野の先生方から、また角度の話を頂き、討論会では、高校生なりの様々な質問や実際の実験、研究の相談のような形でした。お開きの後には、数人でサイエンスの話で盛り上がっていました。
 最後に、東北大でも行ったレポートを手渡し、帰りまでに渡辺の手元に頂くことにしました。少し時間を頂きますが、また、受講生にコメントをfeedbackをしたいと思います。
最後に、東北大でも行ったレポートを手渡し、帰りまでに渡辺の手元に頂くことにしました。少し時間を頂きますが、また、受講生にコメントをfeedbackをしたいと思います。
初めての全国大会でしたが、とても良い交流ができたと思っております。来年もこうした会が引き継がれ、さらには、類似のプログラムとの交流ができればと感じました。最後になりましたが、organizeいただいたJSTの担当の方々に感謝したいと思います。
 わたなべしるす
わたなべしるす
PS. 1日目の東京は今年最高の暑さとか、夜になっても30oC近くありました。。。。本当に暑くて、東大までの銀杏並木の木もかわいそうなくらいでした。。。関連記事1, 2もありますので、お時間のある方は、そちらもどうぞ。

 3日間のプログラムでしたが、2日目の夜には、1日目とは違うグループで自己紹介のようなことではなく、3つの異なる講座を用意し、運営をされている各大学の先生方、受講生と討論会でした。そのうちの1つを、JSTの方からお願いされ、渡辺の方で提供しました。昨年の東北大のこの講座の1つの大きな特徴であった「キャリア教育」の一端を講義しました。少し中身をわかりやすくするようにと言うことで、「世界トップ水準の研究者を目指せ!!!--そのために不可欠な要素とは???--」と言うタイトルで講義をし、他の大学の先生方からのコメントをいただき、受講生との討論会でした。
3日間のプログラムでしたが、2日目の夜には、1日目とは違うグループで自己紹介のようなことではなく、3つの異なる講座を用意し、運営をされている各大学の先生方、受講生と討論会でした。そのうちの1つを、JSTの方からお願いされ、渡辺の方で提供しました。昨年の東北大のこの講座の1つの大きな特徴であった「キャリア教育」の一端を講義しました。少し中身をわかりやすくするようにと言うことで、「世界トップ水準の研究者を目指せ!!!--そのために不可欠な要素とは???--」と言うタイトルで講義をし、他の大学の先生方からのコメントをいただき、受講生との討論会でした。コメントでは、様々な分野の先生方から、また角度の話を頂き、討論会では、高校生なりの様々な質問や実際の実験、研究の相談のような形でした。お開きの後には、数人でサイエンスの話で盛り上がっていました。
 最後に、東北大でも行ったレポートを手渡し、帰りまでに渡辺の手元に頂くことにしました。少し時間を頂きますが、また、受講生にコメントをfeedbackをしたいと思います。
最後に、東北大でも行ったレポートを手渡し、帰りまでに渡辺の手元に頂くことにしました。少し時間を頂きますが、また、受講生にコメントをfeedbackをしたいと思います。初めての全国大会でしたが、とても良い交流ができたと思っております。来年もこうした会が引き継がれ、さらには、類似のプログラムとの交流ができればと感じました。最後になりましたが、organizeいただいたJSTの担当の方々に感謝したいと思います。
 わたなべしるす
わたなべしるすPS. 1日目の東京は今年最高の暑さとか、夜になっても30oC近くありました。。。。本当に暑くて、東大までの銀杏並木の木もかわいそうなくらいでした。。。関連記事1, 2もありますので、お時間のある方は、そちらもどうぞ。