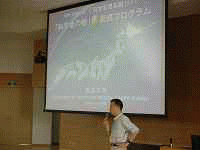all 東北大の企画である「経験・体験を通して「科学を見る眼」をもつ「科学者の卵」養成プログラム」を宮城県第二女子高等学校で、その概要、どういうコンセプトでやろうとしているのか、何を求めているのかなど、40-50名の生徒の前で1hrほど、説明をしてきました。HPも順調に更新しているためか、かなり受講希望があり、多くの質問を頂いたのは、なによりでした。普段の高校での学習、毎日の生活、そして、この科学者の卵が連動することが、その後の研究者であり、人生で重要かを説明してきました。
終わったあとに、こちらがなぜ、植物の研究をしているのかということを質問され、植物は動くことなく、晴れても雨が降っても同じところいるし、ヒトのように五感があるわけでもないのに、ちがう植物の花粉では、種ができないと言うことは、よく考えないと、当たり前にならない、ということでした。質問をくれて、答えを聞いた生徒さんは、明日から、植物を見る眼が変わることが楽しみです。もちろん、天文が好きと言うことも大事にして、それを植物とを連動することもできるかもしれません。ものは考えようですので。今日の説明会でお会いした生徒さんとまた、講座でお会いできることを楽しみにして。
とりいそぎ。
わたなべしるす