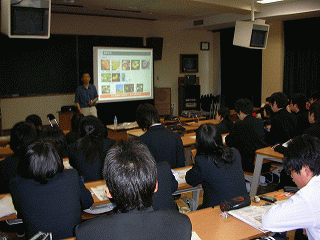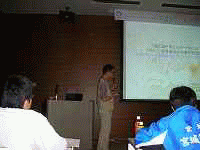
4月から高校1, 2年生を対象に募集していたall 東北大の企画である「経験・体験を通して「科学を見る眼」をもつ「科学者の卵」養成プログラム」の開講式、第1回特別講義を開催しました。100名という募集に対して、418名という4倍を超える応募があり、このプログラムを運営するコアメンバーとしては、心苦しい思いで、100名を選抜し、最初の講義に至りました。
当日は、13:00からの開始にもかかわらず、一部の高校生は10:30すぎから集まり始め、13:00からは、井上総長の開講式でのお言葉をいただき、第1回特別講義を行いました。2コマの講義のうち、最初は、渡辺が行い、「進化論を唱えたダーウィンも注目した高等植物の自家不和合性--花粉と雌しべの細胞間コミュニケーションとその分子機構--」と題して、植物の花粉と雌ずいの自他識別のモデルともいえる自家不和合性について、講義しました。講義のあとは、40min程度でレポート提出と質疑応答を行いました。今までにもずいぶん多くの出前講義を行いましたが、これほど集中して、切れのある質問をいただいたことは初めてでした。まさに、将来の「科学者の卵」としての高い能力を感じました。今年1年でどこまでレベルアップした高校生になるかと思うと、これからも楽しみです。
9月には、渡辺のこれまでの履歴な様なことを紹介する形で、キャリア教育を行いたいと思います。また、講義であえることが楽しみです。
わたなべしるす
PS. 当日は、プレスの取材もあり、TBCではローカルニュースで取り上げられました。
6/30付けの河北新報、教育欄にも、今回の講義のことが、細かく取り上げられていました。