 2008年最後の出前講義は、工学院大学附属中学・高等学校で、中学3年生を対象に、「植物の生殖・アブラナ科植物の多様性」について講義をしました。
2008年最後の出前講義は、工学院大学附属中学・高等学校で、中学3年生を対象に、「植物の生殖・アブラナ科植物の多様性」について講義をしました。
出前講義を始めて、3年あまりですが、中学生に講義をするのは、はじめてでした。東京の八王子といえど、都会。植物の花の写真をいくつか見せましたが、なかなか出てこなかったのは、やはり、地域性を感じました。これがきっかけとなって、植物に興味を持ってもらえるようになればと思いました。
今年もずいぶんたくさんの出前講義を行い、様々な生徒と出会え、話ができたのは幸いです。何より、そこに、東北大というtermで人のつながりがあったのは、とても不思議でした。
その意味でも、ぜひ、ここで講義で出会えた生徒と将来、研究ができればと思います。
わたなべしるす
工学院大学附属中学・高等学校で出前講義(12/16)
2008年12月22日 (月)
SSH指定校・福島県立相馬高校でのアブラナプロジェクト研究指導(12/5-6)
2008年12月 5日 (金)
 今年の夏から、東北地区のSSH高校で、アブラナプロジェクト研究指導を行っています。
今年の夏から、東北地区のSSH高校で、アブラナプロジェクト研究指導を行っています。
福島県立相馬高校では、B. oleraceaの多様性を形態、遺伝子レベルでの研究を展開しており、その研究内容の進展具合、今後の方針などについて、議論を行ってきました。植物の育成、isozyme研究方針など、生徒さんが積極的に行っていただいたおかげで、実り多きものでした。何より、同じ地区の相馬農業高校の方ともうまく連携しているようで、あすは、そちらの方で、植物の育成状況などを確認したいと思います。
今日の議論で、植物を育成することの大変さ、また、楽しさを感じてくれたようです。次に、伺うときにどのような発展があるかを楽しみにしています。
アブラナプロジェクト研究が大きく花開くように、年の瀬を走りたいと思った今日この頃でした。
わたなべしるす
沖縄県立八重山高校で出前講義(11/19-21)
2008年11月20日 (木)
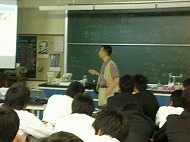 沖縄県立八重山高校で、自家不和合性、生殖の不思議、品種改良などをテーマに講義を行ってきました。今回の沖縄、それも最南端の高校での出前講義を設定していただいたのは、生命学研究科のサイエンスエンジェル(SA)の学生さんのおかげです。まず、最初にその方々に感謝します。
沖縄県立八重山高校で、自家不和合性、生殖の不思議、品種改良などをテーマに講義を行ってきました。今回の沖縄、それも最南端の高校での出前講義を設定していただいたのは、生命学研究科のサイエンスエンジェル(SA)の学生さんのおかげです。まず、最初にその方々に感謝します。
3日間でtotal 6コマの講義で、1~3年生の生徒さん、250名あまりに講義をしました。亜熱帯の自然に囲まれて生活している生徒さんで、とても活発に質問などがあり、有意義な時間でした。何より、自然の中で普段の生活があるからでしょうか。花の名前をよく知っています。それは、どこで講義をしたときよりも、高い割合で感動しました。また、物怖じせず、発表、質問する点は、本土の皆さんにも是非、見習ってほしい点です。
普段、東北地方にいたり、子供の頃生活した四国とも違う世界で、サクラの花びらが散らないと聞いたときには、驚きでした。そういえば、最近の新聞に温暖化が進行すると、そんなことが起きるとあったのを思い出しました。そう考えると、南北に長い日本という地形を生かして、交流すること、研究をすることの重要性を感じました。是非、今回講義をした生徒さんたちと、研究等ができればと思います。西表島も近くにあり、本州、四国とは違った生態系もありますので。るとか。
また、機会を見つけて、日本最南端で講義ができればと思います。あるいは、最西端、最北端なども。
わたなべしるす
仙台市立鹿野小学校で出前授業(11/18)
2008年11月18日 (火)
 仙台市教育委員会との提携で、今日は「鹿野小学校」で「出前授業」でした。国道286号線沿いにあり、何かで通るとよく見かけることはありましたが、講義で伺うのははじめてでした。1, 2校時が授業の時間でした。先週の吉成小学校同様に、リンゴをモデルとした、受粉、受精、自家不和合性、果実の成熟など、小学校5年生には少し難しい課題ではありましたが、一生懸命講義を聴いてくれて、質問ももらいました。朝早くの講義と言うこともあり、後半になるほど、生徒たちのエンジンもかかってきて、最後のリンゴの観察では、食い入るように見ていたのが印象的でした。
仙台市教育委員会との提携で、今日は「鹿野小学校」で「出前授業」でした。国道286号線沿いにあり、何かで通るとよく見かけることはありましたが、講義で伺うのははじめてでした。1, 2校時が授業の時間でした。先週の吉成小学校同様に、リンゴをモデルとした、受粉、受精、自家不和合性、果実の成熟など、小学校5年生には少し難しい課題ではありましたが、一生懸命講義を聴いてくれて、質問ももらいました。朝早くの講義と言うこともあり、後半になるほど、生徒たちのエンジンもかかってきて、最後のリンゴの観察では、食い入るように見ていたのが印象的でした。
また、最後に記念に生徒さんたちと集合写真を撮ったのも、初めての試みでした。これからもこうして生徒たちとふれあい、また、植物に興味を持ってもらえればと思います。
先週からでtotal 200名を超える生徒さんたちに講義をしました。早速、七北田小学校の生徒さんからは、お礼の手紙と質問が届いています。何とか、皆さんにクリスマスまでには、返事が書けるようにしたいと思っています。
このことがきっかけとなり、身の回りの植物の不思議に目を向ける子供が増えることを祈りつつ。また、どこかで新しい子供たちとの出会いを楽しみにしております。
わたなべ
仙台市立吉成小学校で出前授業(11/12)
2008年11月12日 (水)
 今年も仙台市教育委員会と東北大学との間で提携されている「出前授業」の季節になりました。今年の最初は、吉成小学校でした。農学部で助手をしたり、岩手大の助教授の頃、隣の南吉成に、東北インテリジェントコスモス関連企業の「採種技術研究所」があり、そこの所長を指導教官であり、恩師である東北大名誉教授の「日向博士」がされていたこともあり、近くには伺うことはありましたが、この場所に小学校があったのは、最近知りました。
今年も仙台市教育委員会と東北大学との間で提携されている「出前授業」の季節になりました。今年の最初は、吉成小学校でした。農学部で助手をしたり、岩手大の助教授の頃、隣の南吉成に、東北インテリジェントコスモス関連企業の「採種技術研究所」があり、そこの所長を指導教官であり、恩師である東北大名誉教授の「日向博士」がされていたこともあり、近くには伺うことはありましたが、この場所に小学校があったのは、最近知りました。
さて、11/12の午前の3, 4校時で、リンゴをモデルとした、受粉、受精、自家不和合性、果実の成熟など、小学校5年生には少し難しい課題ではありましたが、一生懸命講義を聴いてくれ、また、最後に、こちらが困ってしまうようなシビアな質問もくれました。また、機会があれば、キャベツとブロッコリーの不思議も講義できればと思います。
今回お世話になった5年生の先生には、昨年、川前小学校でもお世話になり、人のつながりに驚かされ、また、大変お世話になりました。何より、今回の授業をサポートしていただいた5年生の先生方に感謝するとともに、なれない、2校時続きの授業を最後まで熱心に聞いてくれた生徒さんに感謝です。最後に質問の時間が切れてしまったのは残念だったので、是非、また、質問の手紙でもいただければ、応えたいと思います。
わたなべ

