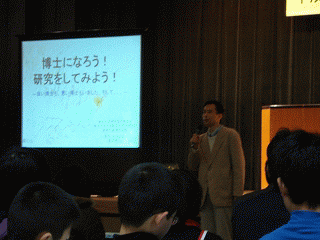今から、30年くらい前に渡辺は、今治市立桜井小学校の6年生でした。その頃から、今治市周辺では、5, 6年生になると理科は理科専科の先生に授業をしてもらい、そうした先生方がお世話役をして、理科とか自然が好きな生徒を集めて、「今治自然科学教室」というのが毎月、開催されていました。海、山などの自然をめぐり、植物を観察したり、化石を見たり、とても楽しかったのを未だに覚えています。
それから、30年ほどたった3/1に、今治自然科学教室の年末の報告会に、講師として招待され、200名程度の生徒さんの前で、小学生の頃からどう考え、科学者になろうと思ったのか、博士になったのか、今の職業に就いているのかという講義を1.5hr程度行いました。30年前にこのような講義をすることなど、夢にも思わず、毎月の教室に通っていたのを思い出しました。
博士とは、研究者とはどのようなものであり、そこに至るまでの過程が、小学生にも少しは理解してもらったのではないかと思います。昨今の理科離れを防止するためにもこうした活動の重要性を感じました。
自然に恵まれた愛媛で子供の頃を過ごすことがどれだけ、科学者の心を育てるか、豊かにするかということを、理解してもらい、今持っている科学に対する興味を失わないで大きく育ってほしいと思いました。この機会に講義を聴いてもらった生徒さんと将来一緒に研究をしたり、何かを一緒にやる機会ができれば、さらにうれしいと思ったのでした。
そういえば、早速、参加していた小学生から質問をもらいました。ありがとうございました。
今回の特別講義には、昨年の今治市立日吉小学校、今治小学校での出前講義がきっかけであり、今治自然科学教室会長の武本先生、事務局長の渡邊先生に大変お世話になりました。この場を借りてお礼申し上げるとともに、今後も、何らかの形で、こうした自然科学を楽しむ心を養う生徒さんたちを支えることができればと思っております。
わたなべしるす