
秋のアブラナの交配
2009年11月24日 (火)

キャベツ・多様性・人のつながり。。。。
2009年11月18日 (水)
 仙台も随分と寒くなり、あっという間に、11月も半分以上終わったことに気がつき、今年書き残した論文をなんとか今年中にと思って、日々、こうしたことに追われています。「もったいない」というのは、国際語のようで、ご飯粒を残すのは、作ってくれた農家の人に申し訳ないと教えられました。というわけではないですが、やはり、実験をしてくれた人、協力してくれた人に、感謝する意味でも、積み残しをしないで、たくさんの論文を書きたいと思うのでした。
仙台も随分と寒くなり、あっという間に、11月も半分以上終わったことに気がつき、今年書き残した論文をなんとか今年中にと思って、日々、こうしたことに追われています。「もったいない」というのは、国際語のようで、ご飯粒を残すのは、作ってくれた農家の人に申し訳ないと教えられました。というわけではないですが、やはり、実験をしてくれた人、協力してくれた人に、感謝する意味でも、積み残しをしないで、たくさんの論文を書きたいと思うのでした。
今年もずいぶんたくさんの出前講義などに出かけました。また、日本各地で、アブラナの多様性、ダイコンの多様性の研究のお手伝いもしております。そんな折、そんな出前講義を大きく発展させるきっかけを頂いたJSTのとある方から、とても興味深いHPのURLを教えていただきました。
なんと、そこには、研究材料である、Brassica oleraceaというラテン語名のいわゆる「ハボタン(花キャベツともいうそうです)」が大きく写っており、また、その脇に、ちゃんと、その花が添えてあり、とても感動しました。この種には、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、芽キャベツ、コールラビー等、多様性に富んでいますし、食卓でも見かける身近な野菜です。
そんな野菜も、ちょうどこの時期、お正月前には、ハボタンの生け花をしたり、マツなどと一緒にはち植えにして、お正月らしさを出すのに使われるものです。種をまいてすぐは、キャベツと変わりませんが、大きくなるにつれて、葉っぱがまかないで、ただただ広がり、中心部が白くなったり、赤くなったり。たぶん、アントシアニン系の色素が欠落した変異体、あるいは、その色素ができる変異体なのだろうと、町中で見つけると、うれしくなるものでした。
それがなんと、JSTから出ている「科学するこころを開く Science Window」の表紙を飾るとは。。。早速、A4に印刷して、そのきれいさに感動するとともに、自分が実験に使っている材料をこの様に取り上げてくれるところがあったこと、それが、サイエンスつながりで、高校生のSSHであったり、大学の未来の科学者養成のサポートをしているJSTであったことに、人のつながりは、なんと不思議なことなのかと。
誰かの言葉だと思いますが、「集団は多様だから、進化する」というようなニュアンスの言葉があったような気がします。キャベツがもっている自家不和合性も、多様性を獲得する重要な形質であり、それの分子機構を解明しようとしているわけです。研究室だけに限らず、できるだけ外の様々な方と接して、また、共同研究を行ってきたことが、大きな広がりになったのだと思っています。これも人のつながり、そして、新たな多様性を生むことになるのだろうと。
https://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/concept.html
そんなことを思ったとき、出前講義で多様性の講義を始めるきっかけを頂いたJSTの方に感謝の心でいっぱいになった次第で、とりとめのない文章を書いたのでした。さらに人がつながり、研究をする楽しさを伝え、それがまたどこかでつながれば、良いと思っています。ありがとうございました。
わたなべしるす
静電気除去と冬じたく
2009年11月16日 (月)
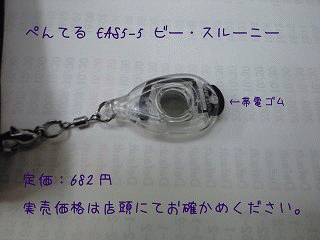 冬の便利グッズシリーズ。
冬の便利グッズシリーズ。
今回は冬の風物詩"バチッ!"からあなたを守る!静電気除去グッズをご紹介します。
部屋が乾燥してくると、突然 "バチッ!" とくる静電気。気になりますよね。
ただ痛いだけではなく、静電気によって大事な精密機器に被害が及ぶ可能性も。。。
そんなときにお使い頂きたいのが、ぺんてるの静電気除去キーホルダー"ビー・スルーニー"です。
根本の金属部分を持って帯電ゴムで金属部分にタッチすれば、体に帯電した静電気を除去する優れもの。
シースルーの液晶画面から静電気除去の確認が出来、満足感もバッチリです。
車のドアや、金属ノブを触る前にお使い頂ければ、あなたを"バチッ"から守ります!
お求めは文具店、バラエティショップ、大学生協片平店にて(定価682円)。
そんなこんなで(どんなだ)渡辺グループ全体でも冬じたくが始まっています。
温室では秋のアブラナシーズンも終盤を迎え、先日収穫したイネの種整理も進み、居室や実験室にも暖房が入り。。。冬がはじまるよ、といったところ。
大掃除の準備もそろそろ。
忘年会の計画も着々進行中のようです(がんばれおだ幹事長!)。
個人的には新型インフルエンザにかからないように過ごしたいです。
ますこ
ついしん:
写真2枚目は、静電気除去シートです。
導電樹脂の働きで体に溜まった電気を逃がす。。。エレベータ前で良く見るアレです。
現在、ラボの入り口とアラビ部屋の入り口にて試験運用中ですが。。。
最近あんまパチっていわなくなったような気が。
ドラゴンフルーツ
2009年11月12日 (木)
先人の名言と智恵と。。。
2009年11月 7日 (土)
 昔の人はなるほどということをたくさん残している。講義でよく使う「勝ちに不思議の勝ちあり 負けに不思議の負けなし」は、戦国時代の武将らしい。よくわからないけど、勝つことがあるが、負けたことには理由がある。反省しようというのがその心らしい。 先人といえば、東北大附属図書館では、「江戸時代のサイエンス」という企画展をしている。
昔の人はなるほどということをたくさん残している。講義でよく使う「勝ちに不思議の勝ちあり 負けに不思議の負けなし」は、戦国時代の武将らしい。よくわからないけど、勝つことがあるが、負けたことには理由がある。反省しようというのがその心らしい。 先人といえば、東北大附属図書館では、「江戸時代のサイエンス」という企画展をしている。
http://tul.library.tohoku.ac.jp/modules/coll/index.php?content_id=88
今日の科学者の卵プログラムで、見学会があり、実に20年ぶりだろうか、附属図書館にいくことになった。教養部で1, 2年生をしていたことを思い出した。昔も、こうした企画展があったのかもしれないが、あまり見ることもなく、遅くまでレポートを書いたりすることで使ったのくらいしか、記憶にない。今となっては、電子図書館というか、雑誌のpdfを読めればよいので、図書館に行くこともなくなった。
話を戻すが、江戸時代のサイエンスがよくできていたことは、ある一面では知られていることもある。関の和算、からくり、などなど。一方で、「変わりアサガオ」というのは、あまり知られていない。メンデル遺伝がもちろん、発表されていなく、西洋のそうした考えが鎖国されていた日本で、いかに多重劣性の変異体の花を咲かせ、また、そのheteroの種を維持し続けたのか、まさに先人の智恵であり、その「経験と勘」のようなものが現在に伝承されてないのは、残念である。一説には、その技術が秘密で、一子相伝で伝えられたとか。。
今年から開講した「科学者の卵プログラム」で渡辺が講義をした「自家不和合性」も、進化論を唱えたチャールズ・ダーウィンと関係が深い。
http://www.ige.tohoku.ac.jp/cgi-bin/prg/watanabe/news/news.cgi?mode=dsp&no=104&num=35
http://www.ige.tohoku.ac.jp/mirai/news/2009/06/13095847.php
http://www.ige.tohoku.ac.jp/mirai/activity/2009/07/14170653.php
彼は、このような名言を残している。「もっとも強い者が生き残るのではなく、もっとも賢い者が残る者が生き残るのでもない。唯一生き残るのは、変化できるものである。」生き物を観察し、進化論を唱えたというチャールズ・ダーウィンらしい言葉だと。現在どんなに強くても、賢くても、環境に合わせて、変えることができなければ、生き残れないのだと。植物を観察していると、そんなことに気がつかされることは、そういえば、あるのかもしれない。よい1日でした。
わたなべしるす


