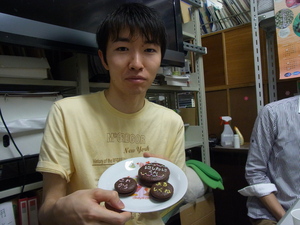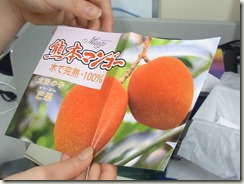仙台は今日、雨だけど蒸し暑い一日となっております。
もう、関東は梅雨明けしたらしいですね。カラ梅雨でしたねえ。。
さて、先週金曜日、古武城さんが毎年恒例、例のブツを持ってきてくれました!

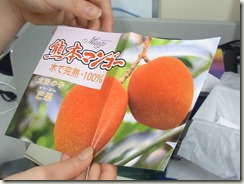
そう、マンゴーです!なんて日だ!
毎年、マンゴーを送って下さる、古武城さんのご実家の皆様方、ありがとうございます。
早速、古武城さんが切り分けてくれました。素晴らしい手際。
みずみずしい果汁あふれる、ツヤツヤマンゴー。今年も非常に美味しく頂きました。
"はじめて食べたけど、今までのマンゴーが食べられなくなりそう。"
"うまーーーーーー。あまーーーーーーー。"
"もう一個食べとこ。"
"次食べるのはいつになるか。。。(遠い目)"
などの感想が飛び交っていました。


ついでに温室ミズナも全部収穫し、黒ニンニクマヨネーズ味噌に和えて、出しました。
渡辺先生のお土産。黒ニンニクを使ってみましたよー!
ミズナがだいぶ育ってしまい、硬くなってしまったので、茹でて水にさらしてから和えましたが。。。
"うまい。"
"この食べ方は、クセが抑えられて食べやすい。"
"しゃきしゃきする。"
"黒ニンニク、味噌に合うねえ。"
などの感想が出ていました。よかった。


須藤くんのお土産、栃木名物イチゴのカレーも食べました。
(↑リンクからamazonのページに飛びます。パッケージが見られます。)
イチゴピューレ由来の、イチゴの種が入ってますよ(写真右)。
"粒??粒入ってますよ??"
"あまい。。。すっぱい。。。か??"
"カレーの香りのあとイチゴの香りするかも。。。"
"でも普通に美味しい。"
などの感想が出ていました。美味しかったです。


マンゴー提供・古武城さん、黒ニンニク提供・渡辺先生、イチゴカレー提供・須藤くん、ありがとうございました!
そんなこんなで、いろいろ盛りだくさんの豪華な、栄養的にもバランス取れた昼食になりました。
増子(鈴木)
後日談。
今年もマンゴーを植えたよ(7/8)。いままでの生長記録(最近さぼってるけど)はこちら。
乾かしたマンゴーの種、皮を取って。。。中に種があるのね。


鉢に入れて、マンゴー3号のできあがり。大きくなるといいなあ。


1号と2号は、葉の病気がひどくって。。。葉を全部落とし、頂芽を切りました。
マンゴーはある程度育ったら、てっぺんを切らないと枝分かれしないらしいの。
頑張って再生してほしいです。