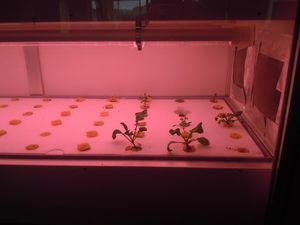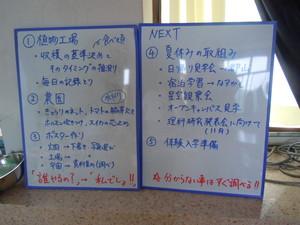こんにちは、M1の辺本です。
今日は7月22日、土用の丑の日ですね。土用の丑の日と言えば・・・鰻を食べる日!
実は私たち・・・一足早く(7月18日)鰻を食べてきました。
なかなか行くことができないであろう雰囲気の良すぎるいわま亭で・・・誠に美味でした。
あ~幸せ。なべさん、ありがとうございました。
さて、土用の丑の日。
土用って、土曜のことではないの?幼い頃こう考えていた人は私だけではないはず。
土用は、全てのものが木、火、土、金、水という5つの元素から成っているという中国の五行思想からきています。
春=木、夏=火、秋=金、冬=水というように、季節ごとにそれぞれの元素を当てはめていくと、「土」があまる・・・
じゃあ、季節の変わり目ってことにしよう、となったのだそうです。
よって土用とは、季節の変わり目を指し、立夏、立秋、立冬、立春の直前約18日間を指します。
ちょうど体調を崩しやすい時期ですね。
次に丑の日とは、十二支の干支が丑の日ということです。
子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥・・・
最近では、今年の干支は○○といったようにしか使われなくなってしまいましたが、
昔は日、そして時間にも適用されていました。
それにしても何故、丑の日なのか・・・それは、江戸時代に遡ります。
夏場は暑くて食欲失せますよね。今のように冷房など無かった時代なら尚更でしょう。
そんな中、鰻の売り上げ不振に悩んだ鰻屋が「鰻が売れなくて困るよー」と平賀源内というお方に相談したそうです。
すると、源内は「本日、土用丑の日」というキャッチコピーを考案し、鰻屋の前に張り紙したのです。
その広告のおかげと、それに加えて「丑の日」と「鰻」の語呂が良かったのもあり、
夏場にも関わらず鰻屋が商売繁盛になったのだとか。
これが「土用の丑の日は鰻」が習慣になったきっかけだと言われています。
(※ちなみに土用の丑の日に関する説は、他にもあるそうです。)
ということで、土用の丑の日は季節の変わり目である18日間の丑の日。特に夏の土用の丑の日のことを言います。
夏バテしやすい時期に、鰻を食べてスタミナをつけましょうということです。
地方によっては鰻に限らず、「う」の付く食べ物をたべる習慣があるのだとか。
うどん、梅干し、ウニ・・・などでしょうか?あれ、「う」から始まる食べ物ってなかなか無いですね。
ここ最近は鰻の価格が高騰し、高級食品となりつつあるので、土用の丑の日にうどんを食べることもアリなのですよ。
土用の丑の日に食べるものが、変わっていきそうですね。
私にとっては初めての仙台の夏。
夏バテしないように、食事、睡眠を十分に摂りたいと思います。
軽く運動もしたいなーと思う今日この頃。そう言えば・・・運動ですが、先週走りました。
あれ、観戦なのに何故?
はて、何故だろうか・・・翌日、全身筋肉痛でした。なべさんは大丈夫だったのだろうか。
最後に。
土用の丑の日ですが、18日間で十二支がまわると言うことは、土用の期間に丑の日が2回来ることだってあるのです。
まさに今年の夏がそうです!土用の丑の日が2回やってきます!
7月22日(一の丑)と、8月3日(二の丑)。
二の丑の時は、うどんを食べようかしら。
M1 なべ