仙台も梅雨明けして、朝から、片平地区は作業停電。。。。いつも夏の暑い時期で。。。梅雨明けしてなければ、涼しいので、labの温度などを気にしなくてよいと思っていたのが、。。。梅雨明けは想定外でしたが、イネの生育、蔬菜、果樹の生長には梅雨明けは必要ですので。。。
 そんな日曜日、渡辺は学会の仕事というか、。。そんなで関西に。。。labの停電の最後を見て、帰ろうとしていた高田君から、こちらの携帯に電話が。こちらは会議の直前でした。地震の速報で、宮城県でM5強があったと。。。去年の鹿児島出張の時もそうでしたが、出ている時に限って、。。。いつも頭を抱えます。こちらも慌てて、netをつないだら。。。震度5強は石巻市だけ。仙台市青葉区は、震度4。たぶん、これなら、大丈夫だろう。ただ、陸地に近いところが震源だったので。。。そのあと、改めて高田君から、研究室内の変化はないという連絡があり。。。かなりほっとしました。
そんな日曜日、渡辺は学会の仕事というか、。。そんなで関西に。。。labの停電の最後を見て、帰ろうとしていた高田君から、こちらの携帯に電話が。こちらは会議の直前でした。地震の速報で、宮城県でM5強があったと。。。去年の鹿児島出張の時もそうでしたが、出ている時に限って、。。。いつも頭を抱えます。こちらも慌てて、netをつないだら。。。震度5強は石巻市だけ。仙台市青葉区は、震度4。たぶん、これなら、大丈夫だろう。ただ、陸地に近いところが震源だったので。。。そのあと、改めて高田君から、研究室内の変化はないという連絡があり。。。かなりほっとしました。
netという便利なものができたことで、迅速にこうしたことに対応できるというのは、何よりもほっとします。ちょうど停電で研究室のHPがdownしている時で。。。世の中、よくできているというか、。。。困ったものというか。。。今回は、Twitterなるもので、速報を打つことができるというものトライしてみました。あらかじめ、ご覧になった方もいるのでは。。。
わたなべしるす
PS. 作業停電も予定通り終わったと。。。研究室も改めて、スタッフ、院生の方々が確認してくれて、特に被害はないと。。。被害がないのと、netの迅速な復旧はありがたいものです。と、作業停電の対応頂いた皆様に、感謝です。。。ありがとうございました。
 そんな日曜日、渡辺は学会の仕事というか、。。そんなで関西に。。。labの停電の最後を見て、帰ろうとしていた高田君から、こちらの携帯に電話が。こちらは会議の直前でした。地震の速報で、宮城県でM5強があったと。。。去年の鹿児島出張の時もそうでしたが、出ている時に限って、。。。いつも頭を抱えます。こちらも慌てて、netをつないだら。。。震度5強は石巻市だけ。仙台市青葉区は、震度4。たぶん、これなら、大丈夫だろう。ただ、陸地に近いところが震源だったので。。。そのあと、改めて高田君から、研究室内の変化はないという連絡があり。。。かなりほっとしました。
そんな日曜日、渡辺は学会の仕事というか、。。そんなで関西に。。。labの停電の最後を見て、帰ろうとしていた高田君から、こちらの携帯に電話が。こちらは会議の直前でした。地震の速報で、宮城県でM5強があったと。。。去年の鹿児島出張の時もそうでしたが、出ている時に限って、。。。いつも頭を抱えます。こちらも慌てて、netをつないだら。。。震度5強は石巻市だけ。仙台市青葉区は、震度4。たぶん、これなら、大丈夫だろう。ただ、陸地に近いところが震源だったので。。。そのあと、改めて高田君から、研究室内の変化はないという連絡があり。。。かなりほっとしました。netという便利なものができたことで、迅速にこうしたことに対応できるというのは、何よりもほっとします。ちょうど停電で研究室のHPがdownしている時で。。。世の中、よくできているというか、。。。困ったものというか。。。今回は、Twitterなるもので、速報を打つことができるというものトライしてみました。あらかじめ、ご覧になった方もいるのでは。。。
わたなべしるす
PS. 作業停電も予定通り終わったと。。。研究室も改めて、スタッフ、院生の方々が確認してくれて、特に被害はないと。。。被害がないのと、netの迅速な復旧はありがたいものです。と、作業停電の対応頂いた皆様に、感謝です。。。ありがとうございました。








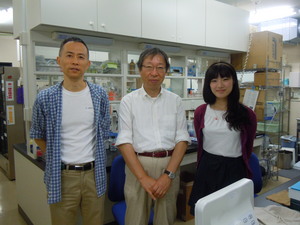

-%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%B4%99-thumb-250x355-6414.jpg)



