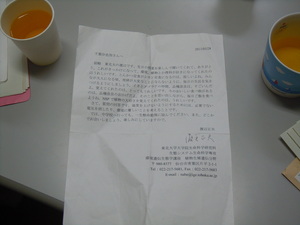7月12日、生命科学研究科全体のソフトボール大会が行われました。
そして、この日は予定が入っているメンバーも多く、全員出場でも人数が足りるか足りないか・・・・。
ということで、数年ぶりに渡辺先生も出場して下さいました!
いつもピッチャーを担当している増子さんがお休みだった為、渡辺先生がピッチャーに。
ほとんどのアウトを先生がとってくれたと言ってもいいでしょう。
また、ホームに戻ってきて貴重な1点を入れてくれたのも先生でした。
ありがとうございました。
元野球少年、大坂さんもカキーンとうってくれました。
結果は2試合して2敗という残念な結果になってしまいましたが、楽しく体を動かすことができました!
そして、お昼はバーベキュー!
なかなか火が付かないというハプニングもありましたが、
助けを借りて、なんとかバーベキューをすることができました。
本当に感謝です。
そしてみなさん、そろそろお気づきでしょうか。
今年のラボTシャツはいつもとちょっと違います!
じゃーーーーーーーーーーーーーーーん!!!
みんな色違いで、かっこいいロゴが背中に入っています!!
企画:大坂さん、構成:須藤さん、デザイン:増子さん
で出来上がった力作です!!!!
ありがとうございます!!!
アップするとこんな感じ。
サギソウをイメージしたサギ、アスパラ、アブラナ、イネなど、
菅野研、渡辺研それぞれの研究テーマとなっている植物が盛り込まれています!!
秋のスポーツ大会でもまた活躍してくれることでしょう。
体を動かして、日ごろの運動不足を解消し、気分もリフレッシュしました。
気持ちを新たに、研究など頑張っていきたいです。
M2 曽根