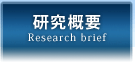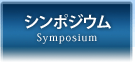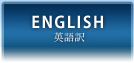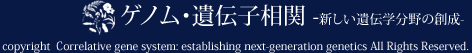文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」
新学術領域|ゲノム・遺伝子相関
月別アーカイブ
計画研究班別アーカイブ
公募研究班別アーカイブ
旧公募研究班別アーカイブ
「研究経過報告」内を検索
研究成果がEcology and Evolutionに公開されました
研究成果がEcology and Evolutionに公開されました。
外来種は、様々な生態学的、社会的な問題を引き起こしています。これら外来種が何故、本来ではない生息地にうまく適応し、在来の固有種を駆逐するまでに定着してしまうのか、その詳しい原因はよく分かっていません。ゲノム遺伝子相関では、集団間の交雑が外来種の適応能力に与える影響について、その遺伝機構の解明に取り組んでいます。
今回の研究で、北野班では、カルデラ湖という本来ではない生息地に定着した小魚イトヨに着目し、その適応機構を詳細に調査し、その成果を米国科学雑誌「Ecology and Evolution」に報告しました。
現在、北日本を代表する三つのカルデラ湖(十和田湖、屈斜路湖、支笏湖)にトゲウオ科魚類のイトヨが定着していますが、いずれも外来の集団であると考えられます。カルデラ湖は火山で形成された湖であり、そもそも魚類は生息していなかったと考えられます。そこへ何らかの人的放流によって導入されたと考えられます。遺伝調査の結果、三つのカルデラ湖のイトヨは、別々の独立したイトヨ集団の放流が原因であることが明らかになりました。特に屈斜路湖の場合には、複数回の放流が行われ、北米の集団に近い遺伝型を持った個体も発見されていることから、北米からのサケマスの移植事業に伴って持ち込まれたと推定されました。また、十和田湖イトヨの過去50年間の追跡調査の結果、移入直後から体のサイズや形態を著しく変化させて新規環境に適応してきたことが明らかになりました。
Adachi, T., A. Ishikawa, S. Mori, W. Makino, M. Kume, M. Kawata, and J. Kitano (2012). Shifts in morphology and diet of non-native sticklebacks introduced into Japanese crater lakes. Ecology and Evolution In press オープンアクセスです