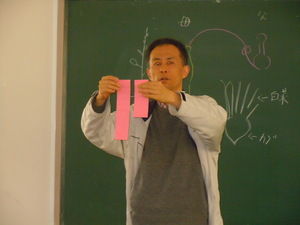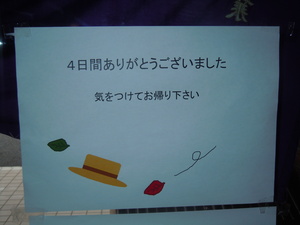5月も半ば過ぎ。仙台での生活の方が長くなり、今治で過ごした子供時代に、いつ頃、ツクシをとったり、タケノコを掘ったりするのは、いつ頃だったのか。いわゆる、旬である。こうしたことをしなくなったせいか、物事の旬を忘れつつある。唯一、研究で使っているアブラナ、イネの旬というか、季節くらいは認識できている。本当においしいというか、それの季節を旬というのであろうが、これだけ、ものが豊富にあると、旬というのがわかりにくいのも事実である。こうした、作物というか、食べ物というか、そうしたものにももちろん旬があるが、物事にも旬がある。いつの時代に何をするのか、どのタイミングを旬にするかによって、変わってくる。ひとによって、旬の感じ方、とらえ方が違ってくる。ただ、できるだけ、早い時期を「旬」と考えることができれば、それぞれが様々なトライをできる。もちろん、それぞれがそれぞれの「旬」を感じて、積極的に行動できる力は、不可欠であろう。
 様々なことにトライすることは、もちろん重要であるが、いろいろなことをやってみると、向き不向きはある程度分かってくる。小学校の頃、運動は苦手で、鉄棒から手を離して落ちたこともあるらしい。らしいというのは、親が、担任の先生から聞いた伝聞なので、本人は意外なことに自覚していない。たぶん、低学年で、低いところからだったのかも知れない。ただ、こうしたことで、自然と怖さも感じたのだろうか。跳び箱、登り棒など、どれも不得手であった。まともな逆上がりができるようになったのは、ある程度の筋力がついて、懸垂で体を持ち上げてからのような気がする。今できるのか、。。。よく分からないが、今度の出前講義の時に、見つけてトライしてみたい。ただ、これが、鉄棒から落ちた記憶が、自分にもっと大きくあったら、こうはいかないだろう。。つまり、ある程度のことができるようになってから、トライすることも大事と言うことかも知れないが、過去の記憶が逆にじゃまをするかも知れないことの、両方があり得ると言うことである。向き不向きはそれまでの経験がpositive, negativeのいずれにも働くのかも知れない。良いとか、悪いとかでなく。。。ただ、やってみようという意志を持って、トライしたいものである。
様々なことにトライすることは、もちろん重要であるが、いろいろなことをやってみると、向き不向きはある程度分かってくる。小学校の頃、運動は苦手で、鉄棒から手を離して落ちたこともあるらしい。らしいというのは、親が、担任の先生から聞いた伝聞なので、本人は意外なことに自覚していない。たぶん、低学年で、低いところからだったのかも知れない。ただ、こうしたことで、自然と怖さも感じたのだろうか。跳び箱、登り棒など、どれも不得手であった。まともな逆上がりができるようになったのは、ある程度の筋力がついて、懸垂で体を持ち上げてからのような気がする。今できるのか、。。。よく分からないが、今度の出前講義の時に、見つけてトライしてみたい。ただ、これが、鉄棒から落ちた記憶が、自分にもっと大きくあったら、こうはいかないだろう。。つまり、ある程度のことができるようになってから、トライすることも大事と言うことかも知れないが、過去の記憶が逆にじゃまをするかも知れないことの、両方があり得ると言うことである。向き不向きはそれまでの経験がpositive, negativeのいずれにも働くのかも知れない。良いとか、悪いとかでなく。。。ただ、やってみようという意志を持って、トライしたいものである。
高校3年の時に見たNHK特集「謎のコメが日本をねらう」。これをきっかけにして、作物の品種改良、遺伝学のおもしろさに目覚め(????)、農学部植物育種学研究室を目指した。ただ、高校2年生の時には、ロケットを打ち上げてみたかった。そういえば、あの当時はやっていたペンシルケースには、スペースシャトルのデザインがあった。そのためだろう、大学はいってすぐの頃の「チャレンジャー号爆発事故」は、ショックであった。その後も、様々なロケットが打ち上げられるニュースなどを見るのは、何ともいえない興味があった。今日のニュースを見ていて、「イプシロンロケット」なるものが、新しく開発され、しばらくしてかも知れないが、8月に打ち上げられるとか。かなり小型であるが、かなりすごいものだと感じた。これまでのものを改良し、制御もこれまでのような大型でないというのが、感動であった。ロケットと遺伝学。どこかで結びつくことはないだろうか。物理学と遺伝学でも良いのかも。。。やりたいと思っていた、異分野をくっつけたら、新しいものが見えてこないだろうか。。。。もちろん、自分でロケットを打ち上げることはできないのであるが。。。
 わたなべしるす
わたなべしるす
PS. 出前講義の七北田小学校でお世話になっていた、板橋教頭先生。この4月から、仙台市立福岡小学校の校長先生に。挨拶状をいただき、久しぶりに電話でおはなしでき、また、出前講義に伺えると。。いつもの教頭先生の気合いを頂きました。
一方で、パソコンのkey boardに、飲もうと思っていた液体をこぼして。。。。(そのあとは、ご想像にお任せします。。。)。なんともいえない、なさけなさを。。というのと、周りの方々にご迷惑をおかけしました。改めて、気合いを入れ直します。。。(いつかこうしたことが起きるのではないかという机の上と言うことを改めて、考え直さないと。。。)
 様々なことにトライすることは、もちろん重要であるが、いろいろなことをやってみると、向き不向きはある程度分かってくる。小学校の頃、運動は苦手で、鉄棒から手を離して落ちたこともあるらしい。らしいというのは、親が、担任の先生から聞いた伝聞なので、本人は意外なことに自覚していない。たぶん、低学年で、低いところからだったのかも知れない。ただ、こうしたことで、自然と怖さも感じたのだろうか。跳び箱、登り棒など、どれも不得手であった。まともな逆上がりができるようになったのは、ある程度の筋力がついて、懸垂で体を持ち上げてからのような気がする。今できるのか、。。。よく分からないが、今度の出前講義の時に、見つけてトライしてみたい。ただ、これが、鉄棒から落ちた記憶が、自分にもっと大きくあったら、こうはいかないだろう。。つまり、ある程度のことができるようになってから、トライすることも大事と言うことかも知れないが、過去の記憶が逆にじゃまをするかも知れないことの、両方があり得ると言うことである。向き不向きはそれまでの経験がpositive, negativeのいずれにも働くのかも知れない。良いとか、悪いとかでなく。。。ただ、やってみようという意志を持って、トライしたいものである。
様々なことにトライすることは、もちろん重要であるが、いろいろなことをやってみると、向き不向きはある程度分かってくる。小学校の頃、運動は苦手で、鉄棒から手を離して落ちたこともあるらしい。らしいというのは、親が、担任の先生から聞いた伝聞なので、本人は意外なことに自覚していない。たぶん、低学年で、低いところからだったのかも知れない。ただ、こうしたことで、自然と怖さも感じたのだろうか。跳び箱、登り棒など、どれも不得手であった。まともな逆上がりができるようになったのは、ある程度の筋力がついて、懸垂で体を持ち上げてからのような気がする。今できるのか、。。。よく分からないが、今度の出前講義の時に、見つけてトライしてみたい。ただ、これが、鉄棒から落ちた記憶が、自分にもっと大きくあったら、こうはいかないだろう。。つまり、ある程度のことができるようになってから、トライすることも大事と言うことかも知れないが、過去の記憶が逆にじゃまをするかも知れないことの、両方があり得ると言うことである。向き不向きはそれまでの経験がpositive, negativeのいずれにも働くのかも知れない。良いとか、悪いとかでなく。。。ただ、やってみようという意志を持って、トライしたいものである。高校3年の時に見たNHK特集「謎のコメが日本をねらう」。これをきっかけにして、作物の品種改良、遺伝学のおもしろさに目覚め(????)、農学部植物育種学研究室を目指した。ただ、高校2年生の時には、ロケットを打ち上げてみたかった。そういえば、あの当時はやっていたペンシルケースには、スペースシャトルのデザインがあった。そのためだろう、大学はいってすぐの頃の「チャレンジャー号爆発事故」は、ショックであった。その後も、様々なロケットが打ち上げられるニュースなどを見るのは、何ともいえない興味があった。今日のニュースを見ていて、「イプシロンロケット」なるものが、新しく開発され、しばらくしてかも知れないが、8月に打ち上げられるとか。かなり小型であるが、かなりすごいものだと感じた。これまでのものを改良し、制御もこれまでのような大型でないというのが、感動であった。ロケットと遺伝学。どこかで結びつくことはないだろうか。物理学と遺伝学でも良いのかも。。。やりたいと思っていた、異分野をくっつけたら、新しいものが見えてこないだろうか。。。。もちろん、自分でロケットを打ち上げることはできないのであるが。。。
 わたなべしるす
わたなべしるすPS. 出前講義の七北田小学校でお世話になっていた、板橋教頭先生。この4月から、仙台市立福岡小学校の校長先生に。挨拶状をいただき、久しぶりに電話でおはなしでき、また、出前講義に伺えると。。いつもの教頭先生の気合いを頂きました。
一方で、パソコンのkey boardに、飲もうと思っていた液体をこぼして。。。。(そのあとは、ご想像にお任せします。。。)。なんともいえない、なさけなさを。。というのと、周りの方々にご迷惑をおかけしました。改めて、気合いを入れ直します。。。(いつかこうしたことが起きるのではないかという机の上と言うことを改めて、考え直さないと。。。)