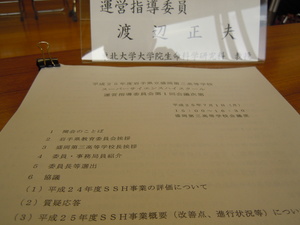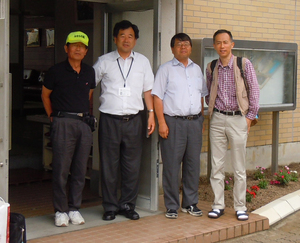先週あったことなのですが、週末にかけて、特にこれということもなかったのですが、記すのをすっかり失念しておりました。昨年に続いての石川県立小松高等学校・ESS部「ディベート討論会」の論旨表現について。昨年よりもずいぶん早い議論のタイミングでしたので、考えられる可能な限りのことを伝えることができたのではと思います。
では、今年のお題は、全部をそのまま書く訳にはいかないので。。。「外国産米の関税について。。」ということにしておきます。農学部出身ですし、大学院の入試で、農業経営学をとった位なので、ある程度のことはわかっているのですが。。。いざ、説明しようとすると。。。何より、輸入米の問題は関税以外の問題もたくさんあり。。その当たりの整理に、少し時間をとられました。
いまも、ミニマムアクセスという形で、輸入はしていると思います。では何に使っているのか、。。。どこから来ているのか。ちゃんとした統計を見たことはありません。そういえば。。。ちょうど、大学院の入試のころだったと。。その後、このミニマムアクセスに関して、問題が起きたのも思いだし。。。単純な図式でないことは、議論の中で、理解してもらえたのではと思います。何より、課題研究で、通過する電車の音をしっかり理解して、研究をしている方が、ESS部もやっていたとは。。。その当たりがびっくりでした。課題研究の論理性を遺憾なく発揮できれば、できるとおもいますので。がんばって下さい。
 昨年より、1ヶ月くらい早い時期ですので、さらにdataを整理して、渡辺にとっては難しい、英語での討論に備えて頂ければと思います。その時に、相手がどの様な戦略、戦術で来るのかに対応して、しっかりディベートしてもらえればと思います。遠く、仙台から、勝利を祈念していますので。。。
昨年より、1ヶ月くらい早い時期ですので、さらにdataを整理して、渡辺にとっては難しい、英語での討論に備えて頂ければと思います。その時に、相手がどの様な戦略、戦術で来るのかに対応して、しっかりディベートしてもらえればと思います。遠く、仙台から、勝利を祈念していますので。。。
わたなべしるす
PS. 週末にかけては、別の高校生からもmailで国際性、進路などについての質問も頂きました。あれで回答になっていたのか。。。気になるところではありますが。。。いつでもmailなどで質問をどうぞとしていることもあり、月に数回は、こうした質問が来ているのを記すのも失念しておりました。。。
では、今年のお題は、全部をそのまま書く訳にはいかないので。。。「外国産米の関税について。。」ということにしておきます。農学部出身ですし、大学院の入試で、農業経営学をとった位なので、ある程度のことはわかっているのですが。。。いざ、説明しようとすると。。。何より、輸入米の問題は関税以外の問題もたくさんあり。。その当たりの整理に、少し時間をとられました。
いまも、ミニマムアクセスという形で、輸入はしていると思います。では何に使っているのか、。。。どこから来ているのか。ちゃんとした統計を見たことはありません。そういえば。。。ちょうど、大学院の入試のころだったと。。その後、このミニマムアクセスに関して、問題が起きたのも思いだし。。。単純な図式でないことは、議論の中で、理解してもらえたのではと思います。何より、課題研究で、通過する電車の音をしっかり理解して、研究をしている方が、ESS部もやっていたとは。。。その当たりがびっくりでした。課題研究の論理性を遺憾なく発揮できれば、できるとおもいますので。がんばって下さい。
 昨年より、1ヶ月くらい早い時期ですので、さらにdataを整理して、渡辺にとっては難しい、英語での討論に備えて頂ければと思います。その時に、相手がどの様な戦略、戦術で来るのかに対応して、しっかりディベートしてもらえればと思います。遠く、仙台から、勝利を祈念していますので。。。
昨年より、1ヶ月くらい早い時期ですので、さらにdataを整理して、渡辺にとっては難しい、英語での討論に備えて頂ければと思います。その時に、相手がどの様な戦略、戦術で来るのかに対応して、しっかりディベートしてもらえればと思います。遠く、仙台から、勝利を祈念していますので。。。わたなべしるす
PS. 週末にかけては、別の高校生からもmailで国際性、進路などについての質問も頂きました。あれで回答になっていたのか。。。気になるところではありますが。。。いつでもmailなどで質問をどうぞとしていることもあり、月に数回は、こうした質問が来ているのを記すのも失念しておりました。。。