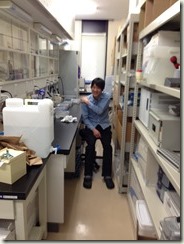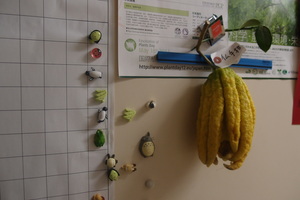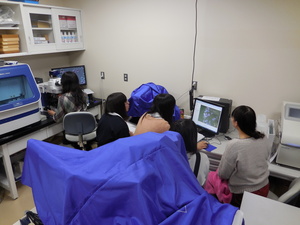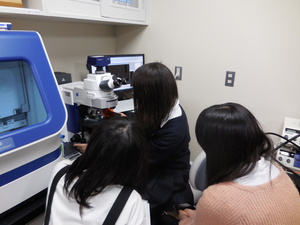大学で研究室に入った時、指導教官だった日向先生から「最近どうですか?」ということをあまり聞かなかったような気がする。日向先生自身がそういうことをあまり言われなかったのか。そんなことはないように思う。あの頃から、研究室での禁煙というのがはやりとなり、廊下で喫煙するという分煙制度ができつつあった。渡辺はタバコを吸わないのであるが、日向先生と議論するためには、廊下に出て、タバコを楽しんでいる時に捕まえで、こちらから、あの実験はという方が、よかったと思っていたのかもしれない。「攻撃は最大の防御」ということを感覚的に理解していたのかもしれない。あるいは、タバコを吸っている心が落ち着いた時に、話をした方がと思ったのかもしれない。日向先生が言われていた言葉に、「帰り際に何かを言われても、よい答えは出てこない。帰る気になって、system downしているので。脳みその。。。」といわれていた。たしか。。ただ、全く言わなかったわけではないはずで、日向先生が普段履いているサンダルと同じサンダルは禁止であった。足音の区別が極めて困難であるからであった。来た時には答えることができるように、先輩方は戦闘態勢にあったのかもしれない。というか、心の準備をしていたのだろう。たぶん。それでも、とある研究室の教授は、足音をさせないで、背後から「どうですか?」というのがあったというのをずいぶん聞いた。年明けからは、少しlabの中を歩いてみるようにしてみようかと。。。「どうですか?」と。。そんなことを書いた本を見つけたからと言うのもあって。。。
 そんな風に何をしているかというような情報を集めることも、教授の仕事である。そうしたことだけでなく、情報はどんなところにいても重要である。例えば、どの道を通るかによって、混雑具合もちがう。それも時間によって。そうしたちょっとしたことに気を遣うだけで、物事がスムーズになる。情報の大切さは、ここでもずいぶん書いてきたし、今月も、学部の1年生対象に講義をした。ただ、情報を集めるだけでなくて、それをいかに活用するのか、ということはそれ以上に大事である。手元に情報があってもそれを活用できなければ、持ってないのと同じである。テレビの情報によると、国立公文書館というようなところで働く人数が、アメリカと日本では、100:1くらいだったような。情報を集めて、管理して、その重要度を理解する。それは国としてもそうかもしれないが、研究室、ここの研究者にとってももちろん重要であり。。。昔に比べれば、どこに何が書いてあるのか、電子物化されたこともあってずいぶん楽になったのではないだろうか。昔であれば、どの論文のどこに何がというのを覚えていたような。。。もちろん、情報量も、今より少なかったことに起因するのかもしれないが。今日の文章にはどうもとりとめがない。。。情報が頭の中でうまく整理されてないからかもしれない。そういえば、土曜日。明日は日曜日。少し脳みそを休めて、来週からも残った今年の仕事を片付けて、新年を迎えたい。。。何とか、気合いと根性で。。。
そんな風に何をしているかというような情報を集めることも、教授の仕事である。そうしたことだけでなく、情報はどんなところにいても重要である。例えば、どの道を通るかによって、混雑具合もちがう。それも時間によって。そうしたちょっとしたことに気を遣うだけで、物事がスムーズになる。情報の大切さは、ここでもずいぶん書いてきたし、今月も、学部の1年生対象に講義をした。ただ、情報を集めるだけでなくて、それをいかに活用するのか、ということはそれ以上に大事である。手元に情報があってもそれを活用できなければ、持ってないのと同じである。テレビの情報によると、国立公文書館というようなところで働く人数が、アメリカと日本では、100:1くらいだったような。情報を集めて、管理して、その重要度を理解する。それは国としてもそうかもしれないが、研究室、ここの研究者にとってももちろん重要であり。。。昔に比べれば、どこに何が書いてあるのか、電子物化されたこともあってずいぶん楽になったのではないだろうか。昔であれば、どの論文のどこに何がというのを覚えていたような。。。もちろん、情報量も、今より少なかったことに起因するのかもしれないが。今日の文章にはどうもとりとめがない。。。情報が頭の中でうまく整理されてないからかもしれない。そういえば、土曜日。明日は日曜日。少し脳みそを休めて、来週からも残った今年の仕事を片付けて、新年を迎えたい。。。何とか、気合いと根性で。。。わたなべしるす
 PS. 今日も残っている年末年始の宿題中。出前講義の手紙に返事を書いていたら、この前のふるさと出前授業で、児童のお母さんが、小中学校の同級生。。。お父さんがという方も。。。びっくりです。。。というか、世の中は、とても狭いです。
PS. 今日も残っている年末年始の宿題中。出前講義の手紙に返事を書いていたら、この前のふるさと出前授業で、児童のお母さんが、小中学校の同級生。。。お父さんがという方も。。。びっくりです。。。というか、世の中は、とても狭いです。PS.のPS. 出前講義でお世話になっている浦和一女の菅野先生から昨日mailが。。。その中に卵の4期生が、「学生科学賞で文部科学大臣賞を受賞した」と。。みんな色々なところで活躍されているのだと。。。こちらも感動を頂きました。ありがとうございました。
PS.のPS.のPS. 東北大のtop pageにITER国際核融合エネルギー機構との学術交流協定締結というのを発見。昔は、こんなことをしたいと思った時期も。。。そんなことがつながって、プラズマを。。。ということなのかもしれないというか。。。写真をよく見たら、卵でお世話になっている工学部の安藤先生らしき方も映っているような。プラズマのtop runnerなので。。。来年はここに写真が載るようなbigなことを起こさないと。。。