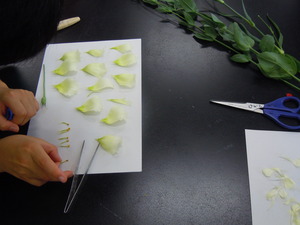地球全体がおかしい。としか思えないくらい、温暖化、異常気象が続いている。8月はあんなに暑かったのに、9月になるかならないかで、あり得ないくらい雨が降っている。西日本の方々は、とてもたいへんだと。。。100mmを越える雨というのは、。。。この前、古川の試験場で出会ったようなレベルではないのであろう。。。何より、観測を始めてから最高に暑かった夏というのが、今年のdataのようだ。その温暖化の関係で、病害虫が高緯度に拡大しているらしい。というのが、Nature Climate Changeに掲載されたというのを見た。。。。。。確かに、最初に仙台にきた頃から見たら、いないような害虫がいたり、少なくともvirusも増えているような気がする。。。それをちゃんとdataにするというのが、評価されるのであろう。もちろん、そうした害虫だけでなくて、スズメバチもかなり繁殖しているようだ。この夏は3匹ほど、研究室にも侵入して、駆除した。。。片平の木々の中に、巣があるとしたら本当は退治をしないと。。というくらい、地球レベルでおかしくなっている。という点では、鮨ネタのクロマグロも急激に減少しているという。海の中なので何が起きているのか見えないのが、問題である。昔に比べれば、マグロを食べることは増えた。その代わり、イワシ、サバなどは減ってきている。この間に何か見えない関係はないのだろうかと言っても、海の中なので、全部をどこかにひっくり返して、何が起きているかは、。。。何とか、その原因を突き止めることができないのだろうか。
 この異常気象に連動しているといえば、そうかもしれないが、寒気と暖気がぶつかって、竜巻が発生している。子供の頃に、かまいたちというか、小さな風が巻いているのくらいは見たことがあるが、北米大陸で観察されるような、そんなものが日本で。。。。どうも、なれないというか、違和感がある。。。といっても、地球温暖化が根本原因なら、何とかしないといけない。台風が沖縄近海で発生して、そこで発達するというのも、やっぱり違和感がある。普通は、もっと南の海で発生、発達というのが普通のような気がする。そんな異常気象に対して、植物の遺伝学をやっている立場からだと、少しでもCO2を固定する植物、作物を育成すればよいのだろうか。。。生殖をずっとやってきたものには、どうもイメージがわかない。違和感というほどではないが。。。そうしたことにも目を向けないといけない時間軸に入ったのかもしれない。
この異常気象に連動しているといえば、そうかもしれないが、寒気と暖気がぶつかって、竜巻が発生している。子供の頃に、かまいたちというか、小さな風が巻いているのくらいは見たことがあるが、北米大陸で観察されるような、そんなものが日本で。。。。どうも、なれないというか、違和感がある。。。といっても、地球温暖化が根本原因なら、何とかしないといけない。台風が沖縄近海で発生して、そこで発達するというのも、やっぱり違和感がある。普通は、もっと南の海で発生、発達というのが普通のような気がする。そんな異常気象に対して、植物の遺伝学をやっている立場からだと、少しでもCO2を固定する植物、作物を育成すればよいのだろうか。。。生殖をずっとやってきたものには、どうもイメージがわかない。違和感というほどではないが。。。そうしたことにも目を向けないといけない時間軸に入ったのかもしれない。
時間といえば、すでに9月に。。あっという間である。先日は、防災の日であったが、これといったことはしていない。それだからであろうか、今朝、9:18頃、震度2の地震が。。。。久しぶりであったが、震源は鳥島近海でM6.9。。。M7.0に近い。。。震源からの距離と搖れ方が比例関係にないのが、不思議な地震であった。。。やっぱり、マグロ、イワシでないが、海の中はよくわからない。。そういえば、9月。イネの季節も終わり、アブラナも本格化するシーズン。こちらは、科研費の申請のシーズン。異常気象・地震に負けることなく、これまで通り、アウトリーチ活動などを行い、普段の生活と平行して、これはという提案にしないと。。。。

わたなべしるす
PS. 昨日テレビを見ていたら、普段通う大学以外に、こんな大学にも通っているそうな。。実際の会社などでの経験の一部を積むようなことを。。。なるほどと、ということと、同じようなことを、SSHとか、科学者の卵とかでも、やっているなと。。高校でやるのか、大学でやるのか、もっと前なのか、。。その当たりは、考えないといけない時期なのかもしれない。。。。
 この異常気象に連動しているといえば、そうかもしれないが、寒気と暖気がぶつかって、竜巻が発生している。子供の頃に、かまいたちというか、小さな風が巻いているのくらいは見たことがあるが、北米大陸で観察されるような、そんなものが日本で。。。。どうも、なれないというか、違和感がある。。。といっても、地球温暖化が根本原因なら、何とかしないといけない。台風が沖縄近海で発生して、そこで発達するというのも、やっぱり違和感がある。普通は、もっと南の海で発生、発達というのが普通のような気がする。そんな異常気象に対して、植物の遺伝学をやっている立場からだと、少しでもCO2を固定する植物、作物を育成すればよいのだろうか。。。生殖をずっとやってきたものには、どうもイメージがわかない。違和感というほどではないが。。。そうしたことにも目を向けないといけない時間軸に入ったのかもしれない。
この異常気象に連動しているといえば、そうかもしれないが、寒気と暖気がぶつかって、竜巻が発生している。子供の頃に、かまいたちというか、小さな風が巻いているのくらいは見たことがあるが、北米大陸で観察されるような、そんなものが日本で。。。。どうも、なれないというか、違和感がある。。。といっても、地球温暖化が根本原因なら、何とかしないといけない。台風が沖縄近海で発生して、そこで発達するというのも、やっぱり違和感がある。普通は、もっと南の海で発生、発達というのが普通のような気がする。そんな異常気象に対して、植物の遺伝学をやっている立場からだと、少しでもCO2を固定する植物、作物を育成すればよいのだろうか。。。生殖をずっとやってきたものには、どうもイメージがわかない。違和感というほどではないが。。。そうしたことにも目を向けないといけない時間軸に入ったのかもしれない。時間といえば、すでに9月に。。あっという間である。先日は、防災の日であったが、これといったことはしていない。それだからであろうか、今朝、9:18頃、震度2の地震が。。。。久しぶりであったが、震源は鳥島近海でM6.9。。。M7.0に近い。。。震源からの距離と搖れ方が比例関係にないのが、不思議な地震であった。。。やっぱり、マグロ、イワシでないが、海の中はよくわからない。。そういえば、9月。イネの季節も終わり、アブラナも本格化するシーズン。こちらは、科研費の申請のシーズン。異常気象・地震に負けることなく、これまで通り、アウトリーチ活動などを行い、普段の生活と平行して、これはという提案にしないと。。。。

わたなべしるす
PS. 昨日テレビを見ていたら、普段通う大学以外に、こんな大学にも通っているそうな。。実際の会社などでの経験の一部を積むようなことを。。。なるほどと、ということと、同じようなことを、SSHとか、科学者の卵とかでも、やっているなと。。高校でやるのか、大学でやるのか、もっと前なのか、。。その当たりは、考えないといけない時期なのかもしれない。。。。