土曜日の岡山県に続いて、月曜日は香川県。SSH実施校で有り、運営指導委員を仰せつかっている、香川県立観音寺第一高等学校。6月に講義と運営指導委員会でおじゃましました。また、7月の岩手・盛岡での「アブラナコンソーシアム」への参加前の研究室訪問、そのあとの実験指導などでお会いして。その後も、mailと電話などで、栽培などについては、何度か議論したことがありました。今回、その栽培のことも含めて、アブラナ科植物についての講義をお願いされました。
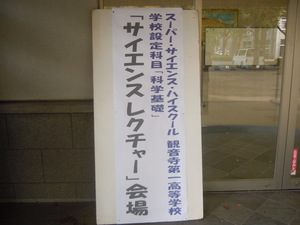 講義内容は、7月の「アブラナコンソーシアム」で話した内容ですが、Brassica属植物について、それぞれの種ごとの多様性、Brassica属植物以外のアブラナ科植物で見かけるもの。多様性という意味で、Brassica属で形の多様性でいえば、一番多様であろう、キャベツの仲間のBrassica oleraceaを題材にして、。また、この多様性は、ひとによる選抜、つまり、進化によるものであると。Domesticaionという単語といえば、そうかもしれないですが。。。
講義内容は、7月の「アブラナコンソーシアム」で話した内容ですが、Brassica属植物について、それぞれの種ごとの多様性、Brassica属植物以外のアブラナ科植物で見かけるもの。多様性という意味で、Brassica属で形の多様性でいえば、一番多様であろう、キャベツの仲間のBrassica oleraceaを題材にして、。また、この多様性は、ひとによる選抜、つまり、進化によるものであると。Domesticaionという単語といえば、そうかもしれないですが。。。

 他のBrassica属植物については、簡単に。このあと、自家不和合性の話をしたあとに、U's triangleのこと。最後のところは少し難しかったのかもしれないですが、なぜ、植物はこのように多様なゲノム構造になったのか、倍数性を受け入れるのかということは、これからの重要な研究テーマでもあることから、お話ししました。ぜひ、興味を持ってほしいと。。。最後は、いろいろな質問を直接もらったり、片付けながら、議論したり。何より、周りの自然から、観察をしてください。たくさんのキャベツ、ブロッコリーなどは、これから、おいしくなる時期ですから。
他のBrassica属植物については、簡単に。このあと、自家不和合性の話をしたあとに、U's triangleのこと。最後のところは少し難しかったのかもしれないですが、なぜ、植物はこのように多様なゲノム構造になったのか、倍数性を受け入れるのかということは、これからの重要な研究テーマでもあることから、お話ししました。ぜひ、興味を持ってほしいと。。。最後は、いろいろな質問を直接もらったり、片付けながら、議論したり。何より、周りの自然から、観察をしてください。たくさんのキャベツ、ブロッコリーなどは、これから、おいしくなる時期ですから。

 最後になりましたが、企画頂いた上原先生、石井先生、島田校長先生(今回は出張でお会いできませんでしたが。。。)、多田教頭先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。
最後になりましたが、企画頂いた上原先生、石井先生、島田校長先生(今回は出張でお会いできませんでしたが。。。)、多田教頭先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。
わたなべしるす
PS. 年度末の運営指導委員会が2/14ということをお願いされました。この時期、大学では、学位審査が。。。何とか都合をつけて、伺いたいと思います。昨年度は何とか都合がつきましたので、同じように。。
PS.のPS. 土曜日の金光学園のSSHの発表会で、観音寺第一の猪熊先生とお目にかかっていたのを記すのを失念しておりました。。。世の中、狭いなと。。。
PS.のPS.のPS. 今回の出前講義では、前回の6月の出前講義の時と同じく、今治南高の別府先生が、ほとんどの講義に同行され、ご自身の社会人入学されている大学院の研究のねたというか、dataというか、そのような形で、。。こちらはとても助かりました。ありがとうございました。
PS.のPS.のPS. のPS. JR四国には、「アンパンマン列車」というのが。。結構、かなり、カラフルな列車でした。
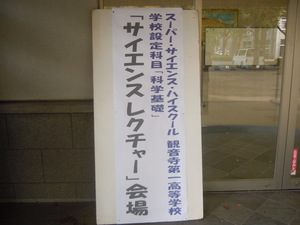 講義内容は、7月の「アブラナコンソーシアム」で話した内容ですが、Brassica属植物について、それぞれの種ごとの多様性、Brassica属植物以外のアブラナ科植物で見かけるもの。多様性という意味で、Brassica属で形の多様性でいえば、一番多様であろう、キャベツの仲間のBrassica oleraceaを題材にして、。また、この多様性は、ひとによる選抜、つまり、進化によるものであると。Domesticaionという単語といえば、そうかもしれないですが。。。
講義内容は、7月の「アブラナコンソーシアム」で話した内容ですが、Brassica属植物について、それぞれの種ごとの多様性、Brassica属植物以外のアブラナ科植物で見かけるもの。多様性という意味で、Brassica属で形の多様性でいえば、一番多様であろう、キャベツの仲間のBrassica oleraceaを題材にして、。また、この多様性は、ひとによる選抜、つまり、進化によるものであると。Domesticaionという単語といえば、そうかもしれないですが。。。
 他のBrassica属植物については、簡単に。このあと、自家不和合性の話をしたあとに、U's triangleのこと。最後のところは少し難しかったのかもしれないですが、なぜ、植物はこのように多様なゲノム構造になったのか、倍数性を受け入れるのかということは、これからの重要な研究テーマでもあることから、お話ししました。ぜひ、興味を持ってほしいと。。。最後は、いろいろな質問を直接もらったり、片付けながら、議論したり。何より、周りの自然から、観察をしてください。たくさんのキャベツ、ブロッコリーなどは、これから、おいしくなる時期ですから。
他のBrassica属植物については、簡単に。このあと、自家不和合性の話をしたあとに、U's triangleのこと。最後のところは少し難しかったのかもしれないですが、なぜ、植物はこのように多様なゲノム構造になったのか、倍数性を受け入れるのかということは、これからの重要な研究テーマでもあることから、お話ししました。ぜひ、興味を持ってほしいと。。。最後は、いろいろな質問を直接もらったり、片付けながら、議論したり。何より、周りの自然から、観察をしてください。たくさんのキャベツ、ブロッコリーなどは、これから、おいしくなる時期ですから。
 最後になりましたが、企画頂いた上原先生、石井先生、島田校長先生(今回は出張でお会いできませんでしたが。。。)、多田教頭先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。
最後になりましたが、企画頂いた上原先生、石井先生、島田校長先生(今回は出張でお会いできませんでしたが。。。)、多田教頭先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。わたなべしるす
PS. 年度末の運営指導委員会が2/14ということをお願いされました。この時期、大学では、学位審査が。。。何とか都合をつけて、伺いたいと思います。昨年度は何とか都合がつきましたので、同じように。。
PS.のPS. 土曜日の金光学園のSSHの発表会で、観音寺第一の猪熊先生とお目にかかっていたのを記すのを失念しておりました。。。世の中、狭いなと。。。
PS.のPS.のPS. 今回の出前講義では、前回の6月の出前講義の時と同じく、今治南高の別府先生が、ほとんどの講義に同行され、ご自身の社会人入学されている大学院の研究のねたというか、dataというか、そのような形で、。。こちらはとても助かりました。ありがとうございました。
PS.のPS.のPS. のPS. JR四国には、「アンパンマン列車」というのが。。結構、かなり、カラフルな列車でした。






-thumb-300x225-4150.jpg)
-thumb-300x225-4154.jpg)
-thumb-300x225-4152.jpg)




-thumb-300x225-4127.jpg)


-thumb-300x225-4138.jpg)


-thumb-300x225-4114.jpg)
-thumb-300x225-4116.jpg)