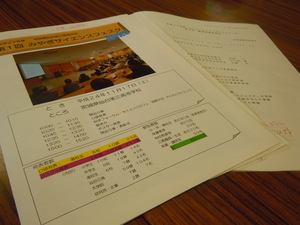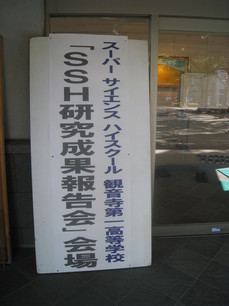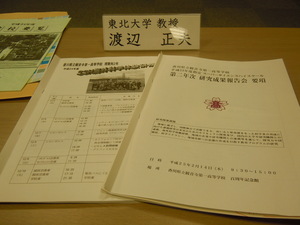昨日は仙台三。それなりに寒いと思っていましたが、盛岡の今朝の最低気温は、-8.9oCとか。。。8年ほど前まで、盛岡にいたのが影響したのか、思ったほどではなく、空気が痛いというイメージはなくてほっとでした。
盛岡三のSSH発表会は、今年度拝見した、鹿児島・錦江湾高校、石川・小松高校、香川・観音寺一と異なり、ディベートの全校大会があり、その決勝が当日の午前のmain event。論題は「日本国は理系教育を拡大すべきである。是か否か。」開始前半は、エネルギー問題についての1年生の発表を見ていて、最初から見ることができませんでしたが、「倫理面」、「新エネルギー」、「自然破壊」などをkey wordにして、論を戦わせていました。高校生なのでということはあるかもしれないですが、ディベートの先進国というか、欧米であれば、相手のミスを徹底的に突いて、勝ちを導くと言うことだと思うのですが、そこまで、徹底していなかったのは、少し残念でした。また、高校生らしいと言うのは、最初に、「お願いします。」から始まっているのは、ちょうど、高校野球の最初の挨拶。確かに、教育的にはそうかもしれないですが、これから、雌雄を決するという場面であれば、そうした配慮もなしで、相手を論破する論理力の要請があってもよかったのではと思いました。
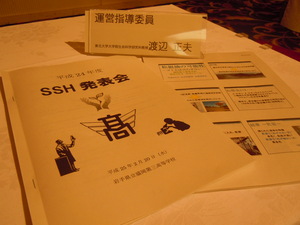 課題研究の発表では、日本語、英語でのプレゼンがあり、多様性もあり、興味深いものでした。津波で生じた沿岸部の松から「松根油」の実験というのは、時代を反映しているのだなと。課題研究の発表の途中で、「エコノミー症候群」防止のために、ストレッチということで、野球部が乱入。ストレッチを指揮したというのは、これまでの発表会で初めてのことで、おもしろい試みでした。昼食時には、関係の先生方と、今後のことと言うことで、「論理性」、「思考力」、「疑問に思うこと」、「国際性」について、今後の発展を含めて議論できたことは、何よりでした。発表会の講評では、「考える力」、「責任」、「質問力」等の重要性についても。
課題研究の発表では、日本語、英語でのプレゼンがあり、多様性もあり、興味深いものでした。津波で生じた沿岸部の松から「松根油」の実験というのは、時代を反映しているのだなと。課題研究の発表の途中で、「エコノミー症候群」防止のために、ストレッチということで、野球部が乱入。ストレッチを指揮したというのは、これまでの発表会で初めてのことで、おもしろい試みでした。昼食時には、関係の先生方と、今後のことと言うことで、「論理性」、「思考力」、「疑問に思うこと」、「国際性」について、今後の発展を含めて議論できたことは、何よりでした。発表会の講評では、「考える力」、「責任」、「質問力」等の重要性についても。
運営指導委員会では、7クラスで5クラスが理系志望とか。また、生物・化学志望より、物理・化学志望が増えているとか。自分が高校の時には、生物を履修したら、行くところが限定されるので、物理志望がほとんどだったのが、いつの間にか、生物志望も多くなって、また、時代が戻っているのかなと。論理的に考えるという「物理」が見直されたというか、そのようになりつつあるのは、よいことなのでは。生物・植物・遺伝学を研究していても、物理的基礎があることは、発展性を考えた時、大事だと思いますので。今後の発展のために、「文章力」、「構成力」、「国際性」、「空間把握能力」、「想像力」、「生活力」ということがkey wordsとして。。次年度が中間年。さらなる発展を祈念しております。もちろん、次年度も、運営指導委員は、承りますので。
最後になりましたが、校長先生をはじめとする関係の先生方、岩手県教育委員会の方々に、この場を借りてお礼申し上げます。

わたなべしるす
PS. 発表会には、他の高校の先生方もいらしていましたが、先週の観音寺一の時に、浦和一女の伊藤先生とお会いしました。今回は、浦和に伺ったときにお世話になっている生物の菅野先生でした。SSHの取組でも珍しい「ディベート」への着目だったそうです。なるほどと。。次年度は、浦和一女に講義に伺えればと思いました。
盛岡三のSSH発表会は、今年度拝見した、鹿児島・錦江湾高校、石川・小松高校、香川・観音寺一と異なり、ディベートの全校大会があり、その決勝が当日の午前のmain event。論題は「日本国は理系教育を拡大すべきである。是か否か。」開始前半は、エネルギー問題についての1年生の発表を見ていて、最初から見ることができませんでしたが、「倫理面」、「新エネルギー」、「自然破壊」などをkey wordにして、論を戦わせていました。高校生なのでということはあるかもしれないですが、ディベートの先進国というか、欧米であれば、相手のミスを徹底的に突いて、勝ちを導くと言うことだと思うのですが、そこまで、徹底していなかったのは、少し残念でした。また、高校生らしいと言うのは、最初に、「お願いします。」から始まっているのは、ちょうど、高校野球の最初の挨拶。確かに、教育的にはそうかもしれないですが、これから、雌雄を決するという場面であれば、そうした配慮もなしで、相手を論破する論理力の要請があってもよかったのではと思いました。
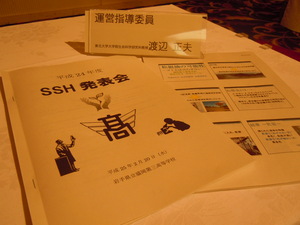 課題研究の発表では、日本語、英語でのプレゼンがあり、多様性もあり、興味深いものでした。津波で生じた沿岸部の松から「松根油」の実験というのは、時代を反映しているのだなと。課題研究の発表の途中で、「エコノミー症候群」防止のために、ストレッチということで、野球部が乱入。ストレッチを指揮したというのは、これまでの発表会で初めてのことで、おもしろい試みでした。昼食時には、関係の先生方と、今後のことと言うことで、「論理性」、「思考力」、「疑問に思うこと」、「国際性」について、今後の発展を含めて議論できたことは、何よりでした。発表会の講評では、「考える力」、「責任」、「質問力」等の重要性についても。
課題研究の発表では、日本語、英語でのプレゼンがあり、多様性もあり、興味深いものでした。津波で生じた沿岸部の松から「松根油」の実験というのは、時代を反映しているのだなと。課題研究の発表の途中で、「エコノミー症候群」防止のために、ストレッチということで、野球部が乱入。ストレッチを指揮したというのは、これまでの発表会で初めてのことで、おもしろい試みでした。昼食時には、関係の先生方と、今後のことと言うことで、「論理性」、「思考力」、「疑問に思うこと」、「国際性」について、今後の発展を含めて議論できたことは、何よりでした。発表会の講評では、「考える力」、「責任」、「質問力」等の重要性についても。運営指導委員会では、7クラスで5クラスが理系志望とか。また、生物・化学志望より、物理・化学志望が増えているとか。自分が高校の時には、生物を履修したら、行くところが限定されるので、物理志望がほとんどだったのが、いつの間にか、生物志望も多くなって、また、時代が戻っているのかなと。論理的に考えるという「物理」が見直されたというか、そのようになりつつあるのは、よいことなのでは。生物・植物・遺伝学を研究していても、物理的基礎があることは、発展性を考えた時、大事だと思いますので。今後の発展のために、「文章力」、「構成力」、「国際性」、「空間把握能力」、「想像力」、「生活力」ということがkey wordsとして。。次年度が中間年。さらなる発展を祈念しております。もちろん、次年度も、運営指導委員は、承りますので。
最後になりましたが、校長先生をはじめとする関係の先生方、岩手県教育委員会の方々に、この場を借りてお礼申し上げます。

わたなべしるす
PS. 発表会には、他の高校の先生方もいらしていましたが、先週の観音寺一の時に、浦和一女の伊藤先生とお会いしました。今回は、浦和に伺ったときにお世話になっている生物の菅野先生でした。SSHの取組でも珍しい「ディベート」への着目だったそうです。なるほどと。。次年度は、浦和一女に講義に伺えればと思いました。