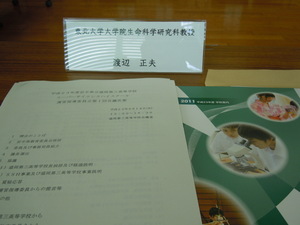科学者の卵養成講座の全国大会に東北大からも参加し、北海道から九州に至る、13の大学での日頃の研究成果の発表会でした。研究内容は、理数の広範なものであり、その多様性も興味深い点でした。発表会に先立ち、日本の液晶、超伝導などの物性科学をリードし、FIRSTのプログラムの代表もされている東工大・細野教授の特別講演があり、科学のアウトプットという点の重要性、try and errorもがんばることなど、受講生には、新しい刺激だったのではと思います。
 初日の東北大からの発表は、早坂・田中さんチームの「ハイブリッドマイクロカプセル・・・」というものでした。2名のプレゼンの呼吸もよく合っており、さすがと思わせるものでした。プレゼンの最後には、この実験系が放射性Csの吸着にも応用できる可能性を話し、今のtopicにあうものでした。多くの質問に対して、的確に応対し、これが発展コース、プレゼン会議があった効果であろうと、実感できました。また、プレゼン会議の時より、内容がversion upしてあったのも、受験生というのに、さすがと。。
初日の東北大からの発表は、早坂・田中さんチームの「ハイブリッドマイクロカプセル・・・」というものでした。2名のプレゼンの呼吸もよく合っており、さすがと思わせるものでした。プレゼンの最後には、この実験系が放射性Csの吸着にも応用できる可能性を話し、今のtopicにあうものでした。多くの質問に対して、的確に応対し、これが発展コース、プレゼン会議があった効果であろうと、実感できました。また、プレゼン会議の時より、内容がversion upしてあったのも、受験生というのに、さすがと。。
 なにより、すばらしかったのは、昨年と同様に、他の養成講座のプレゼンに的確な質問を多くの方々がしてくれて、場を盛り上げてくれたのは、とてもすばらしいことだと思いました。これも「科学者の卵」で培った能力が現れたものだと思っております。明日以降もぜひ、がんばって盛り上げてほしいと思いました。
なにより、すばらしかったのは、昨年と同様に、他の養成講座のプレゼンに的確な質問を多くの方々がしてくれて、場を盛り上げてくれたのは、とてもすばらしいことだと思いました。これも「科学者の卵」で培った能力が現れたものだと思っております。明日以降もぜひ、がんばって盛り上げてほしいと思いました。
夕食後にも交流会があり、国際学会並みのactivityでさすが高校生。1日目は、福井大学の前田先生がorganizeされている「自分の分野で尊敬できる研究者」ということで、参加された先生方から、様々な分野の偉人が紹介され、そのあと、その偉人についてdeepな議論を行いました。ちなみに、渡辺が紹介したのは、「C. Darwin」, 「G. Mendel」、ここまでは遺伝学者として、有名でしょう。いうまでもありません。では、「禹長春」は、植物育種、遺伝学では有名なU's triangle (禹の三角形)という、白菜(Brassica rapa)、キャベツ(B. oleracea)、西洋ナタネ(B. napus)、タカナ(B. juncea)
、クロガラシ(B. nigra)、B. carinataの関係を明らかにした方。お弟子さんには、渡辺の研究室の祖先の方とも言える水島宇三郎先生。もうひとりは、「浜口梧陵」。彼は、遺伝学とは関係ない、和歌山の方。昔は、「稲むらの火」という、教科書にも出ていた大地震の後に、村人を津波から救ったひとのモデルとなったひと。有名な言葉に、「万が一の時になって、思いをめぐらすのではなく、常日頃から非常の事態に備え、一生懸命にわが身を生かす心構えを養うべきである。」という言葉を残し、今、よく言われている「想定外」を戒めているひと。もちろん、実験で想定外のことが起こり、それを意味のあることと気がつくのは大事な想定外ですが。。。
 明日も東北大の発表は午前、午後とあり、夕食後の交流会は、渡辺がorganizeです。続きはまた明日ということで。
明日も東北大の発表は午前、午後とあり、夕食後の交流会は、渡辺がorganizeです。続きはまた明日ということで。
わたなべしるす
PS. 最初の集合写真に、浦和第一女子の2名がいないのは、あとから現地集合だったためです。すみません。。。
そういえば、今日は、M6クラスの地震が朝から、3回ほど。。11日前後に起きるのが、少し遅くなったのでしょうか。朝から、起こされました。。。。
 初日の東北大からの発表は、早坂・田中さんチームの「ハイブリッドマイクロカプセル・・・」というものでした。2名のプレゼンの呼吸もよく合っており、さすがと思わせるものでした。プレゼンの最後には、この実験系が放射性Csの吸着にも応用できる可能性を話し、今のtopicにあうものでした。多くの質問に対して、的確に応対し、これが発展コース、プレゼン会議があった効果であろうと、実感できました。また、プレゼン会議の時より、内容がversion upしてあったのも、受験生というのに、さすがと。。
初日の東北大からの発表は、早坂・田中さんチームの「ハイブリッドマイクロカプセル・・・」というものでした。2名のプレゼンの呼吸もよく合っており、さすがと思わせるものでした。プレゼンの最後には、この実験系が放射性Csの吸着にも応用できる可能性を話し、今のtopicにあうものでした。多くの質問に対して、的確に応対し、これが発展コース、プレゼン会議があった効果であろうと、実感できました。また、プレゼン会議の時より、内容がversion upしてあったのも、受験生というのに、さすがと。。 なにより、すばらしかったのは、昨年と同様に、他の養成講座のプレゼンに的確な質問を多くの方々がしてくれて、場を盛り上げてくれたのは、とてもすばらしいことだと思いました。これも「科学者の卵」で培った能力が現れたものだと思っております。明日以降もぜひ、がんばって盛り上げてほしいと思いました。
なにより、すばらしかったのは、昨年と同様に、他の養成講座のプレゼンに的確な質問を多くの方々がしてくれて、場を盛り上げてくれたのは、とてもすばらしいことだと思いました。これも「科学者の卵」で培った能力が現れたものだと思っております。明日以降もぜひ、がんばって盛り上げてほしいと思いました。夕食後にも交流会があり、国際学会並みのactivityでさすが高校生。1日目は、福井大学の前田先生がorganizeされている「自分の分野で尊敬できる研究者」ということで、参加された先生方から、様々な分野の偉人が紹介され、そのあと、その偉人についてdeepな議論を行いました。ちなみに、渡辺が紹介したのは、「C. Darwin」, 「G. Mendel」、ここまでは遺伝学者として、有名でしょう。いうまでもありません。では、「禹長春」は、植物育種、遺伝学では有名なU's triangle (禹の三角形)という、白菜(Brassica rapa)、キャベツ(B. oleracea)、西洋ナタネ(B. napus)、タカナ(B. juncea)
、クロガラシ(B. nigra)、B. carinataの関係を明らかにした方。お弟子さんには、渡辺の研究室の祖先の方とも言える水島宇三郎先生。もうひとりは、「浜口梧陵」。彼は、遺伝学とは関係ない、和歌山の方。昔は、「稲むらの火」という、教科書にも出ていた大地震の後に、村人を津波から救ったひとのモデルとなったひと。有名な言葉に、「万が一の時になって、思いをめぐらすのではなく、常日頃から非常の事態に備え、一生懸命にわが身を生かす心構えを養うべきである。」という言葉を残し、今、よく言われている「想定外」を戒めているひと。もちろん、実験で想定外のことが起こり、それを意味のあることと気がつくのは大事な想定外ですが。。。
 明日も東北大の発表は午前、午後とあり、夕食後の交流会は、渡辺がorganizeです。続きはまた明日ということで。
明日も東北大の発表は午前、午後とあり、夕食後の交流会は、渡辺がorganizeです。続きはまた明日ということで。わたなべしるす
PS. 最初の集合写真に、浦和第一女子の2名がいないのは、あとから現地集合だったためです。すみません。。。
そういえば、今日は、M6クラスの地震が朝から、3回ほど。。11日前後に起きるのが、少し遅くなったのでしょうか。朝から、起こされました。。。。