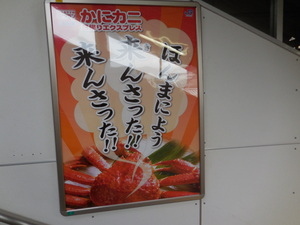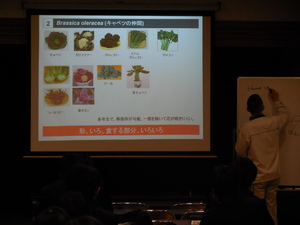技術補佐員の伊藤です。
一気に過ぎ去る仙台の秋。
綺麗に紅葉した銀杏の木を撮影しようと思っていたら、
昨日の風で綺麗なじゅうたんに早変わりしていました。

秋が過ぎ去らぬうちに(もう過ぎ去ったのかな?)
秋らしい話題をいくつか。
芸術の秋
先日、子供たちの通う小学校で学芸会が開かれました。
元気いっぱい、可愛い1年生の劇を楽しみ、
6年生の合奏・合唱に成長を感じ、涙してきました。
朝早くから練習して、放課後に大道具の準備をして。
みんなの頑張りで素敵なひとときを過ごす事が出来ました。
運動の秋
明日は小学校の持久走大会。
低、中,高学年に分かれて学校周辺を走ります。
今年初参加の娘は、「道を間違えないか不安。」と。
先頭を走るわけではないから、、、いらぬ心配です。
母は、、、警備要員として道路に立って見守ります。
子供たちが1、3、6年生に在籍するため、朝から
立ちっぱなしです。
子供たちの為にも、母の為にも、暖かい一日である事を願っています。
食欲の秋
娘がサツマイモを収穫してきました。
サツマイモはすぐに食べるより、少し乾燥させた方が
甘みが増すというので、ベランダに並べてみました。
天ぷらにするか?大学芋にするか?
あ~、楽しみ。

ここまで書いて、全て子供の話題である事に気づく!
季節感を与えてくれている子供たちに感謝しつつ、
冬支度に入る母です。
いとう