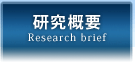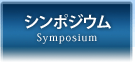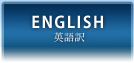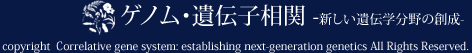文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」
新学術領域|ゲノム・遺伝子相関
月別アーカイブ
計画研究班別アーカイブ
公募研究班別アーカイブ
旧公募研究班別アーカイブ
「研究経過報告」内を検索
【東京工大】田中班の記事を表示しています
2012年11月26日(月)、田中は宮城県教育委員会企画外部講師活用事業が支援する講演会の講師として、宮城第一高等学校を訪れ、理数科クラスの1 年生 80 名を対象に、2 時間 30 分にわたり「対鰭の獲得と四肢への進化」と題して講演を行った。脊椎動物が胸鰭や腹鰭を獲得し、さらに鰭を手足へと進化させたプロセスを明らかにするために行っている研究の成果について講演した後、大学での研究生活や学生による国内外の学会での発表の様子などを紹介した。
2012年11月14日から18日に名古屋大学で行われた 7th Internatnional Chick Meeting : Avian Model Systems にて、シンポジウム "Birds and Evolution" が開催されました。
オーガナイザー: Cheng-Ming Chuong (University of Southern California), Mikiko Tanaka (Tokyo Tech)
S-2-1 Feather as a model for organ regeneration and Evo-Devo study
Cheng-Ming Choung (University of Southern California, USA)
S-2-2 Evolution of feathers and wing digits: Paleontological evidence
Xing Xu (Chinese Academy of Sciences, China)
S-2-3 Developmental and evolutionary aspects of avian-specific traits in limb skeletal pattern
Koji Tamura (Tohoku University, Japan)
S-2-4 The Origin and Development of the Sternum: Examining the Role of Tbx5 in Mammalian and Avian Sternum Formation
Sorrel Bickley (National Institute of Medical Research, UK)
S-2-5 Neocortical neurogenesis is not really "neo" :a new evolutionary model derived from a comparative study of the chick pallial development
Ikuo K Suzuki (ULB, Belgium)
S-2-6 Evolution and development of limbs
Mikiko Tanaka (Tokyo Institute of Technology, Japan)
脊椎動物の手足の起源については、古くから古生物学者や発生生物学者によって研究がされてきました。手足は原始的な魚の対になった鰭が進化したものです。化石の記録などからは、顎を獲得する前の原始的脊椎動物(無顎類)の祖先で対になった鰭が出現したとされています。しかしながら、現存する無顎類であるヤツメウナギやメクラウナギは対になった鰭を持たないために、脊椎動物の祖先がどういった発生プログラムの変化を経て対になった鰭を獲得したかはわかりませんでした。
しかし、近年になって、現存する様々な原始的脊索動物や脊椎動物の体壁をつくる側板中胚葉(Lateral plate mesoderm)の発生メカニズムを調べることで、脊椎動物の祖先が体壁に対になった鰭を獲得するまでの軌跡の一部が明らかになってきました。本総説では、この分野における近年の研究成果を紹介し、手足の起源について議論しています。
Acquisition of the paired fins: a view from the sequential evolution of the lateral plate mesoderm.
Evolution & Development 誌
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1525-142X.2012.00561.x/full
Article first published online: 5 SEP 2012
DOI:10.1111/j.1525-142X.2012.00561.x
2012年8月21日から24日に首都大学東京で行われた日本進化学会第14回東京大会にて、シンポジウム「脊椎動物の形態進化ー発生学、古生物学、形態学の視点からー」が開催されました。
オーガナイザー:田中幹子(東工大)、和田洋(筑波大)
趣旨:
脊椎動物の形態変化の歴史を理解する試みの一貫としては、古生物学•形態学的知見に合わせて、発生生物学的アプローチからも、近年大きな成果が得られている。本シンポジウムでは、四肢や歩行の進化、頭部筋肉の進化、そしてカメの甲羅の獲得といった、脊椎動物の形態進化の3つのトピックスを取り上げる。それぞれについて、発生生物学と古生物学•形態学の立場からの演者を招き、形態進化のより深淵な問題の解決への糸口を探る。
四肢•歩行の進化
1. 「恐竜発生学のすすめ」
田村宏治(東北大•生命)
2. 「ワニと鳥類の祖先(主竜類)における、直立姿勢と二足歩行の進化」
久保泰(福井県立恐竜博物館)
頭部筋肉の進化
3. 「脊椎動物頭部筋肉の進化と頭部分節性問題」
足立礼考(理研•発生再生)
4.「齧歯類における咬筋構造と顎運動の多様性」
佐藤和彦(朝日大•歯)
カメの進化
5. 「最古のカメは語る」
平山廉(早稲田大•国際学術)
6. 「カメの起源:胚発生、ゲノム、そして化石の示す進化シナリオ」
倉谷滋(理研•発生再生)

- 1
- 2