きのうは、福島高校のコアSSHの来年度の企画打合せ。今日からは、鹿児島・錦江湾高校のコアSSH。錦江湾高校はダイコンコンソーシアムに始まり、コアSSHの地域中核拠点形成に移行して、今年が5年目。やっぱり暑いです。地球温暖化の影響というか、この夏の特徴というか。温暖化の影響で、リンゴが甘くなるという新聞記事を今朝見かけました。温暖化だと農作物の栽培適地が北にずれるという余りよくないことはありましたが、こうしたpositiveなこともあるのだなと。。。(PS. 夕方に、NatureのHPを見た時に、このことが記事になっていました。原著はdownload freeで、なるほどというものでした。)
 地域中核拠点形成は、3年プログラムの2年目。ダイコンコンソーシアムで蓄えた研究力、地域発信力を他の教科への展開という横串を目指す年度。これまで以上に研究などがheteroになり、ダイコン研究が物理、化学分野との融合。また、物理、化学、地学の研究もずいぶん増加して、地域中核拠点となってきたのだと思っています。また、地域の科学力強化に向けて、高校生が小中学校へ出前講義等を行う形態で、小中高大連携を目指すという形に発展していると思っています。また、ダイコンコンソーシアムから参画している遠隔地の鹿児島県外の高校がさらに、その地域の中核拠点を目指すという形態は、この錦江湾高校のコアSSHの特徴ではないかと。というか、発展がさらに楽しみになってきました。参加校などは、また、明日からの発表会でお話ししますが、少し入れ替えはあったものの新しい地域の補強もあり、異分野融合など、少しずつ深化していくのではと。。。。
地域中核拠点形成は、3年プログラムの2年目。ダイコンコンソーシアムで蓄えた研究力、地域発信力を他の教科への展開という横串を目指す年度。これまで以上に研究などがheteroになり、ダイコン研究が物理、化学分野との融合。また、物理、化学、地学の研究もずいぶん増加して、地域中核拠点となってきたのだと思っています。また、地域の科学力強化に向けて、高校生が小中学校へ出前講義等を行う形態で、小中高大連携を目指すという形に発展していると思っています。また、ダイコンコンソーシアムから参画している遠隔地の鹿児島県外の高校がさらに、その地域の中核拠点を目指すという形態は、この錦江湾高校のコアSSHの特徴ではないかと。というか、発展がさらに楽しみになってきました。参加校などは、また、明日からの発表会でお話ししますが、少し入れ替えはあったものの新しい地域の補強もあり、異分野融合など、少しずつ深化していくのではと。。。。
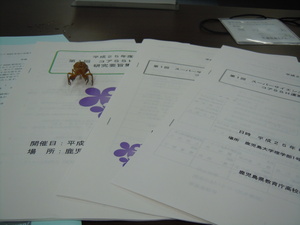 さらなる発展性ということで、県内の学校との連携、HPからの発信力、農業高校、工業高校という、普通科よりも長い課題研究歴のある高校の参画などが取り上げられ、今年度もより、深化・進化があるのではと思います。特に、HPからの情報発信は文章力の強化にもつながるということもありますので、ぜひ、より多くの高校から、情報発信されるのを楽しみにしています。
さらなる発展性ということで、県内の学校との連携、HPからの発信力、農業高校、工業高校という、普通科よりも長い課題研究歴のある高校の参画などが取り上げられ、今年度もより、深化・進化があるのではと思います。特に、HPからの情報発信は文章力の強化にもつながるということもありますので、ぜひ、より多くの高校から、情報発信されるのを楽しみにしています。
最後になりますが、今回の会議をorganize頂きました、鹿児島県立錦江湾高校・郡山先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。
 わたなべしるす
わたなべしるす
PS. そういえば、大学の掲示に、クミアイ化学工業株式会社・第2回学生懸賞論文募集というのを見つけました。テーマは、日本の農業に若者の息吹を!--農業の未来を考える--、というのがあったのを忘れていました。クミアイ化学工業の農薬はいくつかアブラナの栽培の時にお世話になっていましたが、こうした社会活動というか、こんなこともしているのだなと。。。応募要件が、大学生・大学院となっているので、。。。学生の頃、愛媛に帰るたびに、農業をしている方々が高齢化しているのを見ていて、どうなるのか、どうしたらよいのかなど、農学科の懇親会で農業経営の酒井教授などと議論をしたのを思い出しました。SSHの中で農業高校の話題が出たので、脳みその片隅にあったのを思い出しました。HPを見ていてくれている、大学生・大学院生の方、トライしてみてはいかがでしょうか。長い文章を書くというのも、よいトレーニングになると思いますし、懸賞もあるそうですので。。。何あれ、表彰されるというのはよいことですので。。。
PS.のPS. こちらが記事をあげてすぐでしょうか、この3月に卒業された前田君と山村さんがイネのサンプリングに来てくれ、記事も書いてくれていました。ありがとうございました。こちらが出張でお目にかかれなかったのが残念でした。また、研究室にいらしてください。
 地域中核拠点形成は、3年プログラムの2年目。ダイコンコンソーシアムで蓄えた研究力、地域発信力を他の教科への展開という横串を目指す年度。これまで以上に研究などがheteroになり、ダイコン研究が物理、化学分野との融合。また、物理、化学、地学の研究もずいぶん増加して、地域中核拠点となってきたのだと思っています。また、地域の科学力強化に向けて、高校生が小中学校へ出前講義等を行う形態で、小中高大連携を目指すという形に発展していると思っています。また、ダイコンコンソーシアムから参画している遠隔地の鹿児島県外の高校がさらに、その地域の中核拠点を目指すという形態は、この錦江湾高校のコアSSHの特徴ではないかと。というか、発展がさらに楽しみになってきました。参加校などは、また、明日からの発表会でお話ししますが、少し入れ替えはあったものの新しい地域の補強もあり、異分野融合など、少しずつ深化していくのではと。。。。
地域中核拠点形成は、3年プログラムの2年目。ダイコンコンソーシアムで蓄えた研究力、地域発信力を他の教科への展開という横串を目指す年度。これまで以上に研究などがheteroになり、ダイコン研究が物理、化学分野との融合。また、物理、化学、地学の研究もずいぶん増加して、地域中核拠点となってきたのだと思っています。また、地域の科学力強化に向けて、高校生が小中学校へ出前講義等を行う形態で、小中高大連携を目指すという形に発展していると思っています。また、ダイコンコンソーシアムから参画している遠隔地の鹿児島県外の高校がさらに、その地域の中核拠点を目指すという形態は、この錦江湾高校のコアSSHの特徴ではないかと。というか、発展がさらに楽しみになってきました。参加校などは、また、明日からの発表会でお話ししますが、少し入れ替えはあったものの新しい地域の補強もあり、異分野融合など、少しずつ深化していくのではと。。。。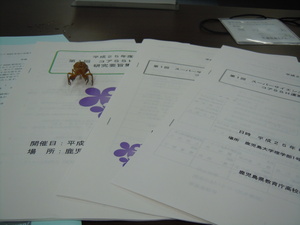 さらなる発展性ということで、県内の学校との連携、HPからの発信力、農業高校、工業高校という、普通科よりも長い課題研究歴のある高校の参画などが取り上げられ、今年度もより、深化・進化があるのではと思います。特に、HPからの情報発信は文章力の強化にもつながるということもありますので、ぜひ、より多くの高校から、情報発信されるのを楽しみにしています。
さらなる発展性ということで、県内の学校との連携、HPからの発信力、農業高校、工業高校という、普通科よりも長い課題研究歴のある高校の参画などが取り上げられ、今年度もより、深化・進化があるのではと思います。特に、HPからの情報発信は文章力の強化にもつながるということもありますので、ぜひ、より多くの高校から、情報発信されるのを楽しみにしています。最後になりますが、今回の会議をorganize頂きました、鹿児島県立錦江湾高校・郡山先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。
 わたなべしるす
わたなべしるすPS. そういえば、大学の掲示に、クミアイ化学工業株式会社・第2回学生懸賞論文募集というのを見つけました。テーマは、日本の農業に若者の息吹を!--農業の未来を考える--、というのがあったのを忘れていました。クミアイ化学工業の農薬はいくつかアブラナの栽培の時にお世話になっていましたが、こうした社会活動というか、こんなこともしているのだなと。。。応募要件が、大学生・大学院となっているので、。。。学生の頃、愛媛に帰るたびに、農業をしている方々が高齢化しているのを見ていて、どうなるのか、どうしたらよいのかなど、農学科の懇親会で農業経営の酒井教授などと議論をしたのを思い出しました。SSHの中で農業高校の話題が出たので、脳みその片隅にあったのを思い出しました。HPを見ていてくれている、大学生・大学院生の方、トライしてみてはいかがでしょうか。長い文章を書くというのも、よいトレーニングになると思いますし、懸賞もあるそうですので。。。何あれ、表彰されるというのはよいことですので。。。
PS.のPS. こちらが記事をあげてすぐでしょうか、この3月に卒業された前田君と山村さんがイネのサンプリングに来てくれ、記事も書いてくれていました。ありがとうございました。こちらが出張でお目にかかれなかったのが残念でした。また、研究室にいらしてください。







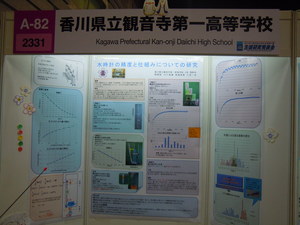
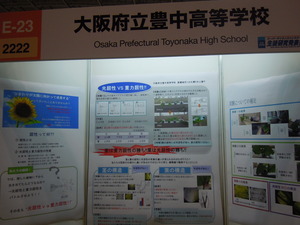


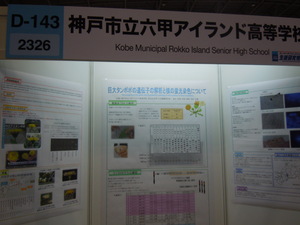
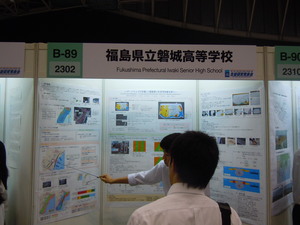


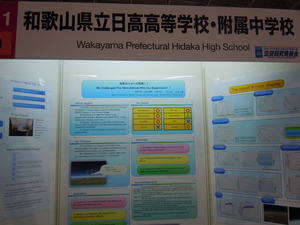
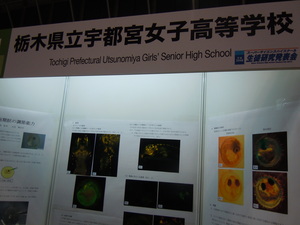

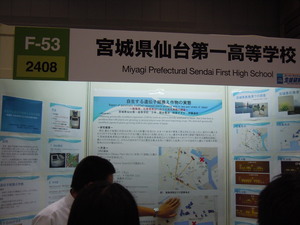
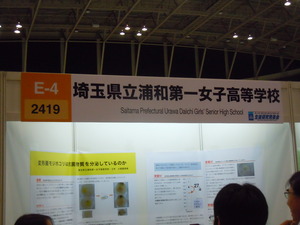



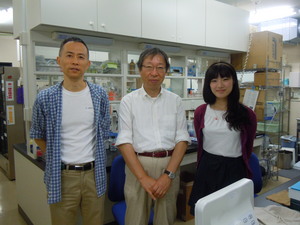

-%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%B4%99-thumb-250x355-6414.jpg)





