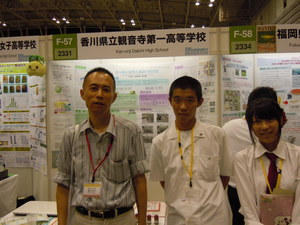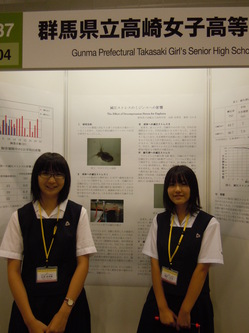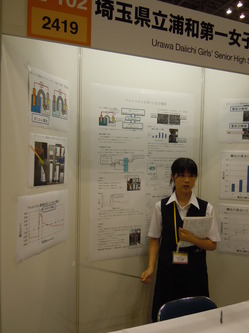昨年度までの3年間、コアSSHのコンソーシアム型の研究であった「ダイコンコンソーシアム」。今年度からは地域中核拠点形成へ。ダイコンコンソーシアムで培ったものを、他の教科、科目に広げるという興味深いものです。タイトルもずいぶん長いのですが、「課題研究支援ネットワークと教育資源活用プログラムによる中核拠点形成--ダイコンコンソーシアムを発展させた鹿児島モデルの推進--」。これまでの高校生の課題研究に加えて、小中高大連携という縦のつながりと、教科、科目を超えての横への広がりを持たせた、興味深いものに発展したというべきなのかもしれません。地域中核拠点形成ということで、これからの3年間、どのように発展させるのか、運営指導委員として、これまで以上にサポート出来ればと思います。(HPが、まだ以前のままですが、ダイコンだけでなく、様々な研究発表がされています。)
 2日間に亘って、今年度の研究計画討論会などが行われ、研究の方向性、実験方法などについて、20弱の高校の研究を議論しました。ダイコンだけが研究対象でなく、物理・天文分野として、5月の金環食の観測、その他の分野では、ゼニゴケ、マングローブ、プランクトン、ミヤマクワガタ(ミヤマクワガタは、子供の頃からとろうと思ってもとれなかった。。。たくさん並んであって、。。。。)など。参加校には、SSH採択校、一般高校、農業高校も。参加校も多様です。農業高校では、創立130年を超える、日本最古の農業高校も。
2日間に亘って、今年度の研究計画討論会などが行われ、研究の方向性、実験方法などについて、20弱の高校の研究を議論しました。ダイコンだけが研究対象でなく、物理・天文分野として、5月の金環食の観測、その他の分野では、ゼニゴケ、マングローブ、プランクトン、ミヤマクワガタ(ミヤマクワガタは、子供の頃からとろうと思ってもとれなかった。。。たくさん並んであって、。。。。)など。参加校には、SSH採択校、一般高校、農業高校も。参加校も多様です。農業高校では、創立130年を超える、日本最古の農業高校も。
ここの討論会のおもしろいというか、すごいところは、生徒さんが発表したあと、運営指導委員だけでなく、指導されている高校の先生方、実験をしている他の高校の生徒さんから、鋭い質疑が交わされるところです。高校生の目線の質疑は何より会議がactiveになります。
 ダイコンの研究をモデルとして、その研究方法、広がりなどが他の教科、科目に応用され、冬にはさらに発展したプレゼンが聞けるのが楽しみとなる会議でした。何より参加者全員の写真を載せたときに、多いこと。すごいことだと。。感動でした。
ダイコンの研究をモデルとして、その研究方法、広がりなどが他の教科、科目に応用され、冬にはさらに発展したプレゼンが聞けるのが楽しみとなる会議でした。何より参加者全員の写真を載せたときに、多いこと。すごいことだと。。感動でした。
最後になりますが、今回の会議をorganize頂きました、鹿児島県立錦江湾高校・讃岐先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。
わたなべしるす
PS. 朝の会議直前(08:46)に九州地方で大きな地震(M4.9)が。。。鹿児島に来て、ずいぶん暑かったので、めまいがしているのかなと思っていましたが、そうでなく、地面が揺れていたのは、びっくりという一方で、自分に問題がないのはほっとでした。そのあと、トカラ列島でも多くの地震(M4.3)が。。。。ちょっと気になりました。
 2日間に亘って、今年度の研究計画討論会などが行われ、研究の方向性、実験方法などについて、20弱の高校の研究を議論しました。ダイコンだけが研究対象でなく、物理・天文分野として、5月の金環食の観測、その他の分野では、ゼニゴケ、マングローブ、プランクトン、ミヤマクワガタ(ミヤマクワガタは、子供の頃からとろうと思ってもとれなかった。。。たくさん並んであって、。。。。)など。参加校には、SSH採択校、一般高校、農業高校も。参加校も多様です。農業高校では、創立130年を超える、日本最古の農業高校も。
2日間に亘って、今年度の研究計画討論会などが行われ、研究の方向性、実験方法などについて、20弱の高校の研究を議論しました。ダイコンだけが研究対象でなく、物理・天文分野として、5月の金環食の観測、その他の分野では、ゼニゴケ、マングローブ、プランクトン、ミヤマクワガタ(ミヤマクワガタは、子供の頃からとろうと思ってもとれなかった。。。たくさん並んであって、。。。。)など。参加校には、SSH採択校、一般高校、農業高校も。参加校も多様です。農業高校では、創立130年を超える、日本最古の農業高校も。ここの討論会のおもしろいというか、すごいところは、生徒さんが発表したあと、運営指導委員だけでなく、指導されている高校の先生方、実験をしている他の高校の生徒さんから、鋭い質疑が交わされるところです。高校生の目線の質疑は何より会議がactiveになります。
 ダイコンの研究をモデルとして、その研究方法、広がりなどが他の教科、科目に応用され、冬にはさらに発展したプレゼンが聞けるのが楽しみとなる会議でした。何より参加者全員の写真を載せたときに、多いこと。すごいことだと。。感動でした。
ダイコンの研究をモデルとして、その研究方法、広がりなどが他の教科、科目に応用され、冬にはさらに発展したプレゼンが聞けるのが楽しみとなる会議でした。何より参加者全員の写真を載せたときに、多いこと。すごいことだと。。感動でした。最後になりますが、今回の会議をorganize頂きました、鹿児島県立錦江湾高校・讃岐先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。
わたなべしるす
PS. 朝の会議直前(08:46)に九州地方で大きな地震(M4.9)が。。。鹿児島に来て、ずいぶん暑かったので、めまいがしているのかなと思っていましたが、そうでなく、地面が揺れていたのは、びっくりという一方で、自分に問題がないのはほっとでした。そのあと、トカラ列島でも多くの地震(M4.3)が。。。。ちょっと気になりました。