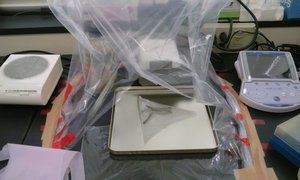SSHの運営指導委員を盛岡三、仙台三、福島、観音寺一、錦江湾高校で仰せつかっております。そんな関係もあり、パシフィコ横浜でのSSH全国の生徒研究発表会の講評者を。昨年に引き続きは、ありがたい限りです。。。いつもこの時期の関東に出てくると、夜も猛烈な暑さなのですが、熱帯夜にならない。。。朝夕には涼しい風が。。。立秋を過ぎたからでしょうか。。。不思議な。。
 最初の特別講演は、九大の数学G-COEの代表も務めた若山正人教授。たくさんの数式が出てきて、数式の部分は全く理解不能。。。ただ、生物というか、生命を理解するためにも、われわれも数学分野との連携は行っており、その重要性はわかっているつもりですが。。。研究室にある様々な機器も、数学、数理科学の基盤の上に立っているのだと。。昔は好きだった数学(高校まで。)。でも、今は数式を見ただけで。。。ただ、遺伝学も今やgenomics, transcriptome解析など、数学、統計学を利用しないわけにはいかない時代。ということを考えたのでした。最後のことばに、「どこでも数学」というのがありましたが、「どこでも遺伝学」というのもありかなと思いました。身の回りには、遺伝的に多様な動植物がありふれているのを、観察することから始まるのだから。
最初の特別講演は、九大の数学G-COEの代表も務めた若山正人教授。たくさんの数式が出てきて、数式の部分は全く理解不能。。。ただ、生物というか、生命を理解するためにも、われわれも数学分野との連携は行っており、その重要性はわかっているつもりですが。。。研究室にある様々な機器も、数学、数理科学の基盤の上に立っているのだと。。昔は好きだった数学(高校まで。)。でも、今は数式を見ただけで。。。ただ、遺伝学も今やgenomics, transcriptome解析など、数学、統計学を利用しないわけにはいかない時代。ということを考えたのでした。最後のことばに、「どこでも数学」というのがありましたが、「どこでも遺伝学」というのもありかなと思いました。身の回りには、遺伝的に多様な動植物がありふれているのを、観察することから始まるのだから。
講演のあとには、ポスタープレゼンテーションを見て、コメント。立ち止まって話し始めると、気がついたら、20min議論していたり。。。コメント時間もあっという間に終わったのは、久し振りに、パソコンの前でない生活のような気がしました。で、研究内容は、理数の様々な分野。生物領域でも、植物、動物、微生物等、多種多様。さらに基本とも言える形態学、解剖学などの観察をベースにそこから見えてくるもの。一方で、遺伝子レベルの研究も。大学生も顔負けというような。。この研究の多様性を評価する評価者は基準をどうするかなど大変だろうなと。。。。
ところで、コメントをしながら思ったのは、in vitroというか、実験系の中で何が起きているかを考えるのも大切ですが、本来その生物がいる場所、機能しているところで何をしているのか、それを考えないと、「実験のための実験」ということになりかねない。という気がしました。自然を観察することがまさに、自然科学の基本。自然の中で起きていることを常に頭に置いて、物事を考えてみるのがという気がしますが、どうでしょうか。
出前講義などでお世話になっている高校の発表、科学者の卵で活躍していた受講生が、このSSHでも大活躍などもありましたが、詳細はまた、明日ということで。

わたなべしるす
PS. SSHのtop pageのところでくるくる回る写真に、渡辺がダイコンコンソーシアムで大根の交配を指導している写真が。。。びっくりでした。ありがとうございました。
 最初の特別講演は、九大の数学G-COEの代表も務めた若山正人教授。たくさんの数式が出てきて、数式の部分は全く理解不能。。。ただ、生物というか、生命を理解するためにも、われわれも数学分野との連携は行っており、その重要性はわかっているつもりですが。。。研究室にある様々な機器も、数学、数理科学の基盤の上に立っているのだと。。昔は好きだった数学(高校まで。)。でも、今は数式を見ただけで。。。ただ、遺伝学も今やgenomics, transcriptome解析など、数学、統計学を利用しないわけにはいかない時代。ということを考えたのでした。最後のことばに、「どこでも数学」というのがありましたが、「どこでも遺伝学」というのもありかなと思いました。身の回りには、遺伝的に多様な動植物がありふれているのを、観察することから始まるのだから。
最初の特別講演は、九大の数学G-COEの代表も務めた若山正人教授。たくさんの数式が出てきて、数式の部分は全く理解不能。。。ただ、生物というか、生命を理解するためにも、われわれも数学分野との連携は行っており、その重要性はわかっているつもりですが。。。研究室にある様々な機器も、数学、数理科学の基盤の上に立っているのだと。。昔は好きだった数学(高校まで。)。でも、今は数式を見ただけで。。。ただ、遺伝学も今やgenomics, transcriptome解析など、数学、統計学を利用しないわけにはいかない時代。ということを考えたのでした。最後のことばに、「どこでも数学」というのがありましたが、「どこでも遺伝学」というのもありかなと思いました。身の回りには、遺伝的に多様な動植物がありふれているのを、観察することから始まるのだから。講演のあとには、ポスタープレゼンテーションを見て、コメント。立ち止まって話し始めると、気がついたら、20min議論していたり。。。コメント時間もあっという間に終わったのは、久し振りに、パソコンの前でない生活のような気がしました。で、研究内容は、理数の様々な分野。生物領域でも、植物、動物、微生物等、多種多様。さらに基本とも言える形態学、解剖学などの観察をベースにそこから見えてくるもの。一方で、遺伝子レベルの研究も。大学生も顔負けというような。。この研究の多様性を評価する評価者は基準をどうするかなど大変だろうなと。。。。
ところで、コメントをしながら思ったのは、in vitroというか、実験系の中で何が起きているかを考えるのも大切ですが、本来その生物がいる場所、機能しているところで何をしているのか、それを考えないと、「実験のための実験」ということになりかねない。という気がしました。自然を観察することがまさに、自然科学の基本。自然の中で起きていることを常に頭に置いて、物事を考えてみるのがという気がしますが、どうでしょうか。
出前講義などでお世話になっている高校の発表、科学者の卵で活躍していた受講生が、このSSHでも大活躍などもありましたが、詳細はまた、明日ということで。

わたなべしるす
PS. SSHのtop pageのところでくるくる回る写真に、渡辺がダイコンコンソーシアムで大根の交配を指導している写真が。。。びっくりでした。ありがとうございました。