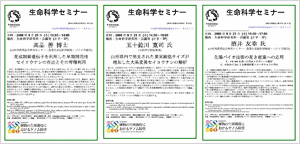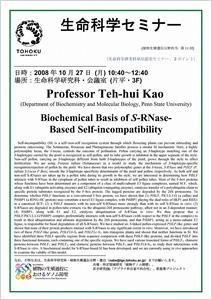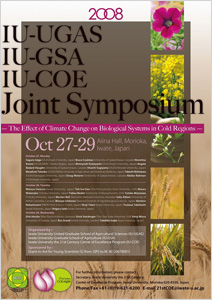生命科学セミナー「現場での問題点を先端技術で解決するために--山形県の取り組み--」を9月25日に開催します。今の生命科学研究科の1つの母体の起源である附置研の「農学研究所」は、やませという冷害克服を目指したものであり、まさに、現場の問題点の解決を目指して設置されたものでした。
今回は、従来のPlant Scienceのfront runnerと言うよりは、そうした現場からという観点で、山形県から高品博士、五十鈴川氏、酒井氏をお招きして、花成誘導、倍数化、メタボローム、変異体の誘発という様々な角度から、お話を頂きます。
高品博士が、13:00-14:00, 五十鈴川氏が、14:00-15:00, 酒井氏が、15:00-17:00です。
少し、現場色が強いセミナーかもしれないですが、昨今の温暖化、食糧問題を考えるためのヒントになるのではないかと思います。ぜひ、ご参加いただければと思います。
9/25(Thr), 13:00~17:00に、片平の会議室で行います。
たくさんのご来場をお待ちしております。
わたなべ
生命科学セミナー「現場での問題点を先端技術で解決するために--山形県の取り組み--」を9月25日に開催
2008年9月19日 (金)
生命科学セミナー「Biochemical Basis of S-RNase-Based Self-incompatibility」を10月27日に開催
2008年9月10日 (水)
生命科学セミナー「Biochemical Basis of S-RNase-Based Self-incompatibility」を10月27日に開催します。国際シンポジウムがあり、アメリカ・ペンシルバニア州立大学のProfessor Teh-hui Kaoが来仙することから、セミナーをお願いしました。Professor Kaoは、Cornell大、Penn State大でアブラナ科植物、ナス科植物の自家不和合性因子を同定、機能解析された方で、現在は、ナス科植物の自家不和合性因子が、雌雄でどのように相互作用されているのかを、in vitroの系で生化学的に研究を進められております。この系には、RNaseによる核酸分解系、26Sプロテアソームによるタンパク質分解系が関係しており、植物限らず、ホットな分野だと思いますので、ぜひ、ご参加いただければと思います。
10/27(Mon), 10:40~12:40に、片平の会議室で行います。
たくさんのご来場をお待ちしております。
わたなべ
2008 21COE Joint Symposiumの開催(10/27-29)
2008年8月20日 (水)
しばらく先の話になるかもしれないですが、ご予定のつく方は、ぜひ、ご参加ください。
渡辺が併任しております、岩手大21COEが主催となり、渡辺が頂いている科研費・若手研究(S)が共催となるJoint Symposiumを10/27-29に開催します。副題として、「The effect of Climate Change on Biological Systems in Cold Regions」をつけてあり、ストレス、生殖、進化、等、複合的な観点からのシンポジウムになります。
場所は、岩手県盛岡市のAllina Hallです。参加は無料です。
渡辺は、アブラナ科植物の自家不和合性の最近の進歩についてお話をして、counter partとして、Penn State Univ.のProf. Kaoを招いて、ペチュニアを用いた配偶体型自家不和合性について、お話しいただきます。他にも国内外から著名な方をお招きしますので、ぜひ、ご参加ください。
みなさまとお会いできるのを楽しみにして。
岩手大・21COEのsiteもご覧ください。
http://www.iwate-u.ac.jp/coe/coesympo.html
わたなべしるす
共同研究成果:イネ・BT型細胞質雄性不稔の稔性回復機構解明
2008年8月11日 (月)

イネはアジアを中心とした数億の民の食糧であるとともに、近年はバイオエタノール、バイオマテリアルへの利用の可能性も示唆され、応用度の高いモデル植物といえる。イネを高収量で生産するための手法として、中国などでは雑種強勢によるF1品種育成がなされている。その基礎技術となるのが、細胞質雄性不稔である。
BT型細胞質雄性不稔は、品種Chinsurah Boro II細胞質に由来し、ORF79が蓄積することにより、不稔性が誘発されることは明らかになっていた。また、その稔性を回復させるために、PPR(pnetatricopeptide-repeat)タンパク質をコードするRF1が重要であることは示されていた。しかしながら、その分子機構は不明であった。
当研究室では、本学農学研究科・鳥山教授、名古屋大・杉田教授との共同研究により、ORF79タンパク質の蓄積の量的制御が不稔性に影響していること、RF1タンパク質が直接的に、atp6-orf79転写産物のプロセッシングを制御し、稔性を回復させていることを示した。今後はこの研究をさらに発展させて、さらなる分子メカニズムを解明したい。
この研究内容をPlant J. (2008) 55: 619-628に発表した。なお、Plant J.のImpact factorは、6.8である。
以上の論文のabstractは以下のリンクから是非ご覧ください。
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-313X.2008.03529.x
わたなべ
"Self-incompatibility in Flowering Plants - Evolution, Diversity, and Mechanisms" (Ed.: V. E. Franklin-Tong), Springerに執筆
2008年7月14日 (月)

"Self-incompatibility in Flowering Plants - Evolution, Diversity, and Mechanisms" (Ed.: V. E. Franklin-Tong)と題する植物の自家不和合性について、多方面からの抄録を集めた本が"Springer"から、出版され、その中のChapter 7に、"Milestones identifying self-incompatibility genes in Brassica species: From old stories to new findings"と言うタイトルで、アブラナ科自家不和合性のこれまでの研究をまとめたものを発表しました。
自家不和合性の研究は古く、C. Darwinの著書にもありますが、アブラナを例にとれば、その分子機構が分かったのは、ここ10年ほどの研究の進展の賜物です。その研究に寄与でき、また、この様な本に執筆できたのは、うれしい限りです。
自分たちが発見したmilestoneに続いて、これからの10年で新たなmilestoneとなるような発見を論文に発表できればと思います。
わたなべ