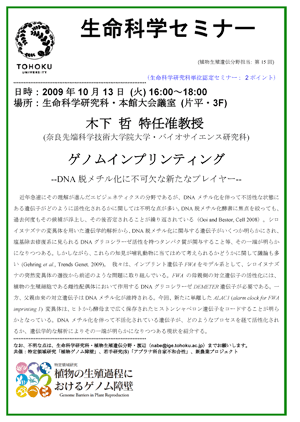今まで様々な学会などから依頼があり、講演を行ってきました。出前講義などもそれに該当するのかもしれません。そんな中、サイエンスをいかに一般の人にもわかってもらうかということのために、「サイエンスイラスト」は欠かせない存在です。数年前のプロジェクトから、ポスター、ポンチ絵などを作製してもらった経験から、このようなフォーラムに招待されました。
日 時: 10 月24 日(土)12:30 ~ 14:30
会 場:第19 会場(神戸国際展示場2 号館3 階3A 会議室)
オーガナイザー:三輪佳宏(筑波大学)、小林麻己人(筑波大学)
渡辺は、
13:10 ~ 13:35 ポンチ絵をかえれば、あなたの教育・研究・研究費が変わる!
---サイエンスデザイナーによる劇的ビフォー・アフター!---
ということで、今までの経験をお話しします。
植物科学、遺伝学、育種学を中心にやってきましたが、生化学という違う立場の人からのお誘いに、少々、緊張しておりますが、お時間のある方、学会に出られる方は、10/24に神戸でお会いしたいと思います。
わたなべしるす