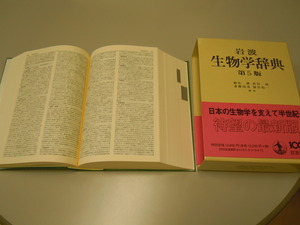JSTが発行している「Science Window」。小中高向けということらしいですが、大学にいるものが読んでも、へーーと思うようなこと、こんなことだったのだということがあります。JSTといえば、今日は、SSH実施校の山形県立鶴岡南高等学校が、研究室訪問をしてくれ、実験、見学、講義を受けて、行かれました。
今日、発表された、Science Window 2013年 春号(4-6月)の「せんせいクラブ」に、書評「実体験が大切なのでは」という文章が掲載されました。前回のトピックは、「情報と学び」でした。最近、いろいろなところで出前講義を行います。そうした時、感じるのは、今のこともたちはいろいろなことを知っている、Internetなどのおかげもあったりで。ところが、実際に体験をしてないので、何となくとか、ぼんやりとしか思いがないというか。。。体験、経験をしたら、それに伴って、五感が動くので、いろいろなことを覚えていると。。。今考えても、子供の頃に、あんなことをしたとか、その時に、覚えた花の蜜の味とか、忘れないものがあります。何とか、実体験ができる世の中になればと。。。
今回のScience Windowでは、色、絵を描くこと。色は、植物の花を見ているので、きれいと思う訳ですが、絵を描くのは、苦手でした。どう見ても、目の前のものとは違う絵になっていて。。。小中学校の絵を描く時間は、。。。でした。その中に、植物学者の牧野富太郎の話が。確か、高知県の出身で、植物園もあって、小さい頃にいったのを思い出しました。楽しめた誌面でした。

長くなりました。お時間のある方は、
Science Window 2013年 春号(4-6月)(file size 13.73MB)
Science Window 2013年 冬号(1-3月)(file size 10.4MB)
をdownloadしてお読み頂ければ、幸いです。
わたなべしるす
PS. 連載ものの「いにしえの心」というページを解説されていたのが、奈良先端科学技術大学院大学の学長をされている磯貝彰先生。磯貝先生とは、東北大で日向研究室に配属されて、共同研究ということで、初めて、研究室に伺ったのは、4年生の6月。実験に使うタンパク質のサンプルをいただくため。1987年でした。その当時、磯貝先生の所属は、東京大学農学部。それから、25年以上、アブラナ科植物の自家不和合性研究が、ここまで発展できたのも、磯貝先生とのよい共同研究ができたからだと思っています。そして、自分が書いた記事と磯貝先生の記事が同じ紙面に載るというのは、本当に不思議なご縁というか、うれしい限りでした。。。。ありがとうございました。
今日、発表された、Science Window 2013年 春号(4-6月)の「せんせいクラブ」に、書評「実体験が大切なのでは」という文章が掲載されました。前回のトピックは、「情報と学び」でした。最近、いろいろなところで出前講義を行います。そうした時、感じるのは、今のこともたちはいろいろなことを知っている、Internetなどのおかげもあったりで。ところが、実際に体験をしてないので、何となくとか、ぼんやりとしか思いがないというか。。。体験、経験をしたら、それに伴って、五感が動くので、いろいろなことを覚えていると。。。今考えても、子供の頃に、あんなことをしたとか、その時に、覚えた花の蜜の味とか、忘れないものがあります。何とか、実体験ができる世の中になればと。。。
今回のScience Windowでは、色、絵を描くこと。色は、植物の花を見ているので、きれいと思う訳ですが、絵を描くのは、苦手でした。どう見ても、目の前のものとは違う絵になっていて。。。小中学校の絵を描く時間は、。。。でした。その中に、植物学者の牧野富太郎の話が。確か、高知県の出身で、植物園もあって、小さい頃にいったのを思い出しました。楽しめた誌面でした。

長くなりました。お時間のある方は、
Science Window 2013年 春号(4-6月)(file size 13.73MB)
Science Window 2013年 冬号(1-3月)(file size 10.4MB)
をdownloadしてお読み頂ければ、幸いです。
わたなべしるす
PS. 連載ものの「いにしえの心」というページを解説されていたのが、奈良先端科学技術大学院大学の学長をされている磯貝彰先生。磯貝先生とは、東北大で日向研究室に配属されて、共同研究ということで、初めて、研究室に伺ったのは、4年生の6月。実験に使うタンパク質のサンプルをいただくため。1987年でした。その当時、磯貝先生の所属は、東京大学農学部。それから、25年以上、アブラナ科植物の自家不和合性研究が、ここまで発展できたのも、磯貝先生とのよい共同研究ができたからだと思っています。そして、自分が書いた記事と磯貝先生の記事が同じ紙面に載るというのは、本当に不思議なご縁というか、うれしい限りでした。。。。ありがとうございました。